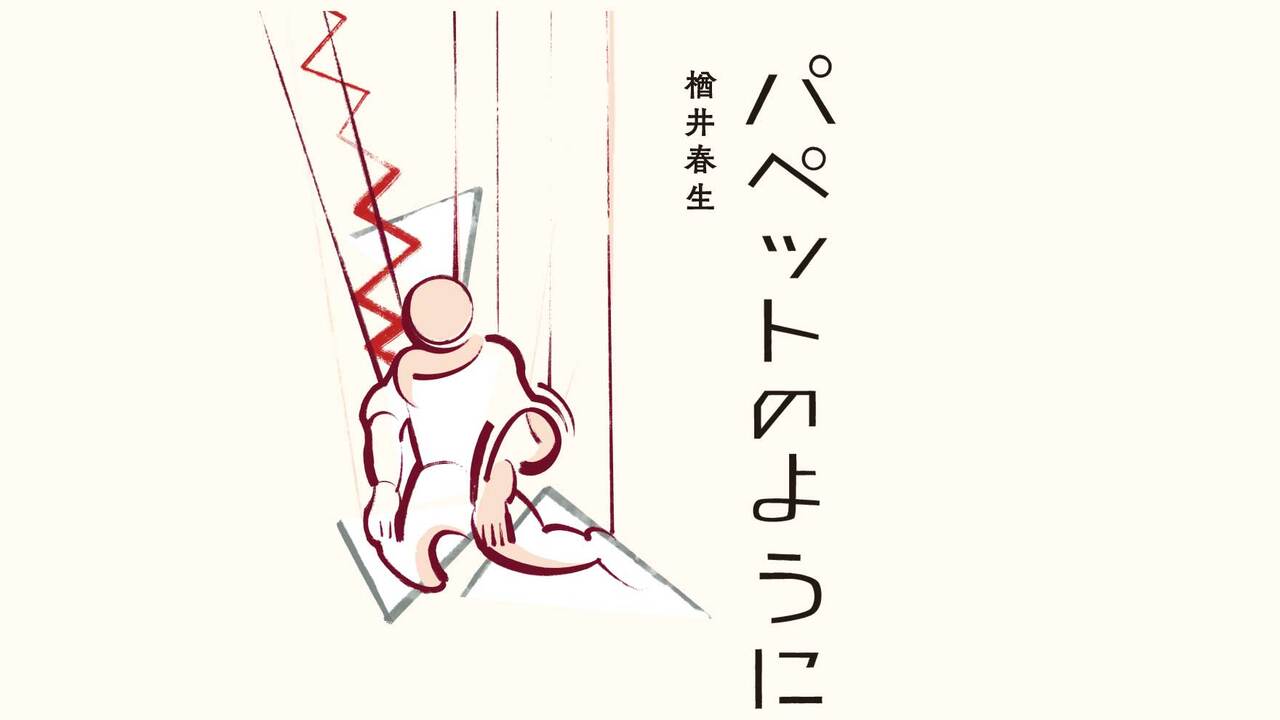一部 ボートショーは踊る
四
ジムは俊夫を誘って公園に入って行き、公園の中の一角にある小さな喫茶店の前のテラスのベンチに腰を下ろした。愛想のいい笑顔を浮かべて近付いて来たウェイトレスに紅茶を注文した。二人は紅茶をすすりながら業界の噂話に興じた。お互いに業界の隅々まで知り尽くしている安心感が話を弾ませる。
話題は業界の古い世代と新しい世代の交替についてといったものから、業界の有力者たちの誰彼のゴシップめいた話にまで及んだ。
「ところで、君はその大和電気での経験を入れると何年になる。この業界で」
「三十年、いや、もっとになりますか」
「なるほど、じゃあ私と似たり寄ったりだ。年から考えて、私の方が少し長そうだが。私はサラリーマン生活抜きでおやじの後を継いでオーシャントレックの経営を始めた。最初の何年かはおやじの見習いだったがね」
「マリンの業界を最初は私は好きではなかったが、何時の間にかどっぷり浸つ かり込んでしまった。この狭い業界はとっても居心地がいいので」
「狭い」
ジムは疑問を呈するように首を傾かしげた。
「確かに小さな業界だ。マリンエレクトロニクスに限っていえば、世界中の売上を合わせてもたかだか一千億ドル余りだろう。だが、狭いというのは考え違いだよ、君。我々の業界は広大な宇宙のシンボルのようなものだ。ちっちゃな船が何千、何万、いや、何十万、何百万隻が対象だ。そのそれぞれの船にもそれぞれに完結した社会がある。そして何より海だよ。
我々業界の環境をなす海だよ。そこは地球の一部でありながら壮大な宇宙そのものでもある。生命を育んだ海は地球を越えた生命のシンボルだ。海なしに我々人間を含めてすべての生命体は育たなかった。そこが我々の業界の場なんだよ。私はこの業界にいることに誇りすら感じている」
公園で朝のすがすがしい空気を吸い、爽やかな風を肌に感じながら語るのには哲学的な話題は相応しいとはいえない。だが、そんなジムの論調はまさに哲学的な域に達していて、しかも自然と俊夫の心に染しみ込んで来る。