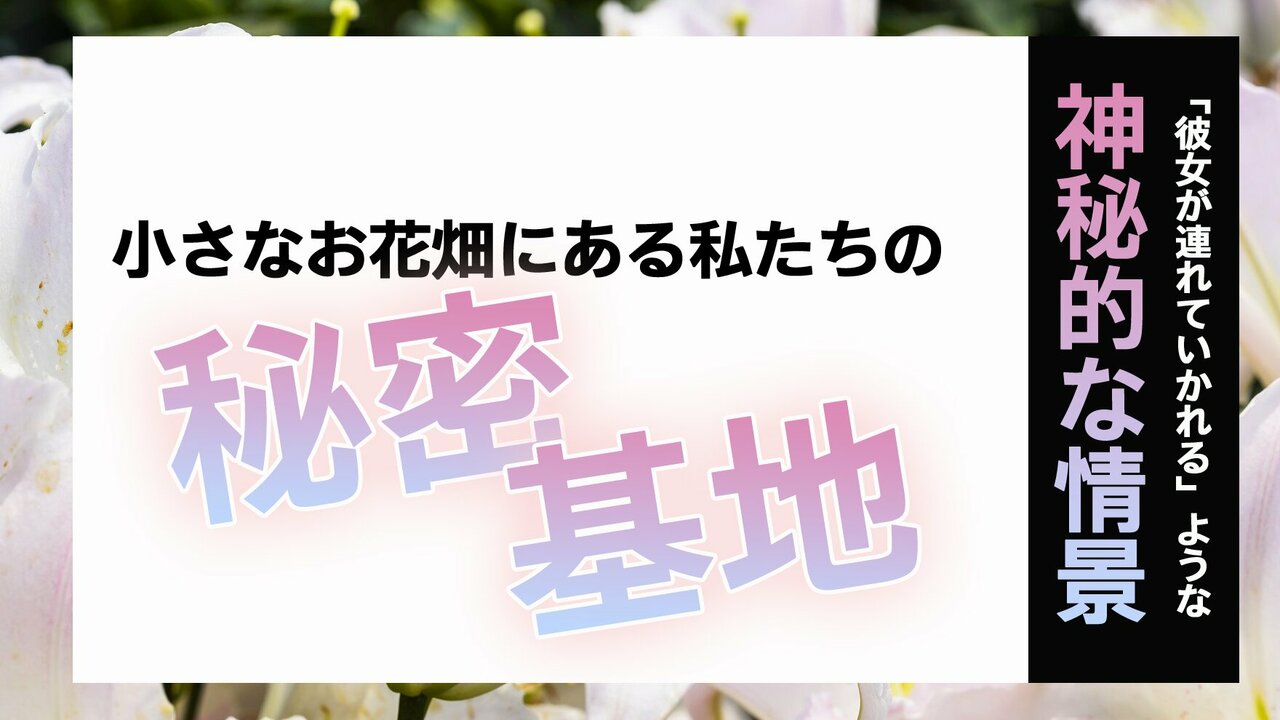4
次に彼女が口を開いたのは、ノルマ分の書架整理が終わった頃、私が足場を片付けている時だ。
「そもそも、海も空も本当は青くないんだよね」
本の詰まったダンボールを難儀そうに持ち上げながら、彼女は呻くように呟いた。
「その話生きてたの?」
「うん。どっちも太陽の光が散乱して、光の青いところだけがその場に残るから、海も空も青く見えるんだって」
「ふうん」
初めて聞く知識だったから、話が完全に脱線していることにも気づかず素直に頷いてしまう。海の青さは空の色が映ったものだと思っていたし、その空の色は宇宙の暗闇が薄まったものだと思っていた。それがまさか太陽の光が散ったものだったとは……なんだか、
「不思議でしょ?」
さよちゃんが私の気持ちを代弁するかのように、そう言った。
「目に見えているものは、その人の知識と感性で構築されているんだよ」
「誰かの言葉?」
思わず訊き返していた。
素敵な言葉だと思ったからだ。本を率先して読まない私でもわかる……洗練された言葉だ。きっと著名な哲学者だとか物理学者の言葉に違いない、そう当たりをつけた。
「さあ? 今思いついたんだけど……でもこのくらいのこと、きっともう誰かが言ってるでしょうね」
私の思考を読んでいたとでもいうように、さよちゃんは得意げに微笑む。その表情が勝ち誇っているように見えたのは、私が彼女に対して「負けた」と感じているからかもしれない。さよちゃんの言葉を聞いた後だとますますそう思う。思わされる。
出会ってから何度も、私はこういう「はっきりしない敗北感」を味わってきた。彼女に対して敵わない、抗えない、掴めない、といった感情を抱いてきた。彼女と私の間には、近くにいるのに決定的に埋められない距離があって、彼女と話すたび、傍に立つたび、その距離がどんどん広がっていくように感じられた。
でもそれが嫌なわけではない。
むしろ逆で──触れられないから、辿り着かないからこそ安心して近寄っていける……私が何をしようと穢れることはない、そういう絶対的な領域に彼女はいた。
これは尊敬や憧れだろうか? 何度も考えたことがある。「いいや違う」私はさよちゃんに勝ちたいと思ったことはないし、彼女みたいになりたいと思ったこともない。ただ、ただ……そう、たとえるなら月を眺めることに似ている。
手に入らなくてもいい、ただそこにあるものを、見ていることさえできれば。彼女に対する私の感情はそういうものなのだと、私は理解していた。
これを名前で呼ぶのなら、何だろうか?