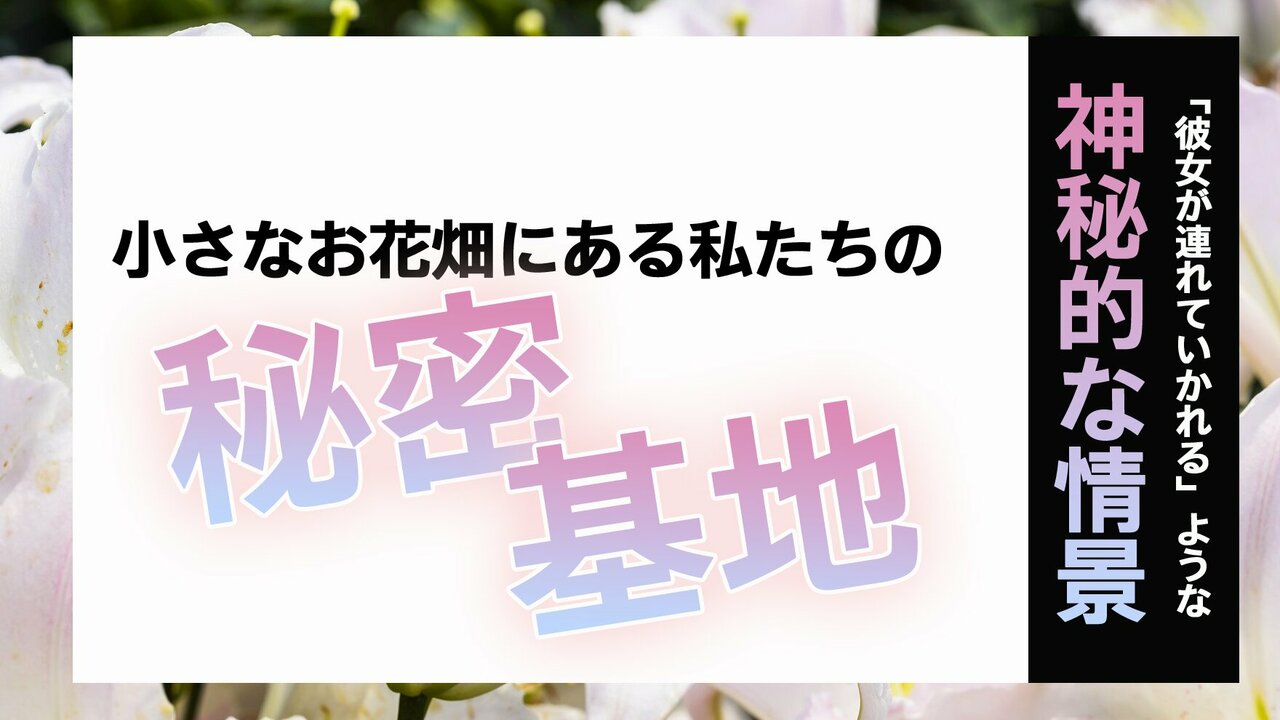0
七年前の、とある夏の日──家の裏手にある山で、私は墓を掘っていた。彼女と別れるために。シャベルを土に突き入れ、削り、掬い、放る。単純だが過酷な動作を、何度も何度も繰り返し、固い土を掘り返す。体の節々が軋み不満の声を、手の皮が悲鳴を上げている。額を伝った汗が目に入って煩わしい。
……顔が汚れるのも構わずそれを拭っても、汗はどんどん流れてきて、気休めにもならない。肌に張り付いた衣服が気持ち悪かった。暑さと、痛みと、不快感で、頭の中はぐちゃぐちゃになっていたけれど……黙々とシャベルを振るった。そうすることしかできなかった。
そんな苦労の甲斐もあって……いや、こんな大変な目に遭っているにも関わらず、目当ての物は酷くあっけなく見つかる。乾いた土の隙間から控え目に顔を覗かせたのは──象牙質の塊──骨だ。シャベルを振るう手を止めて、しばらくその物体に目を奪われる。
……どれくらいそうしていただろう。突然、表出した骨がきらりと光り、私の意識は引き戻される。さっきまで滝のように流れていた汗は嘘のように引いていて、肌は乾き、体は冷え切っている。あちこちから降り注ぐヒグラシの鳴き声も相まって夏とは思えないほど空気が寒く感じられた。無意識に背中が震える。一瞬、けれど大きく。痙攣するようにびくりと跳ね上がった。
厚い木々に覆われているこの場所は日差しがあまり届かない。それなのに骨に光が届いた、ということは──空に視線を移す、太陽が西に傾き始めていた。
……急がなくてはならない。庭のように駆け回った場所とはいえ夜の山を歩く勇気はない。陽が沈んでしまう前に下りなくては。作業を再開しようとシャベルを持つ手に力を入れた瞬間、さきほどとは比べられないほどの痛みが走った。
見ると持ち手の部分が赤く滲んでいる。豆が潰れたのだろう。汗だと思っていた水気は、血だったのだ。もう一度シャベルを握り直す。熱を伴った痛みが手の中に広がるが、それを無視してなおも強く、隙間なく持ち手を握り込んだ。シャベルを土に突き入れ、削り、掬い、放る。その動作一つひとつに痛みが奔る。
その痛みを紛らわせたくて、動作は次第に乱暴に、感情的になっていく。結果、余計な力が加わり手の痛みは増していった。悪循環──それでも手を止めず、シャベルを振るい続けた。私はこの痛みを二度と忘れないだろう。たぶん、一生。それは皮肉にも、七年前に思い浮かべた言葉と、まったく同じものだった。今、夏のその日に──実家の裏山で、私は百合を掘っていた。彼女に会うために。