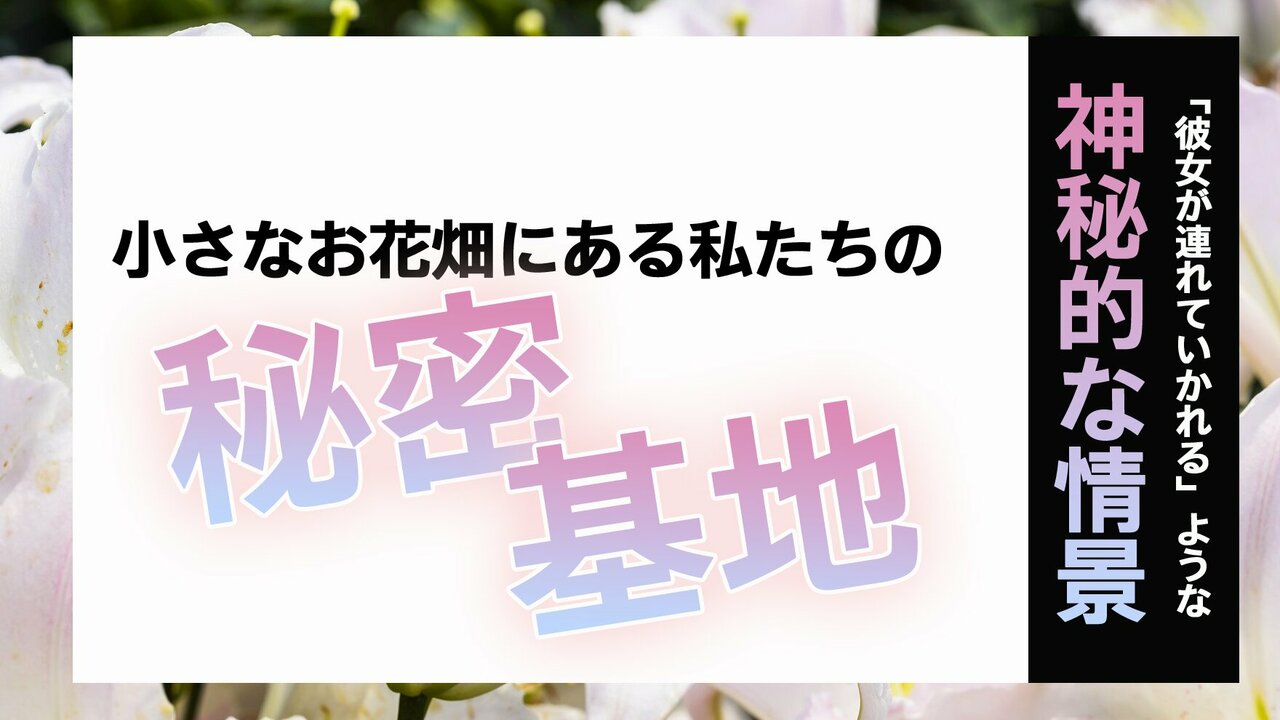1
二人の女生徒に目が行った。夏服に身を包んだあか抜けない少女たち。彼女らは席が選び放題、座り放題の車内で敢えて席に着かず、扉の傍に立ち、振動で体が揺れることなんて気にもとめずお喋りに興じている。
会話は聞こえないが、ころころと変わる表情から察するにその内容は二人にとって有意義なのだろう。いや、本当は内容なんてどうでも良くて、その時間が有意義なのだろうと思った。下校中の電車で二人がお喋りする、その時間が大切なのだ。私にはそう思えた。私たちも先日まではああいう時間を過ごしていたから。
先日といっても、もう七年も前のことだけれど……「彼女」との時間は色褪せることなく私の中に残っている。それこそ「つい昨日のことのように」思い出せる。「つい昨日のことのように」それは過去を振り返る時の常套句。あらゆる文章で多用される比喩表現だが、私はこの言い回しが気に入っていた。
昨日──それは今日から最も近い過去だ。それは過去ではあるが昔というほど遠い物ではなく、しかし物理的に今日ということは絶対に有り得ないタイムスタンプ。生きていれば常に更新される最新の過去、それが「昨日」。通常「昨日」は一つしかないけれど、私の「昨日」はいくつも存在している。そしてそのどれにも彼女がいた。
そう……ちょうど今、そこにいる女生徒たちのように、私と彼女が下校中に楽しくお喋りしている、そんな「昨日」がたくさんあった。その日も今日みたいな晴れた日で、夏休みにも関わらず委員会の予定があって登校していた。
その帰り道に──と、見知らぬ少女たちに過去の自分を重ねようとして失敗する。視界が大きくぶれたのだ。はっと意識を引き戻される。いつの間にか電車は止まっていて、間の抜けた息を吐きながら、さっさと出ろとでも言いたげに扉を開いていた。目的地に着いたと気づいた私は慌てて鞄を引っ掴み、席を立った。
実家の最寄り駅は相変わらずだった。言葉通りの意味だ。見た目に変わった所がない。社会人になってから年二回、盆と正月は必ず帰って来るようにしているから大きく時間を空けたことはないが、通学に利用していた七年前と比較してもほとんど変わっていない。
建物自体は新しい木造の駅舎は、利用者が少ないからか、はたまた手入れが行き届いているからか寂れた感じはなく、山の中にある駅にしては清潔感があった。外壁の塗料の具合を見ればわかる。構内にある自販機も、七年以上置かれているにしては綺麗だ。
改札を抜けて外へ出る。そこから見える景色も。建物や植生に大きな変化はなく、特別な感慨は湧いてこなかった。……ただ、むしろ変化がないからだろうか。駅から出ていつも通りの景色があって、そこで最初に空気を吸うと、都会の自宅とは違った意味で妙な安心感を覚えた。帰ってきたのだ、と思った。なんとなくその場を動かなかった。
この駅で降りたのは私だけだったから通行の邪魔になることはない。駅に入って来る人も視界の中には見当たらない。山の中の駅舎で、一人、しかし孤独は感じない。周囲は自然の所作で粛々と賑わっている。木々が軋む音、葉っぱの群れの羽ばたき、影の隙間を縫って迫って来る風の声……人の意思が介在しない不規則な響きが、耳に心地よかった。