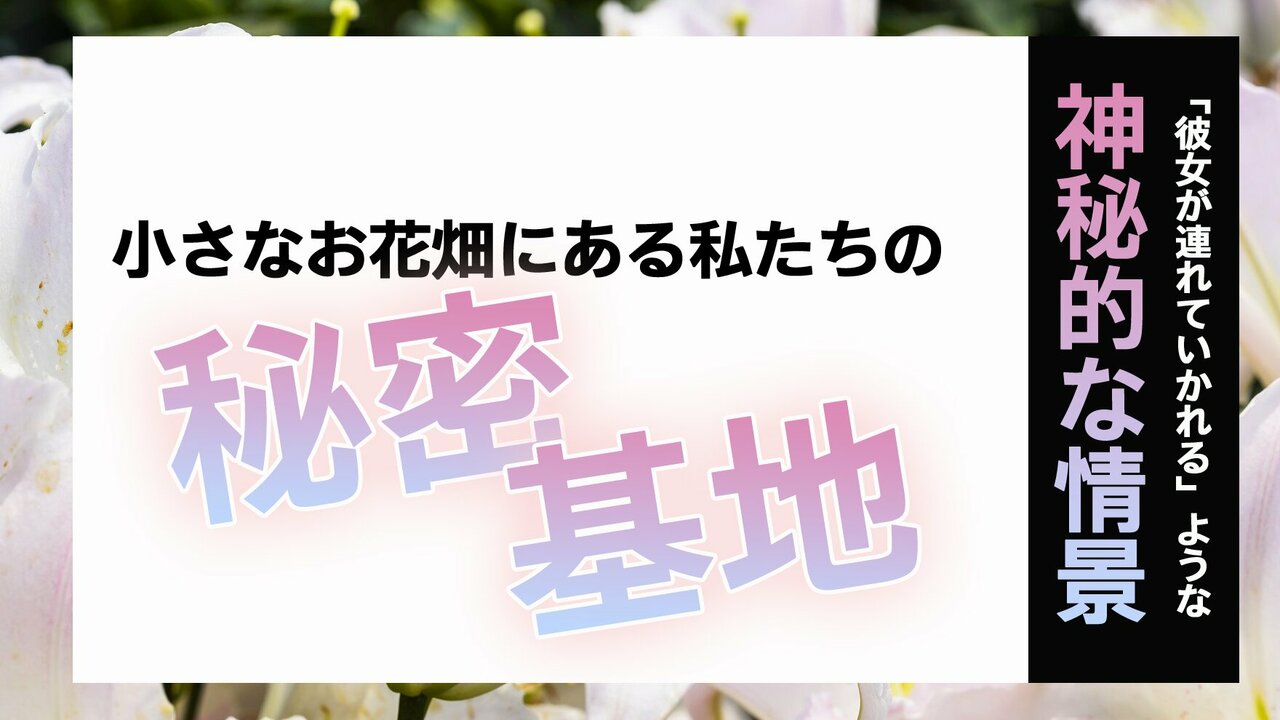「降りた駅は人が滅んだ世界に繋がっていた」。不意にそんな言葉が思い浮かぶ。現状にぴたりと当てはまる言葉だけれど、それ単体で見れば、まるで大衆映画のキャッチコピー然とした文句にも捉えられる。きっと内容はゾンビウイルスが蔓延するパニックホラーだろう。
そこまで想像して一人にやけている私に、近づいてくる影があった。
「ゆたかちゃん、おがえり」
しゃがれた男性の声に振り向くと、駅員のおじちゃんがほうきとチリ取りを持って立っていた。通学に利用していた七年前よりもっと以前、私が子供の頃からこの駅で働き、村の人々の行き交いを見守ってきた人だ。
こちらの名前などとっくに知られていて、帰省するたび声を掛けてくれる。けれど私はおじちゃんの名前を知らない。薄情かもしれないが、長い付き合いではあっても深い付き合いではないのだ、それぐらいがちょうどいいのだと思っている。
「ご無沙汰してます」
素直に「ただいま」と言えばいいのに、咄嗟に口を衝いたのは大人ぶって社交辞令じみた、角ばった言葉だった。少なくとも学生時代は「ただいま」と返していた気がするが……いつの間にか身内以外にそう言うのが気恥ずかしくなって、言えなくなっていた。
他人行儀な言葉に気分を害した様子もなく、むしろ嬉しそうに、歳のせいか日焼けのせいか浅黒くなった顔をにかっとほころばせると、おじちゃんはそのまま駐輪場のほうへ歩いて行った。