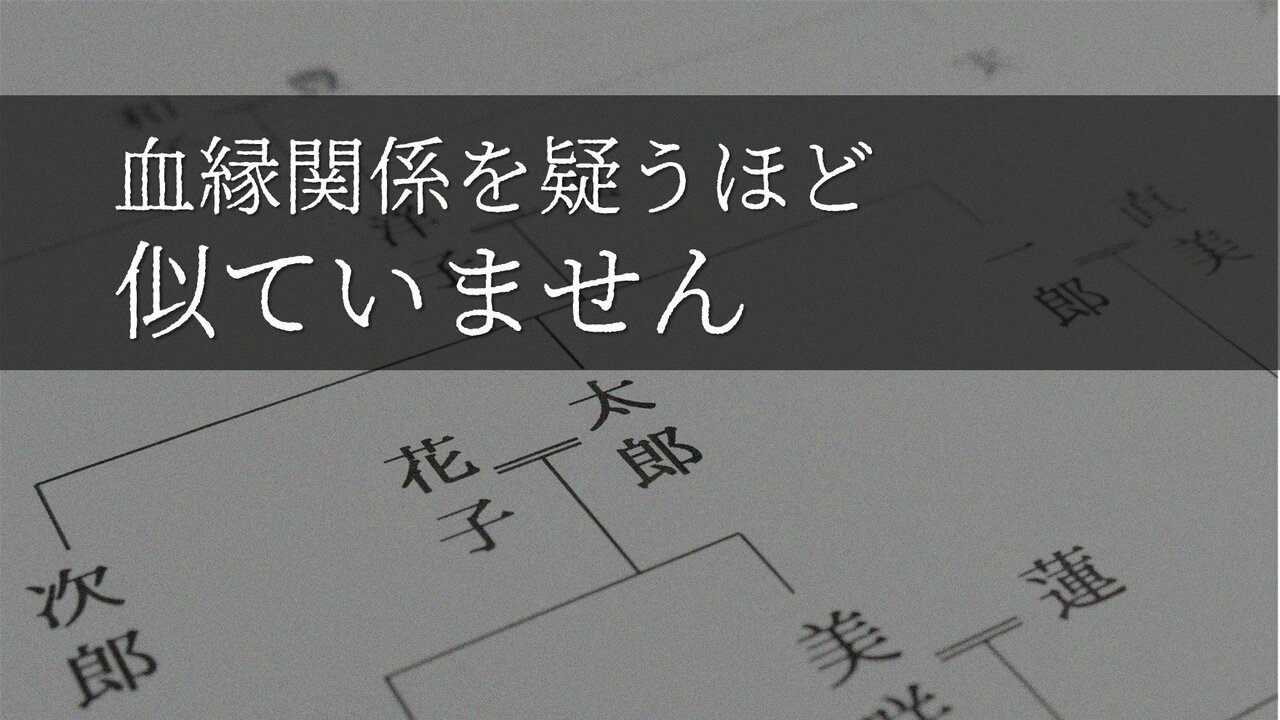一九七〇年 夏~秋
4 マユミの嘘泣き
「おまはん、いったいこんな時間までなんしょうったんで」母は荒げた声で夫に食ってかかりました。
「志乃はんの恨みが聞こえんのんか。このアホたんが。高はんと毎晩毎晩遊び呆(ほう)けくさって。たいがいならええわ」
抑えに抑えてきた母の怒りが爆発します。
「ほれと農協から振り込まれた乳の銭はどこいやったん。瓜の銭はいつ入ってくるん。今日も農協の課長はんに、山野はん、早う塩代入れてもらわな困るっち言われたんじゃけん。あと払うてないんはうちだけじゃって」
父は無言で聞き流していました。その態度がまた母の神経を逆撫でしたようです。
「みな飲んでひもたんか。銭もないのに。貧乏人が高はんみとうなんと一緒んなって。おまはん、飲み屋の女に馬鹿にされとんのがわからんの。牛臭い言われるけん、牛舎の仕事をいっちょも手伝わんのんじゃろ。わかっとるんでよ」
言い募るほどに激していきます。
「ほれでのうても、おまはんみたいな不細工なん、女が相手にするわけないじゃろが。鼻クソびゃあの銭持って行っきょるけんチヤホヤされとるだけじゃのに」
罵倒(ばとう)の材料は父の容姿にまで及びました。ずんぐりむっくりで広いおでこに奥目の父は、足が長くて彫りの深い顔の祖父とは、血縁関係を疑うほど似ていません。
祖父は村の大抵の女子衆(おなごごし)と懇(ねんごろ)ろになり、祖母がホッカアなのをいいことに、流した浮き名は一つや二つではありませんでした。元は内気で朴訥(ぼくとつ)な父が、似合わない飲み屋通いを続けているのは、悪友たる高雄さんの影響が大きいのですが、祖父への競争心みたいなものも働いていたのかもしれません。
「うちがどんな思いで仕事しょうるん。朝から晩まで牛の世話して畑して炊事洗濯掃除して、晩は晩でちょっとでもと思うて他人さんの服を縫いよんでえか。ほの金でテレビも洗濯機も炊飯器も冷蔵庫も、何もかんもぜえんぶ買うたんでよ。おまはんが鼻クソびゃあ稼いでくる日雇いの銭も、ジイやバアがヘソ繰(く)って孫に玩具の一つも買うてやるでもない銭も、うちはびた一文もろうとらんけん。ほれのにほれのにおまはんは……」
仕舞いに悔し泣きが入ります。雑巾を壁に投げつけるような音がしました。
「だあっとれ。ボケが」
普段は温厚な父が手を出したのでした。
「黙っとらんわ。このスカタン」
母は逆上しました。両手を振り回して父に打ちかかります。
「おどれこら、いよいよ張りまされなわからんのか」
父の平手は酔いのせいで加減を忘れた拳骨に変わり、それが母の前歯をへし折りました。それでもなお母は髪の毛を振り乱し、鼠(ねずみ)を食ったような口で喚きます。父が益々猛(たけ)り狂いました。