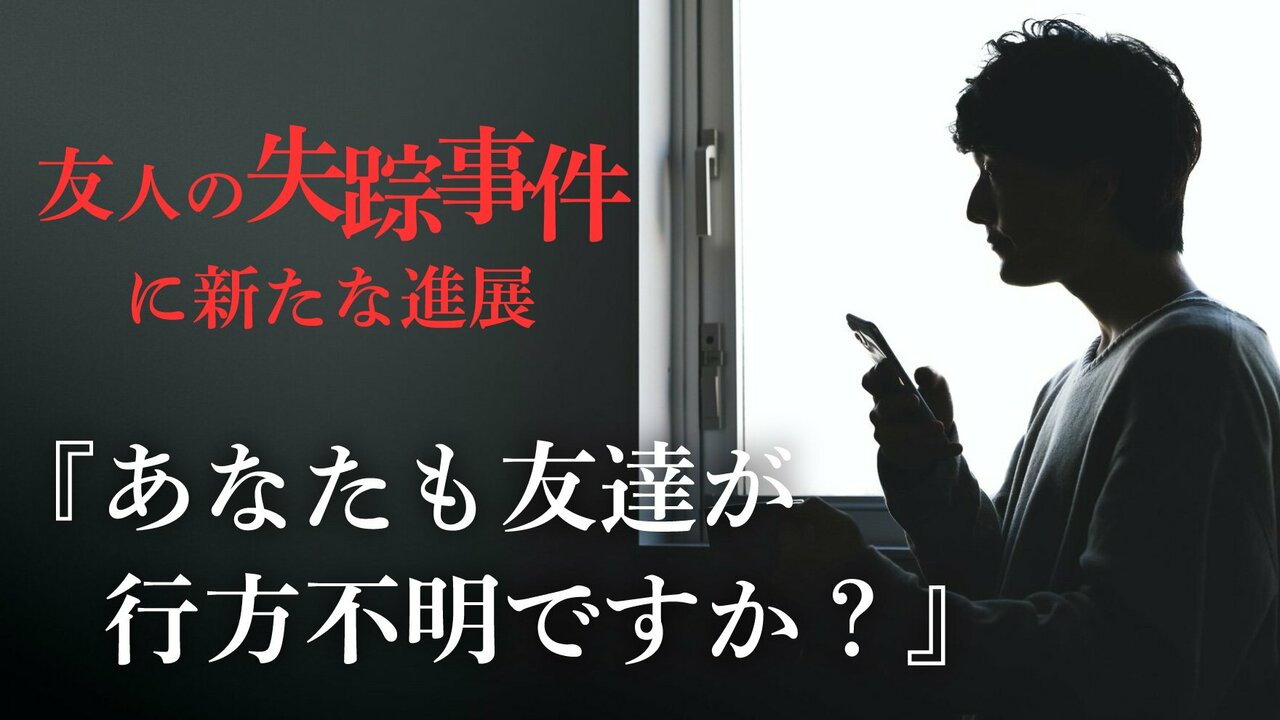2
愛瞳の家を出ると、二人は一度警察署に戻るために、車に戻った。
「なに不満そうな顔してんだ?」
谷山は、苦味が口いっぱいに広がったような顔をしながら、ハンドルを握っている。
「不満なんじゃありませんよ。呆れてるんです。あんなこと、確証があるわけでもないのに話すなんて……行儀よくしてくださいって言ったのに」
ため息混じりに谷山が言う。伏見のそういう話には慣れっこである谷山だが、まさかあの場で話し出すとは思わなかったらしい。
「いや、行儀は悪くなかっただろ。まあ……確かに今のところそれだという証拠はない。けど、確証がまったくないってわけでもない。俺があの手の話をすると、大半の人間は否定するけど、俺もな、何でもかんでも“そっち”に結びつけてるわけじゃなく、それなりの根拠があって言ってるんだぞ?」
「それは分かっていますよ。でも、いきなりあれは……」
「遠まわしに言ったところで、伝わるような話じゃない。むしろ、もし相手が確証をもてない不思議な出来事を見たり聞いたりしていた場合、こっちから心を開くことで、この人なら聞いてくれるかもしれないと思って、話すかもしれないだろ?」
「そういうものですかね……」
「俺はそう思うよ」
口元を緩めながら、伏見は言った。
(しかし、今回の事件が、もしカシマレイコの仕業だとしたら、いったい何のために?)
車の外を流れる景色を見ながら、思考を巡らせる。
カシマレイコは、古くからある都市伝説。“そっち”の人脈である、口裂け女や人面犬の存在を知っている伏見からすると、カシマレイコが実在していても、それほど驚きはない。人間と妖怪、お互いがお互いの常識を持ち込まなければ、共存も可能だろう。しかし、事件を起こすとなると、話は違ってくる。妖怪を処罰する法律はないが、止めなければならない。
「あ、谷山、俺は途中で降りる」
思いついたように、伏見は言った。
「え? どこかへ行くんですか?」
「ちょっとな」
「情報収集するフリをして、サボりに行くわけじゃないでしょうね……?」
「そんなしょうもないことするかよ。もし何か分かったら、連絡をくれ」
「分かりました」
伏見は車を降りると、情報提供者に会うために、とある店に向かった。まだ少し時間が早いが、どこかで軽く食事をしてからいけば、ちょうどいいだろう。カシマレイコが、妖怪なのか、幽霊の類なのか、どこに属するのかは分からない。しかし、“そっち”側にいるやつに聴くなら、カシマレイコがどっちだろうと、あまり問題ではない。
「おっと、酒を用意しないとな」
情報には対価がいる。伏見は、店に行く足の方向を変え、何度か行ったことがある酒屋に向けた。