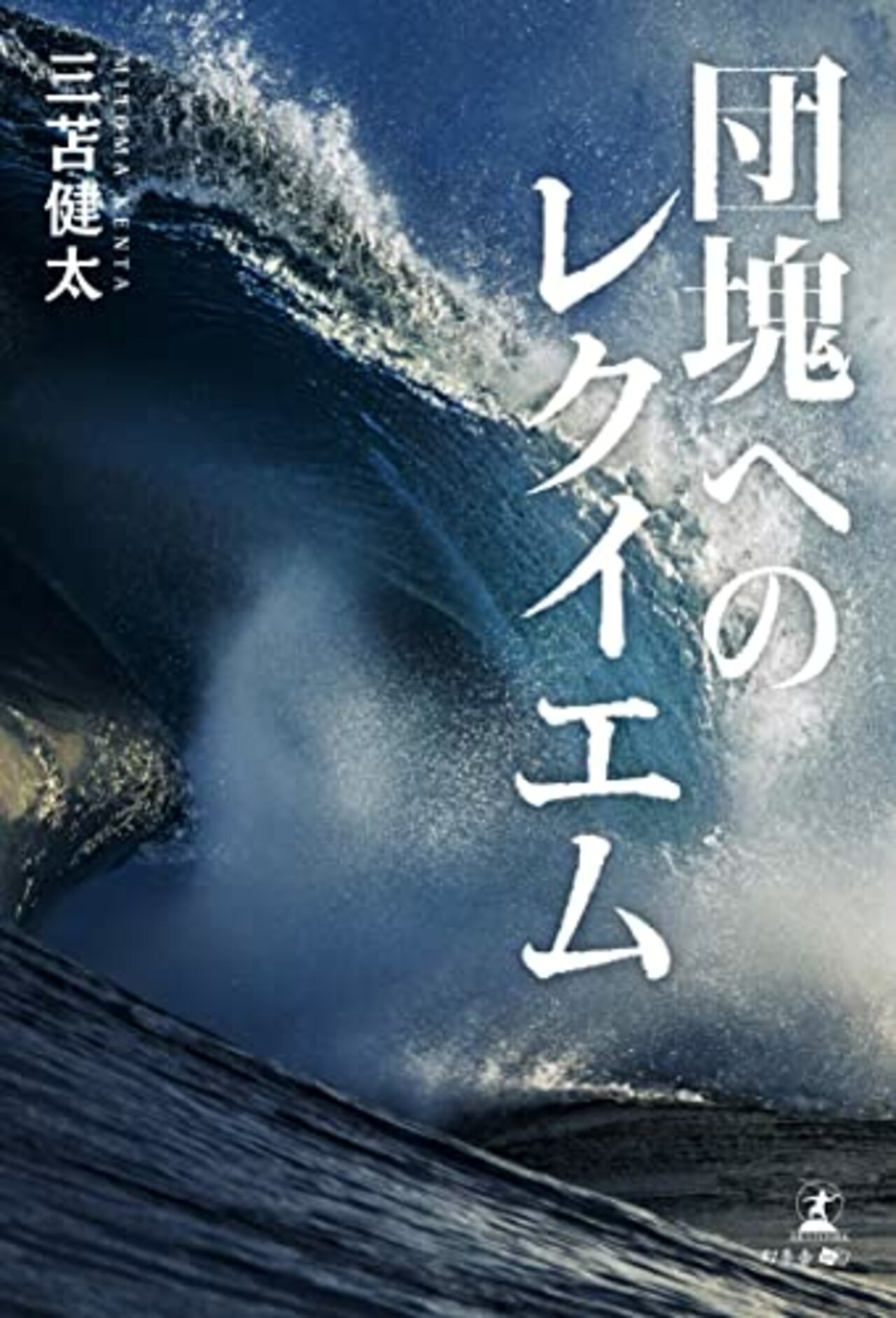3
ランニングマシンはクールダウンのフェーズに入り、徐々に速度を落としている。左沢はフェイスタオルで首筋の汗を拭きながら歩調に合わせて息を整えていった。窓の外には、正面の駅ビルの屋上から顔を出したばかりの十六夜の月が赤みを帯びて輝いている。
左沢はマットに移動し全身のストレッチを始めた。ガラス越しに見えるスタジオではエアロビクスのレッスンが始まった。ヘッドセットを装着して鏡を背にして立つ弥生が見えた。左沢が片足を手すりにかけて腰を落とし再び伸び上がったとき、弥生と目が合った。左沢に気づいた弥生は悪戯っぽく片目をつぶって見せた。
(今夜はとことん付き合うわよ)
そんな弥生の声が聞こえてきそうだった。左沢は慌てて手すりから足を外し、どっかりとマットに尻もちをついた。
(勘違いしてやがる)
左沢は舌打ちをした。
《仕事が終わってから付き合ってほしい。二十一時に駅前の駐車場で待つ》。夕方、左沢はメールを弥生のスマホに送信した。
《左沢さんとデートだなんて夢みたい。ご指定の時刻に待っています》。弥生はすぐに絵文字をふんだんに入れて返信してきた。
もちろん、弥生が期待するような甘い気持ちで誘っているのではない。今夜の目的のためには、女性の弥生の手助けが必要なのだ。
左沢は足を組み、目を瞑った。
昨日は九時過ぎに上野に着いたが、そのままマンションに帰る気になれず、新宿のなじみのバーでバーボンを飲みながら福島での一日のことを何度も反芻した。
周平は滝山みどりとともに、福島駅前でレンタカーを借り、いったん大葉町の実家に立ち寄り、心中の現場となった磐梯吾妻スカイラインのつばくろ谷に向かっている。ふたりがいったん実家に寄ったのはうなずけるが、わざわざ同じ道を引き返して真逆の方角にあるつばくろ谷に行ったことに不自然さが残る。
アーチ橋ができてから自殺の名所にもなったつばくろ谷で、周平たちだけはそのアーチ橋ではなく旧橋の橋台から身を投げたのもひっかかる。案内してくれた老刑事のカンも同じように働いたようで、福島駅での別れ際、この事件を白紙に戻し、いちから捜査をやり直すと約束した。
その多門から今日の昼過ぎに電話が入った。
「今、婆さまに遺体さ見てもらったところですが、遺体さ見ながらしきりに首さ傾げるんですよ」
遺体を見た当初は、まだ若いのに可哀そうだと涙を流していたが、そのうち、しきりと首を傾げるようになったそうだ。不審に思って理由を尋ねると、髪がショートカットで小太りなところはあの日の娘さんと同じだが、全体から受ける印象が違うと言ったという。
「なにぶん高齢ですから記憶さ曖昧なことはわかりますが、私は婆さまのこの言葉さ重く受け止めています。左沢さんに約束したとおり、スカイラインさ中心に目撃者捜しをいちからやり直します」
電話の向こうで、多門は気張ってみせた。
「私も周平と親交のあった者にあたって、いろいろ調べてみます」
左沢は多門の意気ごみに気圧されながら電話を切った。
周平とは、仕事のパートナーとして三年の付き合いがあるものの、彼について何も知らない自分を今さらながら呪う左沢だったが、心当たりとして三人の男女が浮かんだ。左沢が講師を務めた講習会に周平と一緒に参加していた前原宏作、左沢と取引関係にあるソフトハウス「ミクモ」代表の三雲正、そして内川が経営するコンビニの古参の女性店員だ。この三人から何か聞きだせるかもしれない。