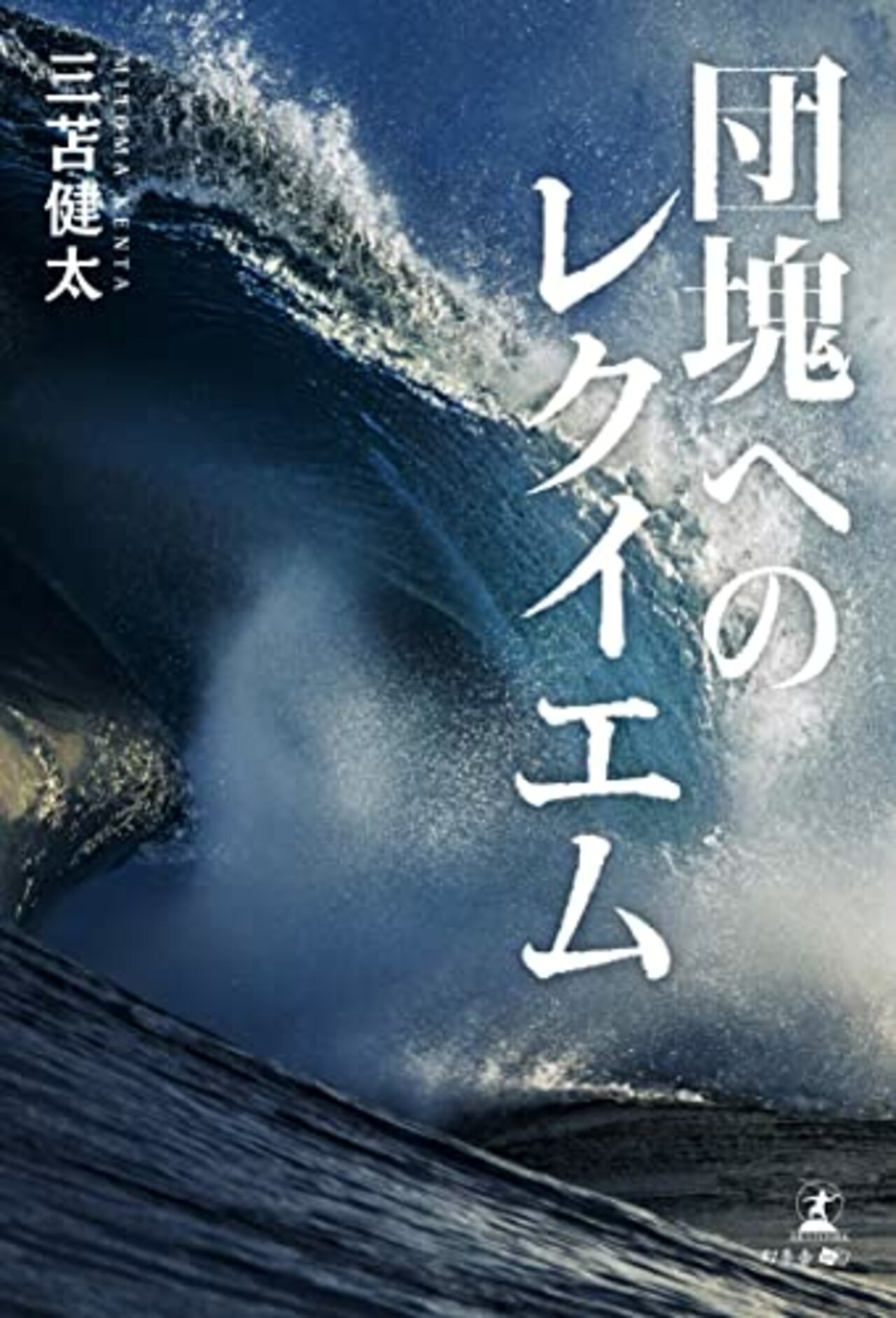2
多門は満足そうにうなずいた。本署を出るとき、周平の家のことに詳しい者を捜しておくよう、電話で駐在所に依頼していたのだった。
「周平のばかたれが、ずんがりどこさ行ってしもて、かぁちゃんさ悲しませてしもて、ほんでよ自分も死んでもただがや」
老婆は、突然家出して母親を悲しませて自分も死んでしまった周平は、大馬鹿者だと嘆いた。
「ここではなんだから、車の中で聞かせてくりや」、と多門は言い、巡査に目配せした。巡査は小さくうなずいて、老婆の両肩を抱きながら、車の後部座席に押し込むようにして座らせた。
左沢は身の置きどころに迷った。車の中とはいえ、刑事による事情聴取である。一般人が同席するのは問題があろう。
「申し訳ねぇですが、左沢さんは少しばっか席を外してもらえねぇですか」
多門は戸惑う左沢に、周平の墓参りでもして時間をつぶしてほしいと、老婆から場所を聞き出して、そのまま左沢に伝えた。
老婆が言うとおり、車から四百メートルほど西に歩くと、右手の小高い丘の頂上あたりに墓地が見えた。左沢は畦道をのぼり、丘の上に立った。同じような形をした十数基の墓石が東の方角に向かって並んでいたが、周平の家の墓はすぐに見つかった。新しい卒塔婆が立てられているのは周平の家の墓だけだったから、それが目印になった。
(周平、おまえはほんとうに死んだのか)
左沢は無言で呼びかけた。アラスカに発つ前日、シティホテルのカフェラウンジで、左沢が話す「ケアタイマ」の仕様に目を輝かせながら聞き入っていた周平が、ひと月も経たないうちに草木深い田舎の墓地に眠っている。
「周平、おまえは絶対に心中なんかしていないよな」
今度は声に出して呼びかけた。左沢に抹香臭い無常観などはない。周平は決して自らの意思で死を選んだのではない。この謎を解いて、周平の無念を晴らしてやる。今心にあるのは、周平の夢を絶った者への憎悪だけだ。