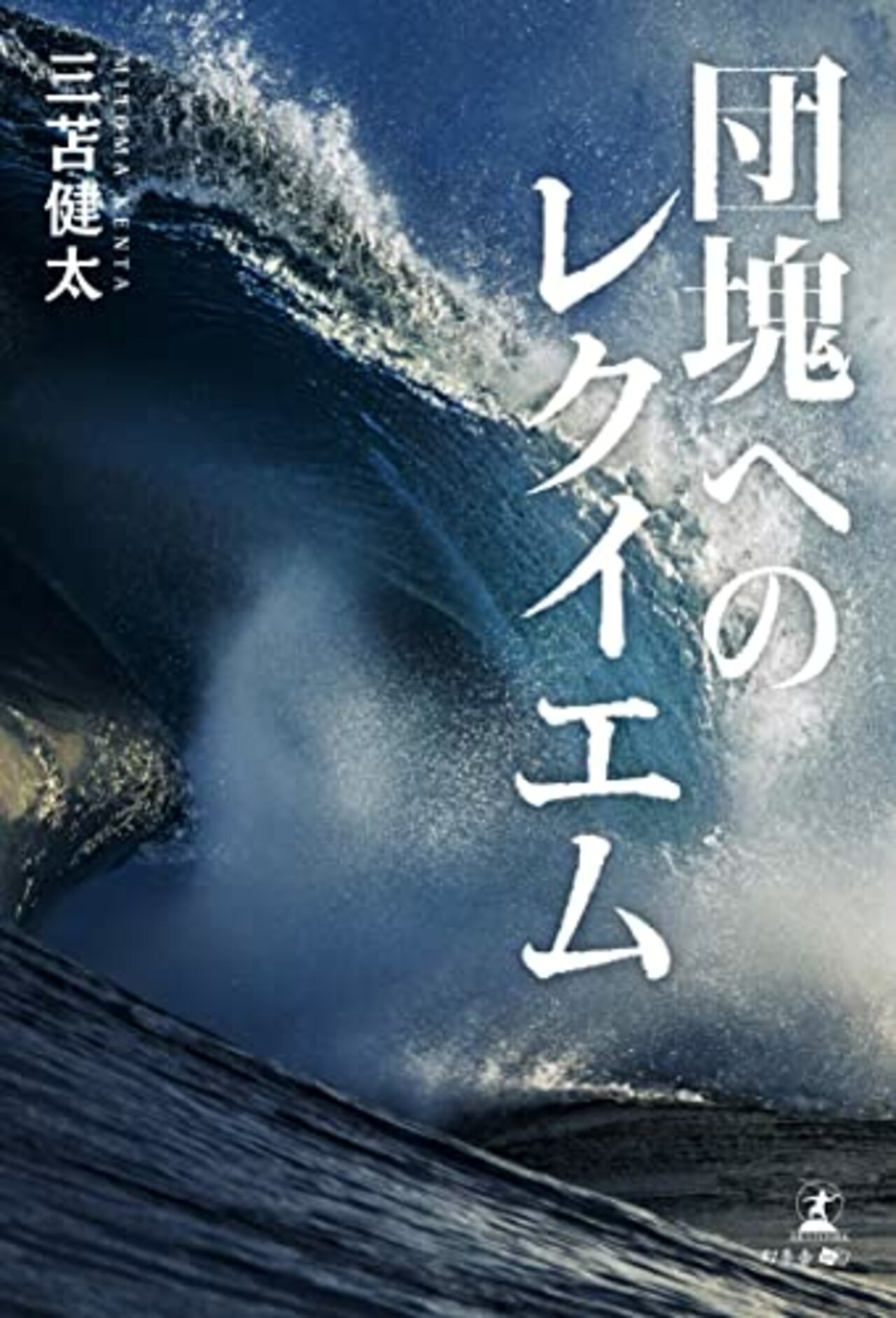1
ランニングマシンで一時間走り、プールで八百メートルを泳ぎ、サウナで残った汗を絞り出すと、頭のなかに居座っていた鉄球がクリームのように溶解し、体中が心地いい倦怠感に包まれた。
左沢陽介はスポーツジムをチェックアウトし、階数数字をぼんやり眺めながらエレベーターの到着を待っていた。
「アテラザワさん、おひさしぶりです」
声のほうに振り向くと、ジム専属トレーナーの寺島弥生がほほ笑んでいた。
「今度はヨーロッパですか、それとも前回と同じアフリカ?」
エクササイズを終えたばかりのようで、フェイスタオルで首筋の汗をしきりに拭いている。ポニーテールに結んだ髪が緩んで、浮世絵に描かれた湯上りの女のようだと思った。
「アラスカだ」
左沢は思いとは裏腹にぶっきらぼうに答えた。
「足の向くまま気の向くまま南に北に、か。羨ましいな。アラスカはどちらですか、バンクーバー、それともアンカレッジ、それとも……」
「バローだ。バンクーバーはカナダだ。バカヤロー」
左沢は苦笑した。弥生がトレーナーになりたての頃、彼女をパーソナルトレーナーにしたのがきっかけで、ふたりは軽口をたたき合える仲になっている。
「バカヤローじゃなくてバローか、確か北米最北の町ですよね、白夜とオーロラの町、いいなぁ。好きなんだ、私、白銀の世界」
弥生は遠くを見るような目をした。
「何がいいなぁ、だ。仕事で行ったんだぞ」
「じゃあ飛行機もホテルも出版社もちですね。やっぱり、いいなぁ。まっ、私たちみたいな肉体労働者はアテラザワさんのエッセイを読んでアラスカに行った気分になるよりしょうがないか。でも、いつか連れてってほしいな、アラスカ」
「ああ、いつかな」
「いつか、か。当てにならないからな、アテラザワさんのいつかは」
弥生は肩をすくめた。
「ふん」左沢は鼻を鳴らし、目を階数数字に戻した。
「それじゃお疲れさま」
エレベーターの到着を知らせるチャイムを合図に、弥生はぺこりと頭を下げて、スタッフルームに歩いていった。