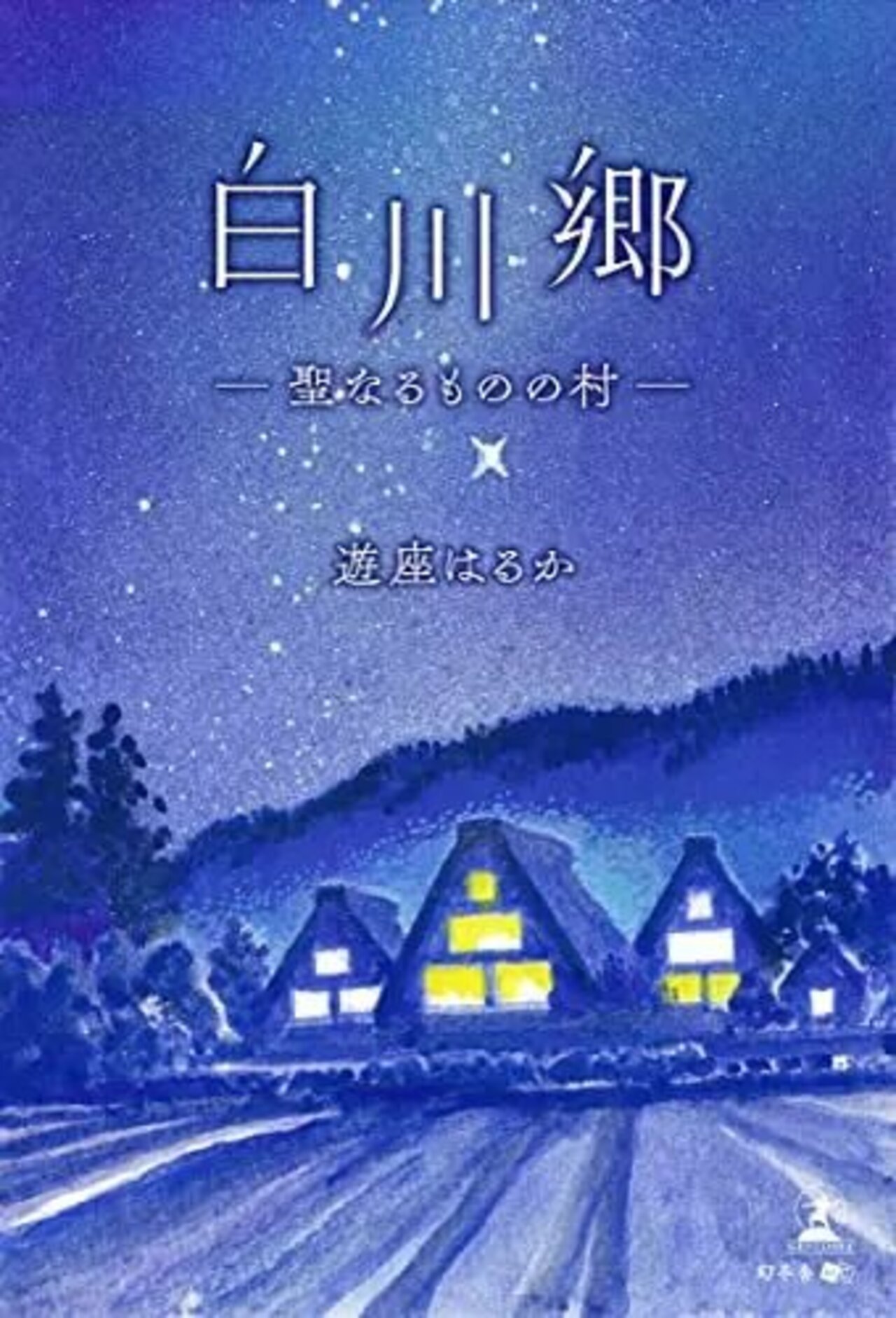伊島は、
「おっと、ここだ」
立ち上がり、篠原に軽く会釈して降りていってしまった。篠原はあわてた。つい、終点まで一緒に行くと思い込んでいたのだ。終点の高山駅に着いたら、その時には新聞記者だと名乗ろうと思っていたし、その上で伊島が了解してくれたら、さらにいろいろ聞きたいと思っていた。このままではただ聞いただけで、何の裏付けも取れていなかった。
篠原は、せっかくのスクープが、自分がうっかりしている間に煙のように消えてしまったと思った。何とも残念だった。かろうじて残った手がかりは、伊島が今も白川郷に暮らしているということだった。それならば、また会って話を聞くことが出来るということだ。
白川郷は人口約二千人で、村人同士はすべて顔見知りだから、戻って調べればすぐに会えるに違いなかった。今回は、二週間後の八月上旬にはまた戻れる予定だった。戦後六十余年、ずっと白川郷に隠れ続けていた陸軍中野学校出身の元戦犯。戦争の記憶が薄れてしまった今こそ、新聞記者として書かなければならない、と篠原は思った。
元々、篠原は、自分が地方支局の一記者で埋もれてしまうとは思ってもいなかった。でも、左遷されてしまったからには、せめて注目される記事を書きたいと思っていた。しかし、山奥の暮らしは何一つ事件も起こらず、穏やかな日々が続くばかりで、着任してから自分は何を書いたらいいのか、悩んでもいた。
そんな時に、支局長の緑川の話から白川郷に興味を掻き立てられ、それで今回の長期取材を申し出たのだった。篠原の取材テーマは『世界遺産白川郷の経済基盤は何だったのか』というものだったが、それが取材に当たっているうちに、暗礁に乗り上げた感じだったので、この戦犯の話は渡りに船だった。
いや、こちらの話の方が、最初の企画よりもずっとインパクトがあった。篠原は山奥の飛騨支局転勤を残念に思っていたが、実はこの話を書くためであったのか、と気負い立った。一時も早く、支局長の緑川にこの話をしてみたいと思った。ただ、緑川は明日から二週間、北アルプスの山小屋の取材で山に入ると言っていたので、今日会えないと、話は二週間先になってしまうのだった。
何としても、今日中に話さなければならなかった。