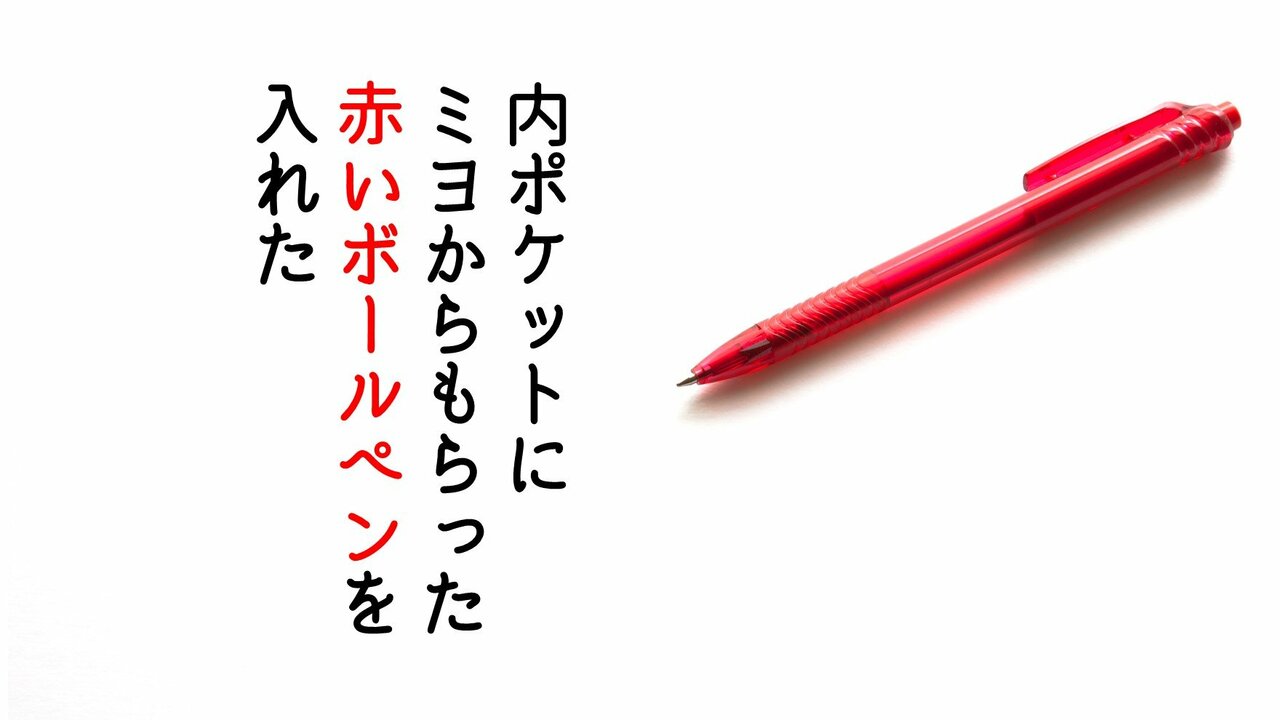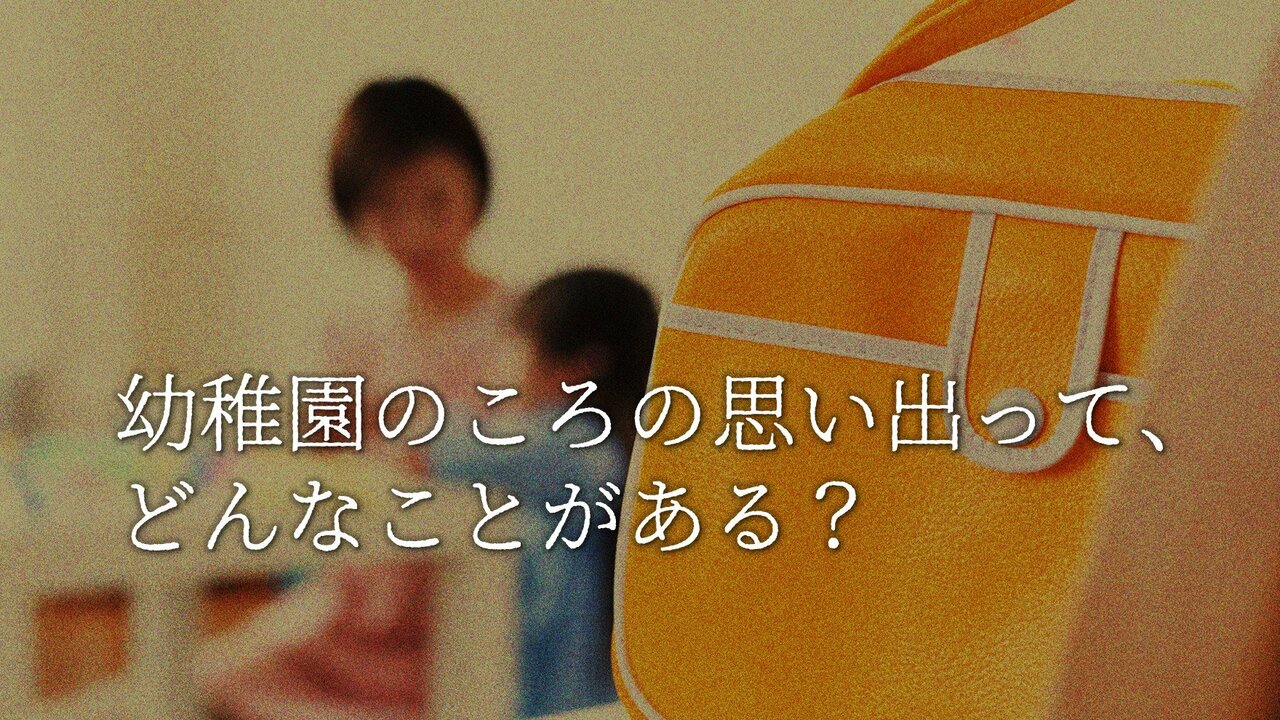第三章 運命の人
その時、携帯からメロディが鳴った。
「ミヨ先輩からだ」
椅子から立ちあがり、少し伸びをすると、達也は部屋のテーブルに置いてある携帯を手に取った。
メロディはミヨと同じ『ブリリアント・スノー』だ。文化祭のあと、達也もこの曲をダウンロードし、ミヨからの通信があった時だけに鳴るように設定していた。このバラード曲が携帯から流れるたびに達也の心は躍る。
『達也くん、こんばんは。勉強、とても順調そうね。だけど、英語に苦戦しているのね。今度の日曜日、図書館でいっしょに勉強するというのはどうかしら? 私でよければ英語みてあげるわよ』
達也はミヨの提案に甘えることにした。第一志望が確定した夜のことだった。
約束の日曜日。達也は町の図書館に向かっていた。穂高第二中学校から自転車で約十分。青空に帆を張る白い船のような外観が見えてきた。その入り口付近で空をずっと見上げ、少女が一人立っている。
「ミヨ先輩」
達也の声に気づくとミヨはゆっくりとこちらに顔を向けてきた。黒のトレンチコートに黒い光沢を放つブーツ。どうやら今日は私服のようだ。
「すみません、遅くなってしまって」
首を横に振るミヨは、白いマスクを着けている。
「体調悪かったですか? 今日」
達也は申し訳なさそうに言った。
「ちょっと咳(せき)がでるだけよ」
ミヨはくるりと後ろを向くと館内に入っていった。ミヨのあとについて入ると、老若男女様々な人が静かに読書を楽しんでいる。二人は自習スペースのある奥へと進んだ。
A、B、Cと三つのブロックに分かれており、それぞれ四人がけの机が一つずつ並んでいる。受付で使用許可をもらい二人はCブロックの席に隣同士になるように腰かけた。
白樺(しらかば)造りの椅子や机からは木の温もりを感じる。コートをぬぎ、一度椅子に腰かけたミヨは何か思いだしたのか急に立ちあがった。
「バッグ見ていてくれる? お願いね」
黒いオフタートルのAラインニットワンピースに銀のネックレス。胸の辺りに下がった銀のクロスを持ち、ミヨは書架へ向かった。達也は持ってきた英語の問題集を開き、一問目に取りかかろうとした。そこを偶然、同じ中学校に通う男子生徒が通りかかった。鶴岡(つるおか)だ。
「あ? 斉藤か? どうしたんだ、こんなところで。珍しいこともあるものだな」