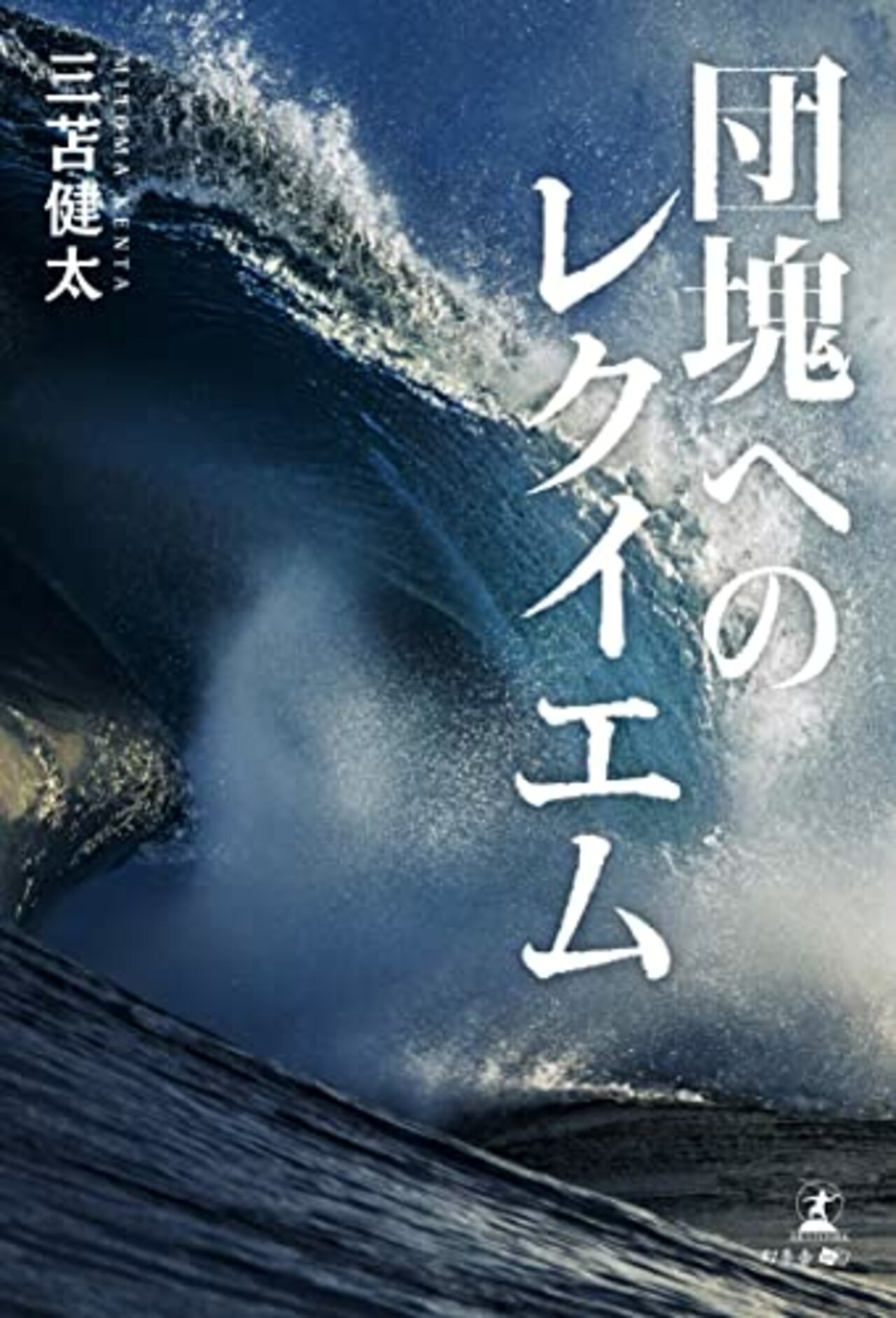「周平はそれ以来、この家に戻っていないのですか」
「母親が亡くなってふた月ほど経った頃、ひょっこり戻ったそうで、母親の死さ聞いてずいぶんと悲しんだそうです。そんで、それからはちょくちょく帰り、家や墓の草取りや掃除をするようになったということです。あの婆さま、死んだあとさ孝行してもなんもなんねぇと怒ってましたけどね」
年に数回は福島に帰っていたとは意外だった。左沢が出会って三年間、周平はおくびにも出さなかったことだ。
(周平の過去を知っていれば、もっと別の接し方や助言もできたはずだし、今度の事件にも遭わなくて済んだかもしれない)
左沢は、周平の私生活に無関心であった自分を今さらながら責めた。
「周平は、心中した当日、いや心中したとされる当日、ここに立ち寄った形跡はありませんか」
左沢は、自責の念にかられながらも、ふと思いついたことを尋ねた。今から死のうとする者が、その決行の前に少し足を延ばせば行ける自分の生家に立ち寄ってみたくなるのは自然のことだ。逆に、立ち寄った形跡がなければ心中への疑問はさらに深まる。
「左沢さんはやっぱし鋭いですね。仰るとおり、周平さんは当日ここさ立ち寄っています。婆さまが声をかけると手を振って応えたそうですから、間違いねぇです」
「じゃあ、相手の女性も」
左沢は、軽い失望を感じた。やはり、死を覚悟した周平は、見納めにわが家わが町に立ち寄ったのだろうか。
「ええ、ちょうど私たちが今いるこのあたりさ、お相手の滝山みどりさんと一緒に立っていたそうです。婆さまは、あのパトカーの止まっているあたりからふたりさ見ています」
左沢はパトカーと自分の距離を目測した。三十メートルはありそうだ。続いて左沢の目は老婆の歩いていった方向を追った。老婆は県道から自宅に延びた取り付け路を、手押し車を押し全身を左右に揺さぶりながらのぼるところだった。バイクに跨った巡査が県道から何やら声をかけると、老婆は振り向いて、体全体で大きくうなずいた。
「明日の朝十時さ迎えに行くと念を押しているんですよ」
振り向くと、多門の目も老婆を追っていた。
「婆さまに滝山みどりさんの遺体さ見てもらうことにしました。だども、あまり期待さしていません。なにぶん、あの日、滝山みどりさんはマスクさしていたそうですし、この距離で婆さまの視力ですから、遺体とあの日の女性が同一人物かどうか判断できんでしょう」
多門は腕組みをして視線を遠くに投げた。その先にイチエフの真っ白な排気塔が光っていた。