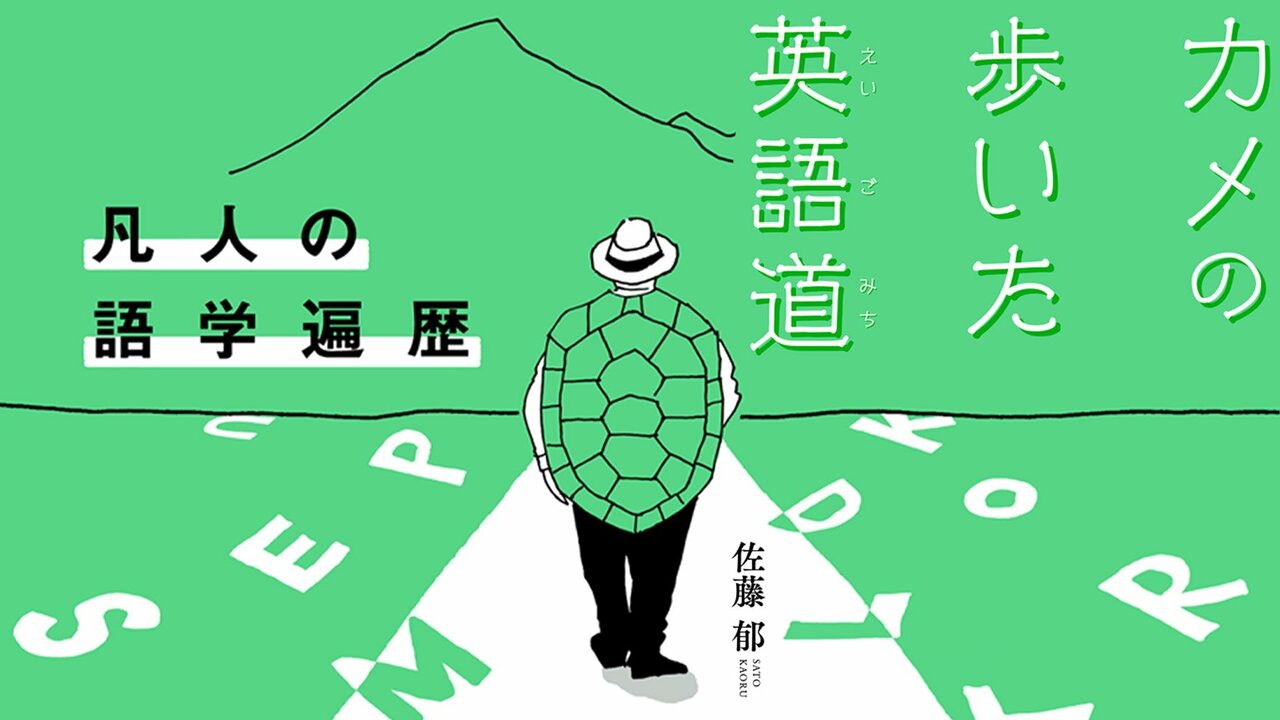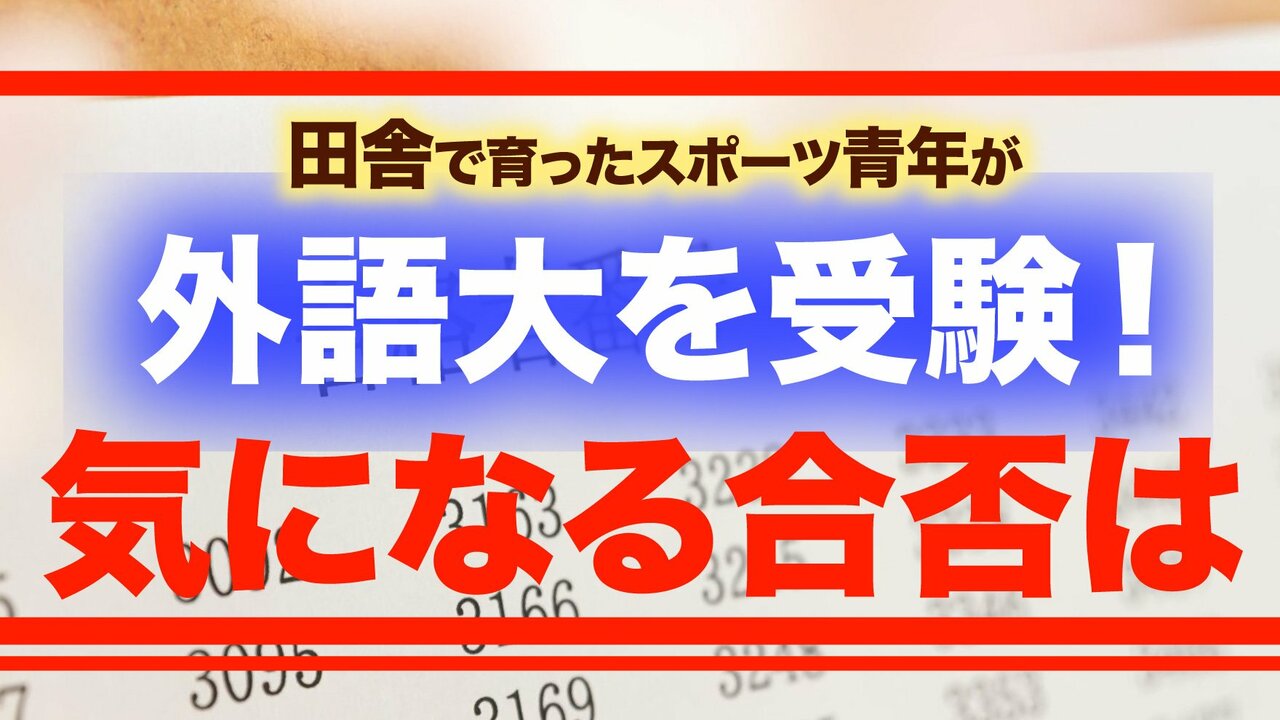【前回の記事を読む】「早くこんな田舎から東京へ」大学へと夢想を膨らませるが…
中学・高校時代
大学へ進学する希望もあったが、家の経済事情を考えると、私は親に相談しづらく、担任の先生にも何も伝えていなかった。黙って小遣いを貯めて、高校3年の大学入試時期が来たとき国立大学2期校の受験料400円を添えて、東京外国語大学(当時は2期校)へ入学願書を送った。そのフランス語学科を志望して。
当時の田舎では大学受験に関するまともな情報はほとんどなく、外語大が東大受験者の流れで競争率が高く、主要学科はどれも約30倍だということぐらいしか知らなかった。
町の本屋に受験雑誌はあったようだが、購読するほどの熱意も資金もなかった。競争率が30倍ということがどれほどのものかという「危機感」のような怖さは全くなかったし、陸上競技部のキャプテンとして練習に頑張っていたのであるから、呑気なものである。
担任の先生に内申書を頼んだとき「外語大は難しいぞ」と言われ、先生の知人が教師をしている某私立大学の体育学部なら推薦入学も可能だと勧められたが、私はもう陸上競技はやりたくないと固く思っていたし、家庭の経済的事情からも私立大学は無理だと思ったので、先生の勧めを丁重に断ってしまった。
陸上部の練習で疲れて帰宅しても、一応英語だけは参考書で毎日少しずつ英文読解の自主トレをしていた(実際は眠っていることが多かったが)。英語に執着したのには一つの動機があった。
高校1年の時である。当時村の中学は男女別学であったが、県立高校普通科に入学したら男女共学、アイウエオ順で席が決められていた。ある時英語の時間に教師の説明をニコニコしながら聞いていたところ、「何をニヤニヤしているか!」と私に向かって教師の叱責が飛んだ。
小学校5年時から男女別学だったので、男女共学に慣れていない私は隣の女子の手前、赤面した。そして腹の中で(よしこのオレが不真面目な奴だと思うなら、そのうち期末試験で良い点を取って見返してやる)と自分に誓った。
田舎の村出身の新入生でも英語では町の連中に負けないぞという、劣等感の裏返しの心理が英語へのモチベーションになったのかもしれない。村の中学ではまともに英語は勉強しなかった。
その頃英語は中学の必修科目ではなく、職業家庭との選択科目であり、われわれ男子の多くは「職業」科目を選び、校庭に隣接していた畑でサツマイモなどの栽培をしたりしていた。高校へ進学すると決めていた生徒は英語を選択していたのだが、私は前述のように、進学をしたいが親には相談していなかったので、英語は3年次の3学期になってから進学のための補修授業に参加して猛烈に(自分ではそのつもり?)「追っかけ」勉強したのである。
高校では、大学進学希望のクラスに属して、英語は必修科目のほかに英作文コースも受講したが、今考えると田舎の県立高校のクラス全体のレベルは相当に低かったようである。
私は文学的な本をよく読んでいたので国語(現代文)は得意科目で、英語もクラスで上位になったようだが、このあとで記述するように外語大の受験で、私の英語レベルの低さを認識させられ、徹底的に打ちのめされたのである。