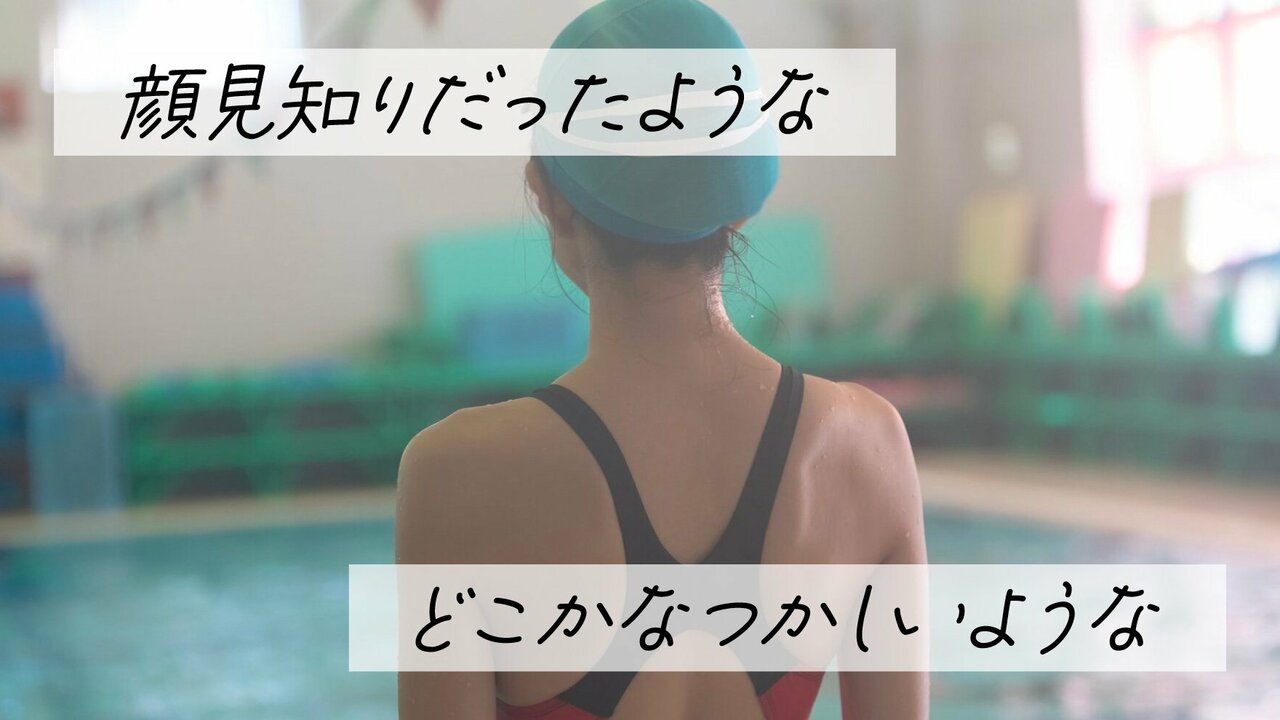ホテルの玄関前のロータリーを通って表通りに出た。小路に入り、緩やかな坂を上がりきった小学校のそばにあるコンビニに寄る。
「いいんですか? あなたのような方だったら、この近辺のおしゃれなランチのお店とか、そういう情報に詳しいのではないのですか?」
万里絵が先に定番のサンドイッチとドリンクヨーグルトを買う。
「米派でしてね」
釣木沢は緑茶のペットボトルとおにぎりを三個のレジを済ませた。ホテルへ引き返す道も自然に肩を並べて歩いた。
「わたしは全然グルメじゃないし、お料理も上手じゃない。今、住んでいるのは食事つきのマンションです」
「パンションですね」
「なに、それ?」
「そういうところ、パンションって言いませんか?」
「初めて聞きました」
「そうでしたか、失礼しました。岩手県人はみな、知っているものとばかり」
仕事柄なのだろう、釣木沢の口調には誠実さと生真面目さが感じられたが、とにかく固い。
「わたしは時事情勢にも流行にも疎くて、これといった趣味もなくて、食べて眠る以外は仕事だけの人間です」
万里絵はつぶやきながら、自嘲的な自己紹介だと思った。
これから水泳を教えられる釣木沢と話しながら、スキーを教えてあげますと言った三智治の額に、緊張のためにつたっていた汗の記憶が呼び覚まされた。過去のことだ。あんなに早く別れることになるのだったら、ちゃんと習っておけばよかったと今ならば思える。
「書く人から産み出されるものの声を聞くために生きている。ある意味、世捨て人みたいなものです」
万里絵は小声で付け足した。
プールサイドで軽く準備体操をした後、練習が始まった。膝上丈のシンプルな黒色のスイムパンツを着けた釣木沢を見た時、美しい人なのだと万里絵は改めて思った。大胸筋から腹直筋、鍛え上げられた筋肉の張りが体の隅々まで満ち溢れて盛り上がっていた。
経歴や身長はもちろん、武術や拳銃射撃にも長け、英会話も堪能な文武両道の条件をクリアした者だけが警備部警護課に配置される、生粋の選ばれた人なのだ。手本として見せられた釣木沢のフォームは、水生動物のようになめらかに水になじみ、万里絵には手の届かない人なのだと念を押されたような、圧倒的な美しさだった。