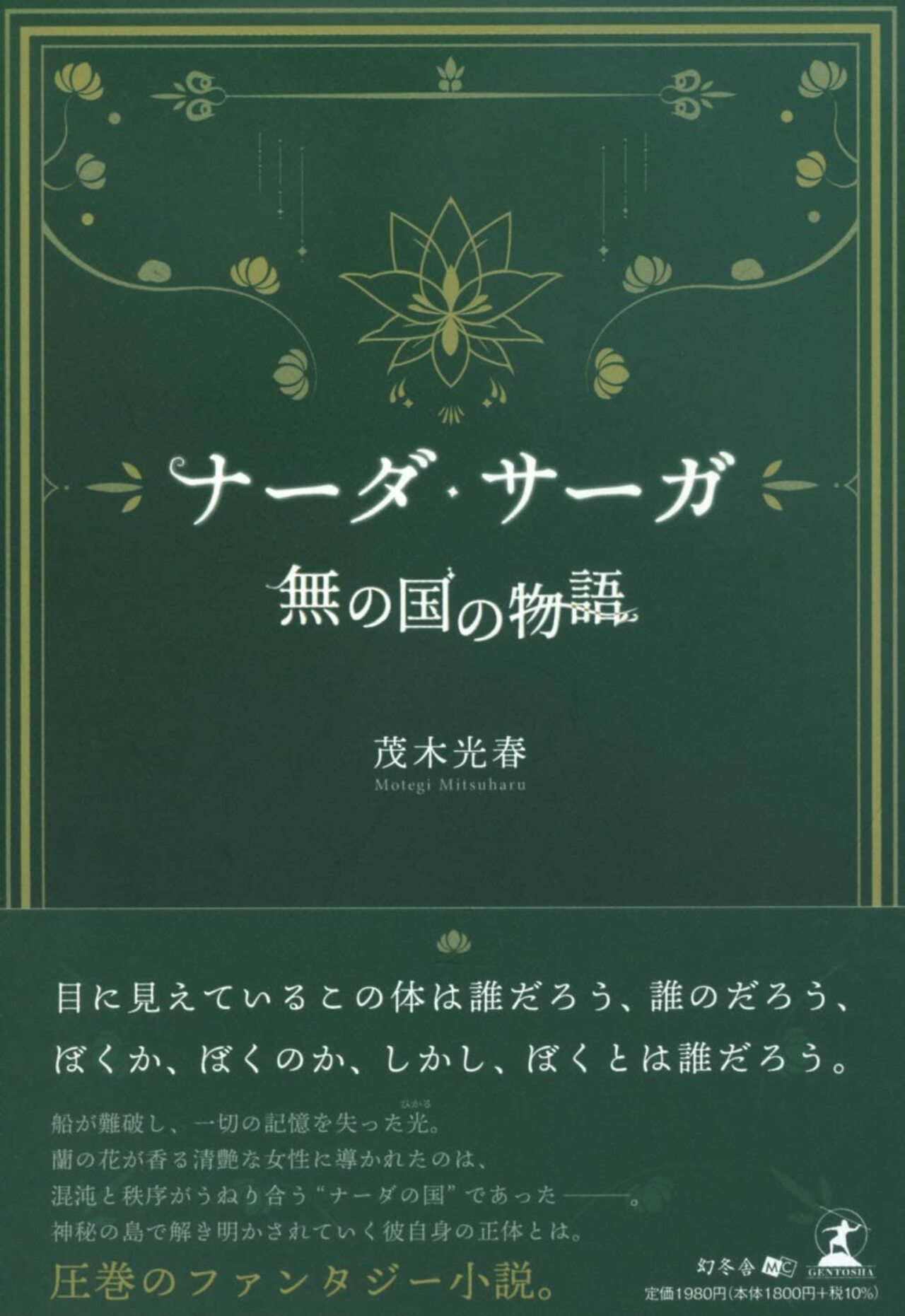「さぞかし驚かれたことでしょうね」
少女はようやくぼくの方を振り返り、美しい微笑を浮かべながら言った。
「ここは一週間に一度開かれるナーダ・グッズを売り買いする広場、バザー・ナーダです。この国の日用品または必需品が、すべてとは言いませんが、主なものを網羅してありまして、大変な賑わいを呈している所でもあり一日でもあるのです。それに今日はNondayと言って無曜日です。その日に限ってこのバザー・ナーダが開かれるんです。
その国を知りたいならその国の食べ物を食べよと言いますから、まずこのバザーの中を歩いて、何でも結構ですから試食してみてください。もちろん他の品物もございます。さあ、どうぞ、自由にバザーを楽しんでください。私から離れても迷子になることはありません。私はいつでもあなたを見つけることができ、すぐにでも参りますから。それにこの世は迷路です。そして迷子になることほど楽しいことはありません。もっと言えば、この世は無路、そして無子になることほど楽しいことはありません。そうではございませんか」
少女はそう言って、すうっと消えた。どこかへ歩み去ったというよりもむしろ、あくまですうっと消えたのである。
少女の言うことなすこと、不思議さの連続であり、驚きの連続だった。しかしそれは少女自体のというより、この国の不思議さであり、その反映にすぎないのかもしれなかった。ぼくは一人残され、途方に暮れつつも、目の前の光景にはや心を奪われて行った。
途方もない人たち、売り買いする人々の群れで一杯であり、その声が会場にこだまし、反響して、足下が揺れ動くかとも思われたほどであった。人々はほとんどが白いサーリーを身に纏い、子供はもちろん女の人も老人も同じ服装だった。
ぼくは階段を下りて行った。いろんな店が出ていた。それらは朝市のごとく、ノミの市のごとく、フリーマーケットのごとく、骨董市のごとくであり、古いもの、新しいもの、それはもう何でもあって、食べ物、道具、衣服、玩具、書画骨董、その他衣食住に関するあらゆるものがあった。
それに、店が並んでいるだけではなく、手品師などの大道芸人もいれば、居合抜きなどの武芸者、似顔絵師、ヨガ師、断食芸人もおり、ゲームコーナーもあれば、囲碁将棋チェスなどの勝ち抜きコーナーなど、その他数限りもない見世物小屋が延々と続いているごとくであった。