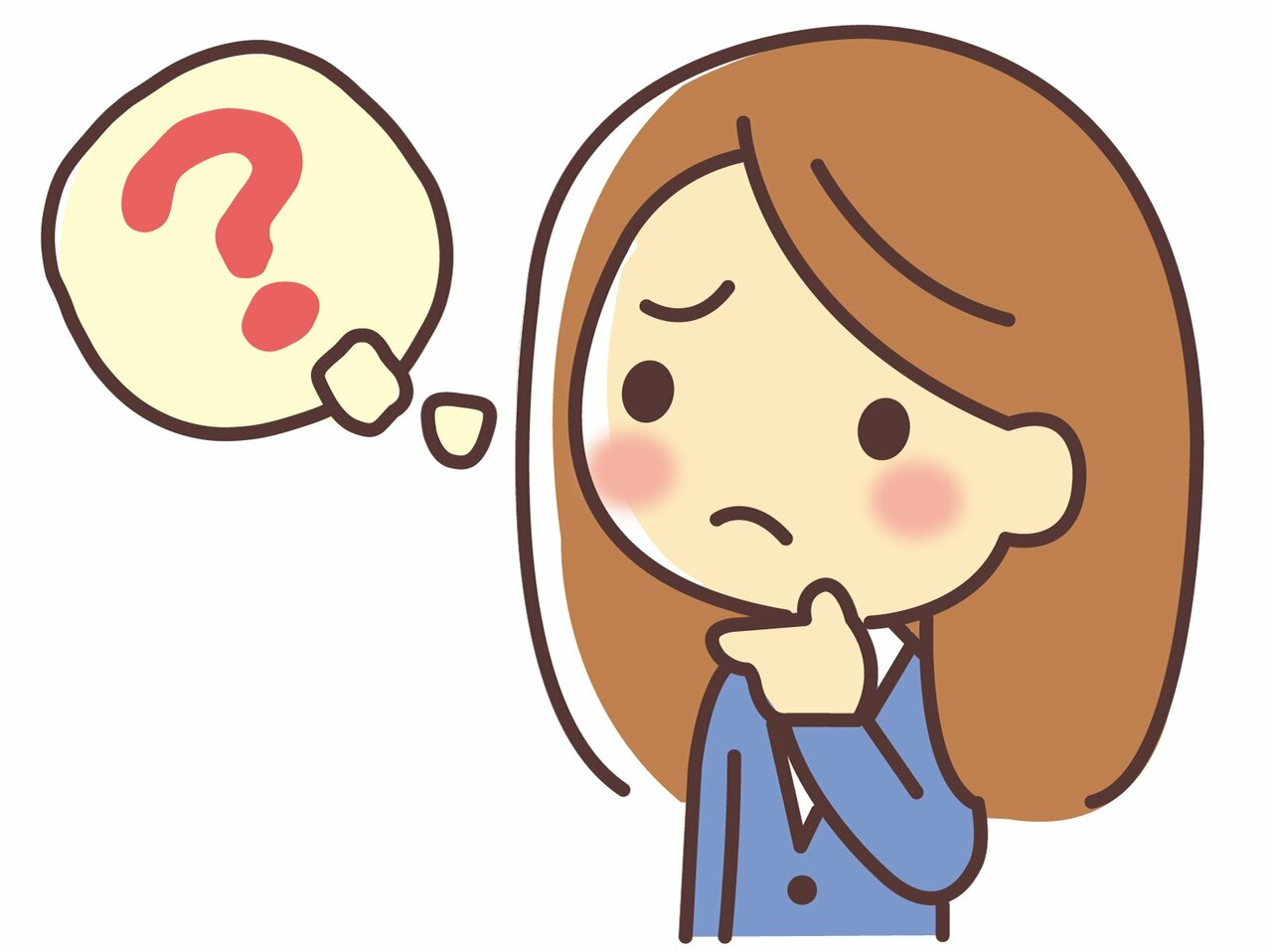第一楽章 あなたの瞳が教えてくれた記憶
Ⅰ 汽笛がつないだ出会い
そんな状況が続いたある日のことです。列車を待っている駅で、彼女はひとりの男の子に出会いました。4~5歳の年の頃でしょうか。ちょっとワケありな雰囲気の男の子のように感じました。この子、きっとお腹を空かしていそうな気がするわ、と彼女が内心思っていたところ、
「おねえさん、また今日もここへ来ているの?」
「えっ? なぜキミが知っているの? そうだけど……」
「ボクはたまに列車を見に来ているんだ。どんな人が乗っているのかなって」
「そうだったのね。私はね、ある人と約束をしていて、帰ってくるのを待っているの。でも、まだ戻ってこない。
でも、その人はきっと帰ってくるって信じているから、私は迎えに来ているの」
「そういうことだったんだ。その人は男の人? だったら帰ってくるといいね」
「ありがとう。キミはやさしいのね。声をかけてくれてうれしかったわ。なんか急にお腹空いてきちゃった。よかったら、一緒にご飯でも食べてから帰らない? おねえさんがご馳走するわよ」
「本当にいいの? おねえさん、ありがとう」
その男の子は目をきらきらさせて返事をしていました。
こうして、彼女とその男の子は、それからもその場所で出会っては、一緒に食事をするようになり、気づけば、男の子は青年へと成長していきました。
あるとき、青年になったその子が彼女に言いました。
「まだ迎えはつづけるの? もういい加減、あきらめた方がいいんじゃない?」
「心配してくれてありがとう。でも私はあきらめないわ。だって、必ず戻ってくる!って彼は言ったの。だから私は、待っているって約束したんだもの。破るわけにはいかないわ」
「わかった。ボクも一緒に信じるよ。その人が帰ってくることを!」
「本当? ありがとう。なんか元気をもらえた気分になったわ」