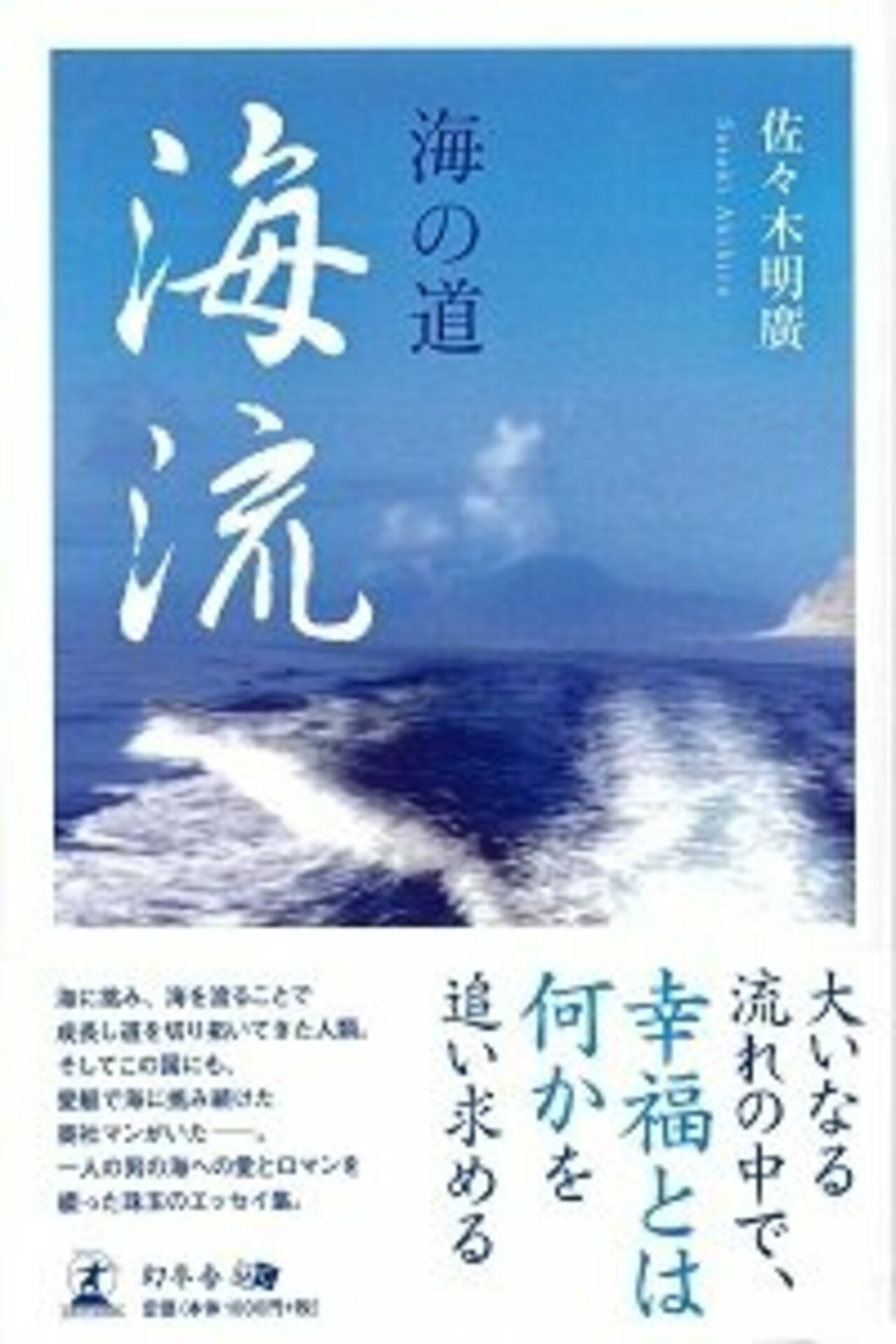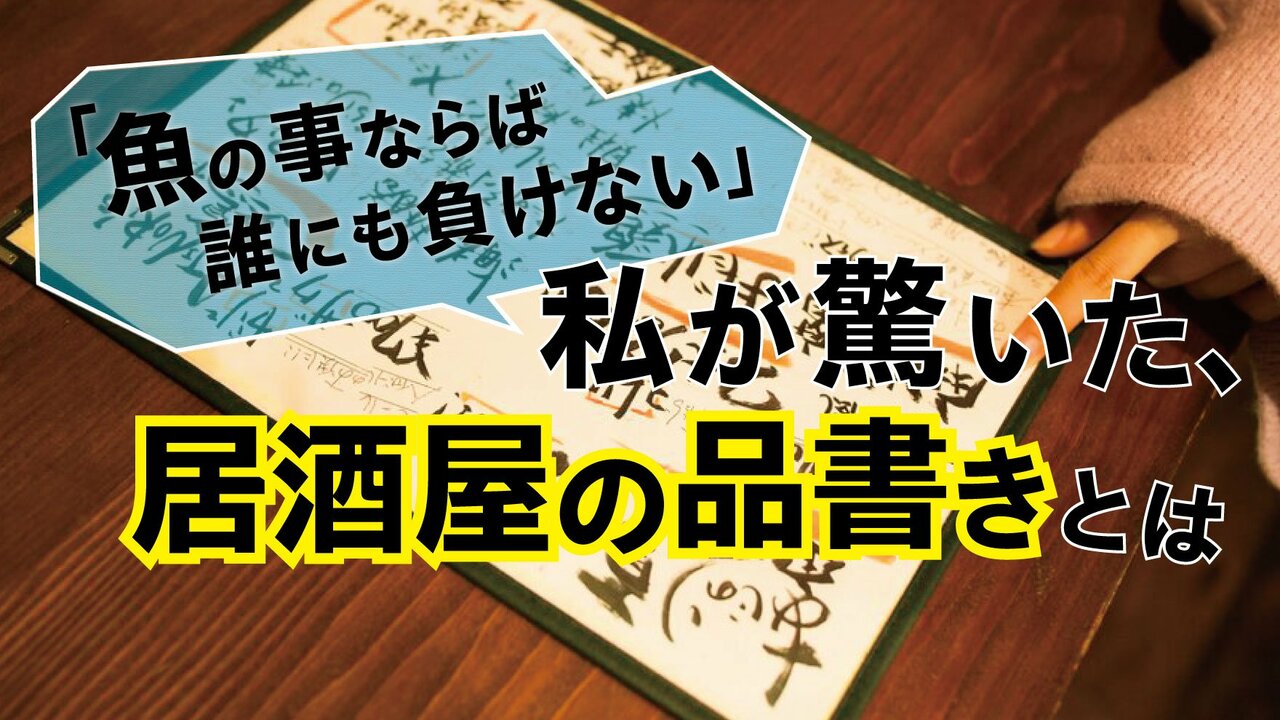すぐに行動を起こしたのは居酒屋探しであった。三軒茶屋は渋谷のベッドタウンとして栄え、すずらん通り、ラビリンス街など居酒屋が密集する街である。そのすずらん通りのアーケードには戦後の関西の糸へん・金へん時代の好景気にあやかって「喰うてかへんか」の文字が今でも掲げられている。
探し続けている内に会社に近いすずらん通りを下がった右に何やら貼り紙がベタベタ貼られ、お化け提灯がぶら下がった店を発見した。「味とめ」である。このような店が意外と行きつけの店となることがある。
中に入ろうとしたが仕入れた食材の発泡スチロールの箱が入り口に積み重なっていて入りにくい。またいで中に入るとよく喋るおばちゃんが居た。店の主のおばちゃんであった。店内の壁にびっしりと貼られた品書きを見ると東北、北陸、東海、四国から九州まで全国津々浦々の食材を使った料理が書かれている。
私は故郷北海道の魚が無いではないかと言うとおばちゃんはすかさず「言ってくれれば宗八(鰈)、ホッキ、ムール貝、何でも揃えるよ」と言う。一寸聞いただけで私の好みである北海道の魚介類の名がぞろぞろ出てくるおばちゃんに興味を持った。
これからは仕事の上で客やスタッフとのお付き合いも多くなる。お代はともかくこの店のお世話になろうと決め、その後毎晩のようにカウンターの止まり木に止まるようになった。
ただ一つ気になったことは、夕方になると常連客がムクドリのように集まって来て順番に好みの止まり木に止まってしまうことであった。私は店の全体が見渡せるカウンターの角に座りたかったがそこはどうやら司法書士の大岸さんが座る場所であったようでしばらくの間、彼との席取合戦が続いたが、やがて地の利がある私の定席とすることができた。
一方、常連客の顔ぶれが徐々にわかってきた。右奥に座るのが葬儀屋の川並さん、その横は最初の亭主がその筋の人、二人目も同じだったという女傑のサツちゃん、早い時間からすずらん通りを原色のサイケ風なドレスをひらひらさせて歩き、席が埋まり始めたら私の席を先に取ってくれる金魚の妖精モロちゃん、私が角を占めた時左に座るのが負けた司法書士の大岸さん、そしてその隣には木屋の包丁研ぎの名人熊ちゃん。
遅く来て止まり木に止まれず、近くのテーブルに可愛い娘が居ればわしは特攻隊の生き残りだとか何とか言って割って入り込もうとする爺さん。まあどこの居酒屋にでも居るような常連客ではあったが新参者の私は当初、何か難しそうな感じの人として煙たがられて居心地が悪かった。しかし、意外とそうでもないことがわかるとすぐに仲間として受け入れてくれるようになっていった。
更に知ったことは厨房に味付けと魚さばきの名人、工藤君が居たことと、店内を取り仕切る伊藤さんが居たことである。伊藤さんは私と同じ北海道出身で、本をよく読む物知りでよく話が合った。一方、工藤君は佐渡島出身であったが、その工藤君と気心が通じ合うようになったきっかけはモスクワからの帰国時、空から見た佐渡島の情景を語り聞かせてからである。