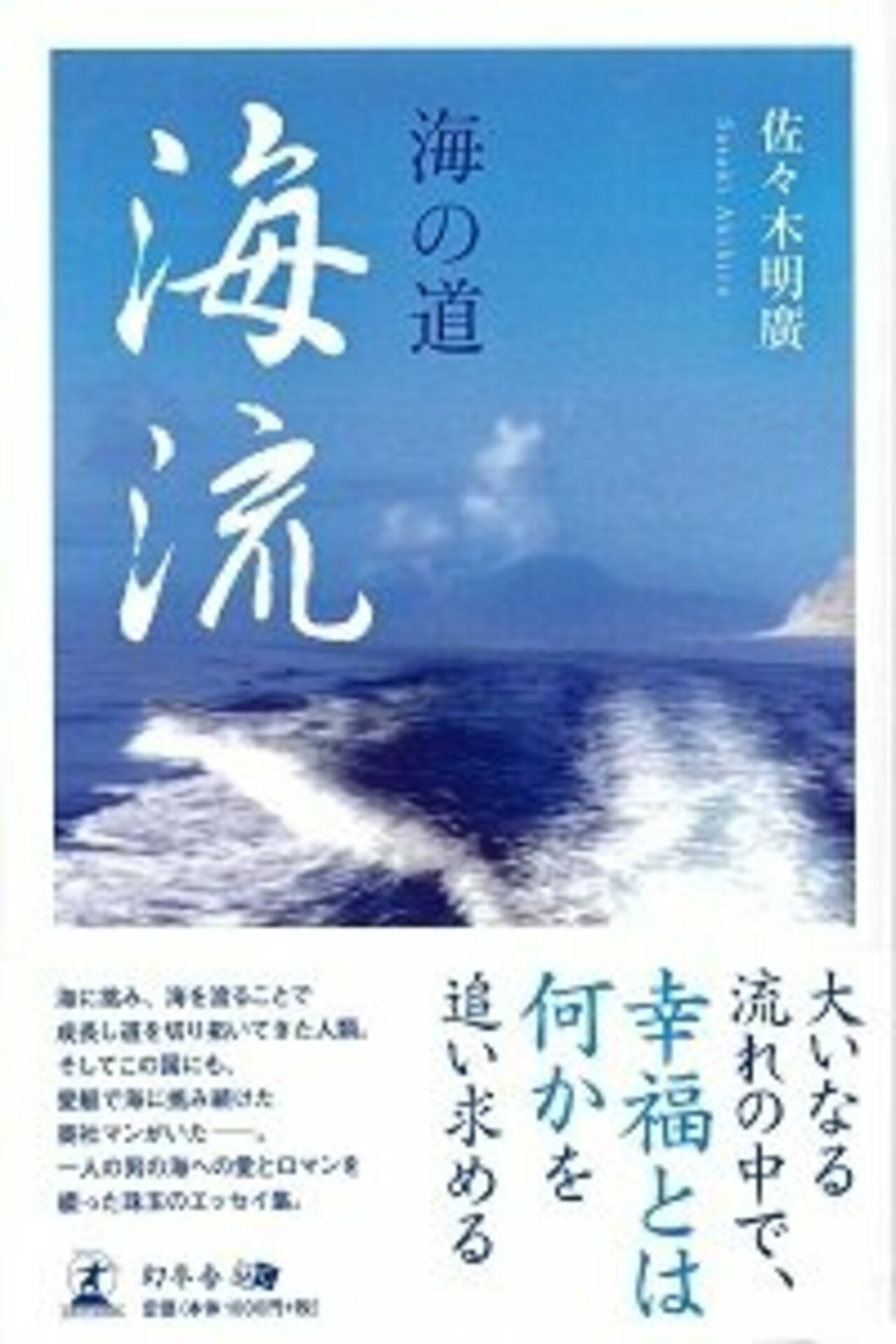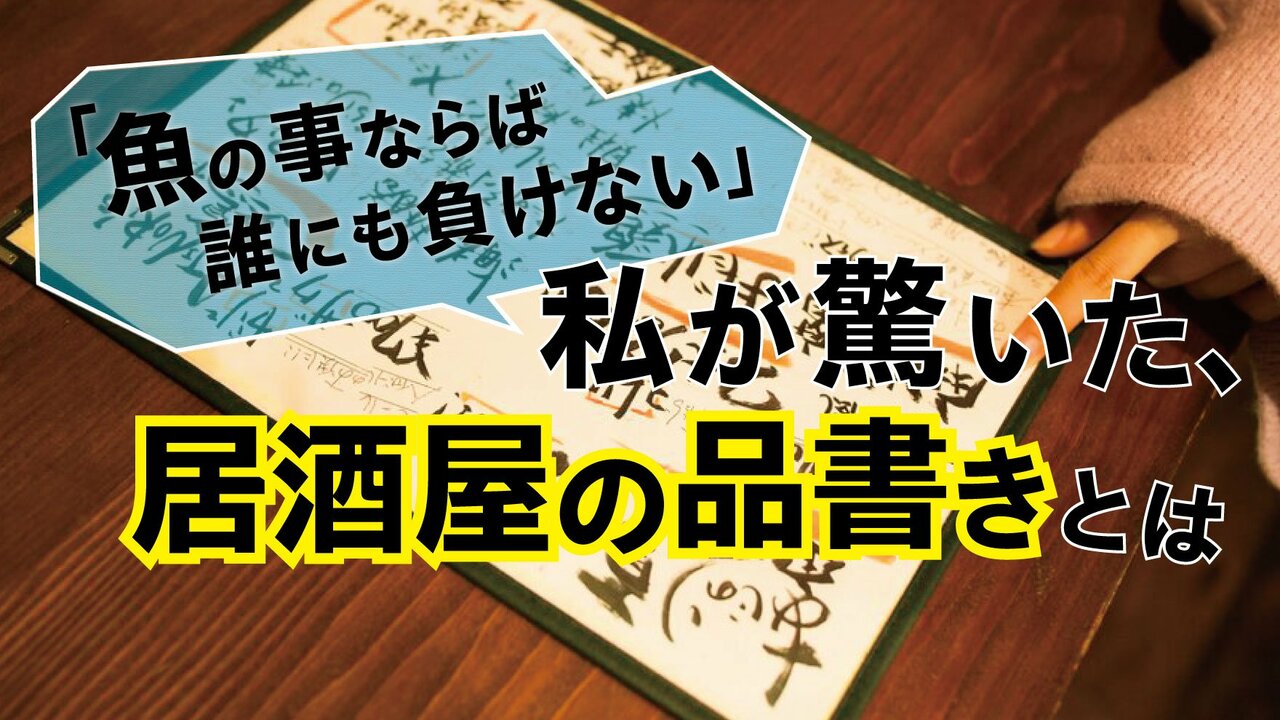【前回の記事を読む】縁遠いと思っていたが…大分で果たした「奇跡の出会いの連続」
第二章 西日本
三 大分
昭和十六年生まれの同輩は、高校・大学時代、更には大分の岡本や大河内のような入社同期を含めて大勢いるが一様に不思議な個性がある。元気で人間味があり、しかも打たれ強くて粘り強く、そしてしたたかなのだ。生まれ年は巳年であり、終戦後の育ち盛りの我々は食糧難で苦労をしたことからその様な人間が形成されたのでないかと思っている。
盃を交わしたあとは全てに打ち解けてお互いの出生と生い立ち、終戦後の苦しみ、互いの事業の現状と行く末、人生観、幸福とは何か等々、誰に憚ることも無く話は尽きなかった。同じ年頃の男兄弟が居ない現実と、話し合える同輩が少なくなってきた寂しさがお互いを引きつけたのかもしれない。
一方、私の終戦後の話は向洞爺村の疎開や電信浜での磯物獲りなど、幼少時代の故郷のノスタルジックな話で、どちらかというと抒情的な想い出話であるのに対し、兄貴の苦労話は壮絶なものであった。
父親は東京電灯(現在の東京電力)に勤めていて一家は満州開発のインフラ整備のため大陸に渡っていたという。私は終戦時、満州に渡った日本人が越境してなだれ込んで来たソ連軍に殺害されたり捕虜となってシベリアに送られたりした悲惨な運命を辿った歴史を知っていたので社長一家はどう生き延びることができたのかと聞いた。すると、それは会社の雇用人や近所付き合いをしていた中国人に助けられたのだと意外な話をしだした。
中国人にとって、日本人は勝手に他国に入り込み満州国を造った侵略者であり、敗戦の色が濃くなると一気に迫害・略奪が起こるのは必然的である。その中で彼らは中国人と見分けがつかぬよう変装させてくれて国内の親戚を総動員し、リレー方式で引き上げ船が待つ港まで送り出してくれたと言うのである。
それを聞いた私はすかさず中国人のその行為はご両親の人徳によるものだと断言、続けて兄貴はまさしくそのDNAそのものを受け継いでいるのではないかと言いきった。