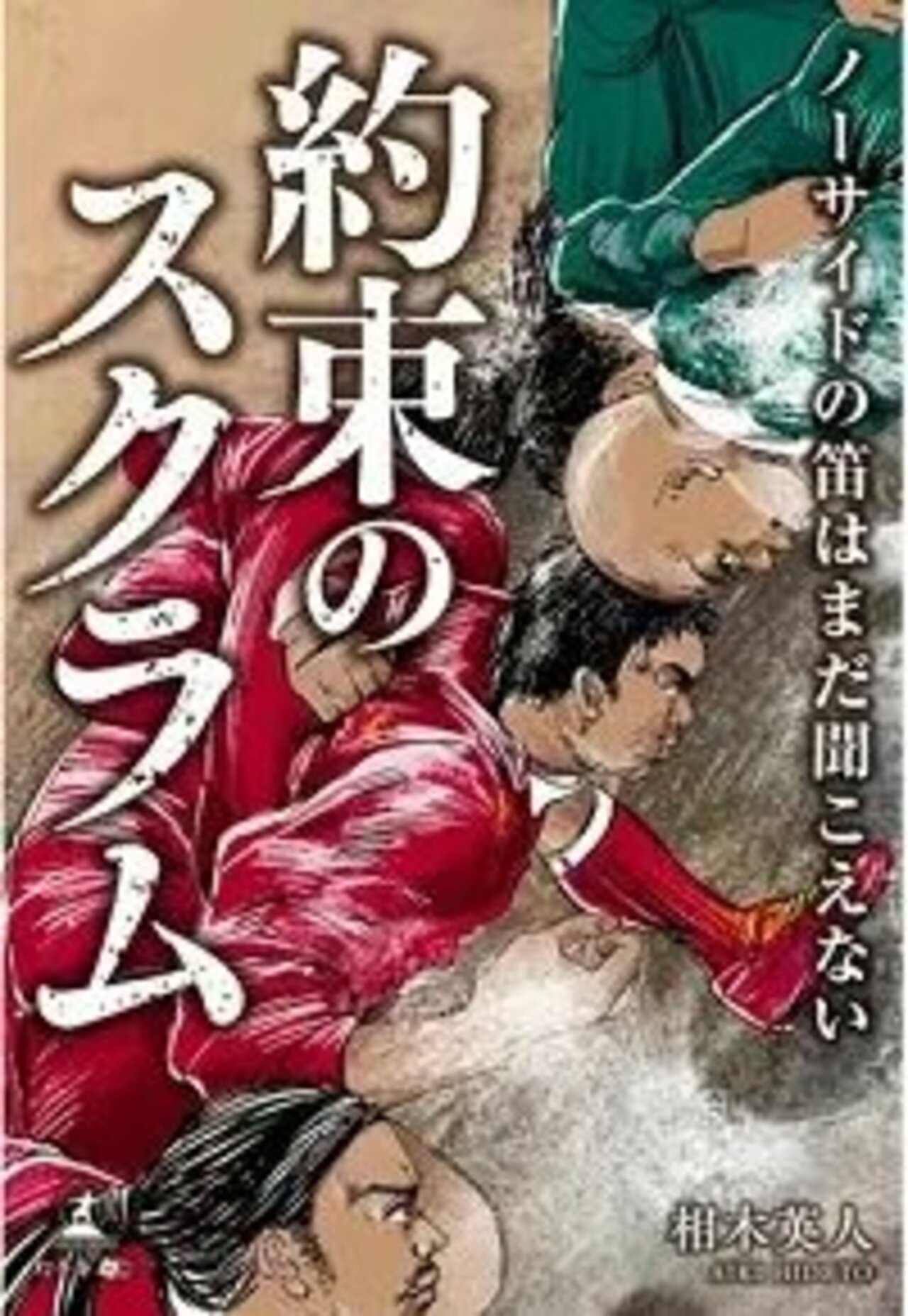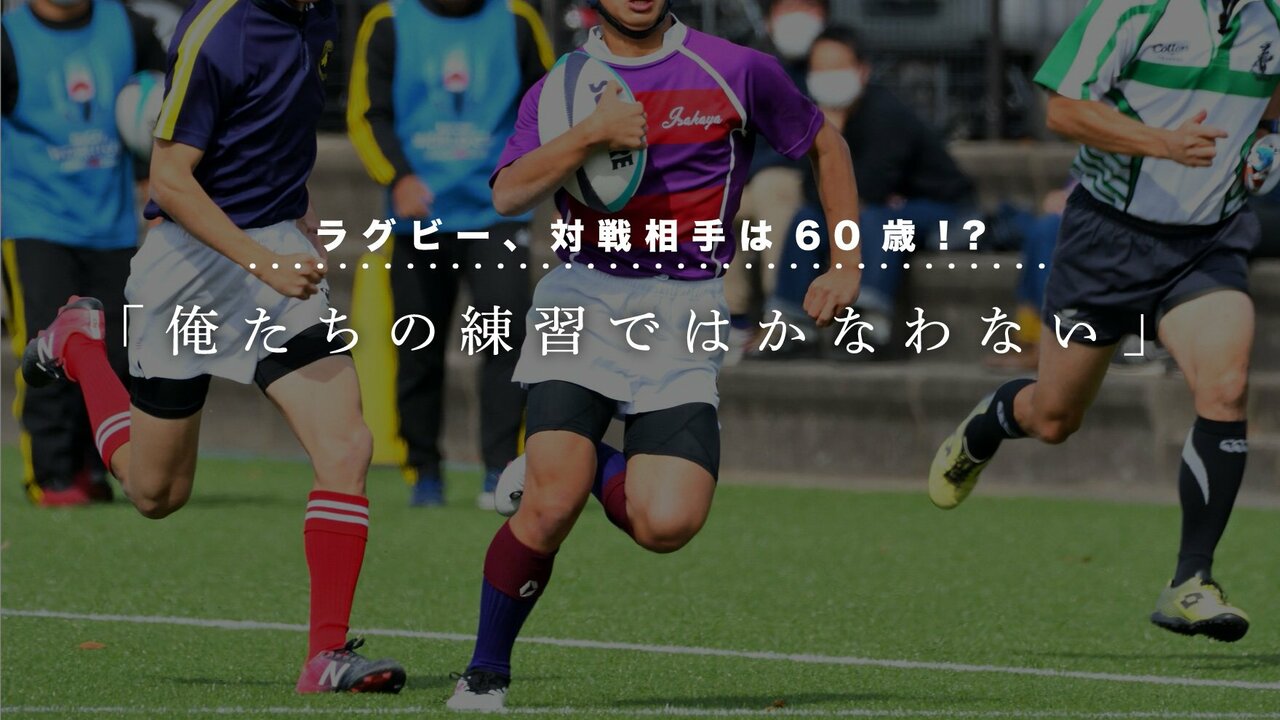第二章・記念試合 ~二度目の卒業式~
二〇〇七年三月十日(土)
記念試合の当日が来た。
楽しみにしていただけに朝早くに目が覚めた。学校へ向かう途中、コンビニで朝刊を買った。今日の記念試合の件が取り上げられると先輩たちから聞いていた。新聞の朝刊に、今日の記念試合の記事が出ていた。高校での練習風景の写真が大きく載っていた。二回生、四回生の先輩たちだ。
タイトルが『青春の地 胸に刻む』となっている。「今月閉校 きょう記念試合」とサブタイトルがついている。いつの間にか話が大きくなっていた。
びっくりだ。今日の記念試合のいきさつが上床先輩を中心に紹介されていた。誰かが新聞社にこの思いを伝えたのだろう。
……こんな事が出来るのはあの先輩しかいないか。
地方版だが、新聞の記事にまでなった。少し感動した。そして、俺たちの「思い」を世間の人に少しでもわかってもらえたなら、嬉しい限りだ。
学校についた。既に大勢いる。四十名のOBとその家族たち、総勢七十名ほどか。同級の六回生の女子たちが十数名集まっていた。懐かしい顔ぶれだ。キミもいた。背が高くスマートで全然変わっていなかった。
そして当時のラグビー部の顧問であった鬼と呼ばれた先生たちがいた。加藤(貞)先生と小川先生だ。加藤先生は一年のときに、小川先生は二、三年のときの監督だ。二人ともかなり(相当)厳しかった。
特に加藤先生は「グッチ」のあだ名がついていた。そのあだ名の由来は、当時ローラーゲームというローラースケートを履いてぶつかり合うスポーツ(懐かしい)があり、その外国チームのむちゃくちゃ暴れる監督がグッチという名前だったところからついていた。
俺たち一年生は入部当時二十三名いたが、二ヵ月後には半分以下に減っていた。
「加藤先生。お久しぶりです。六回生の相木です。覚えておられますか?」
「蟹江高校の最後の年だ。いろいろあったから忘れられんよ」
厳しく育てられたおかげで俺たちは強くなった。試合はなかなか勝てなかったが。今では感謝している。練習で俺は頭を切り病院で数針縫った事があるが、その時は家までついてきてくれた。グラウンドを離れると、本当にもの静かなあったかい先生だった。
小川先生からも
「蟹江に来て最初の生徒たちがお前たち六回生だ。忘れるものか。相木が小柄なその身体でフッカーをやっていたのにはびっくりしたよ」
お二人とも元気で嬉しかった。お二人にとっても俺たちの年代はやはり節目の年で記憶に残っていてくれた。OBは二回生から二十三回生までそろった。二十代から五十代まで幅広い年齢となっていた。