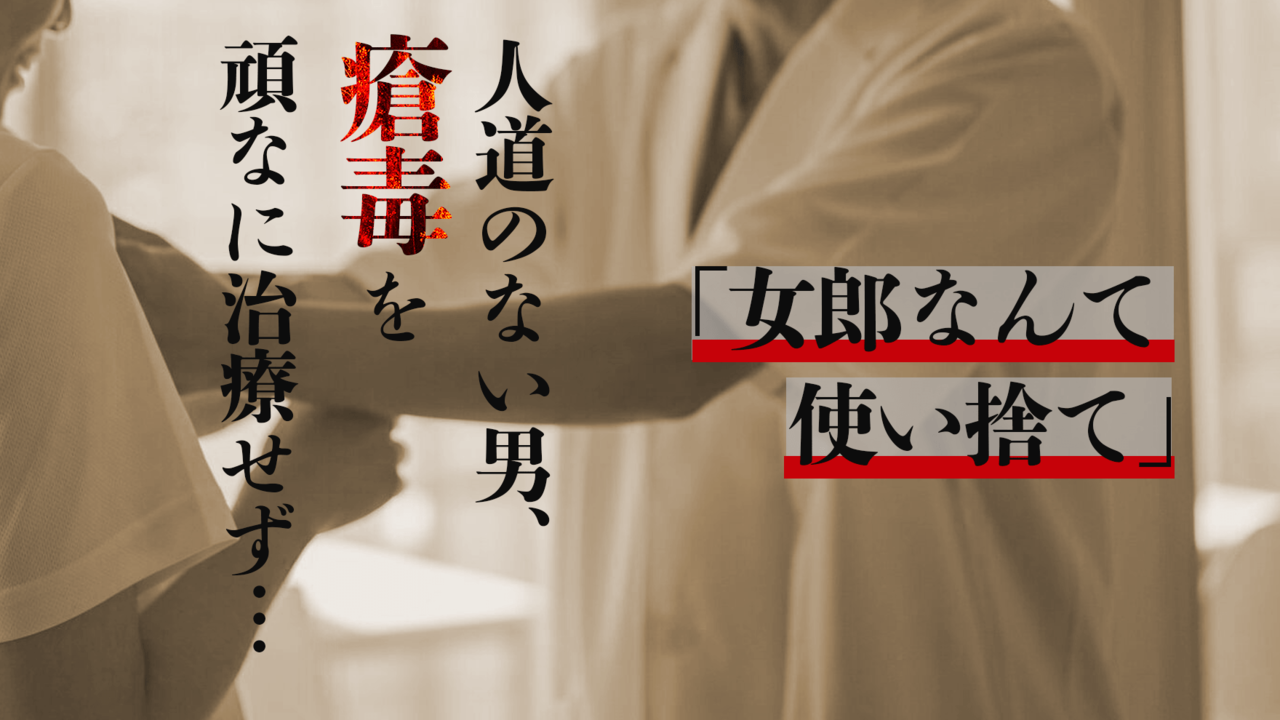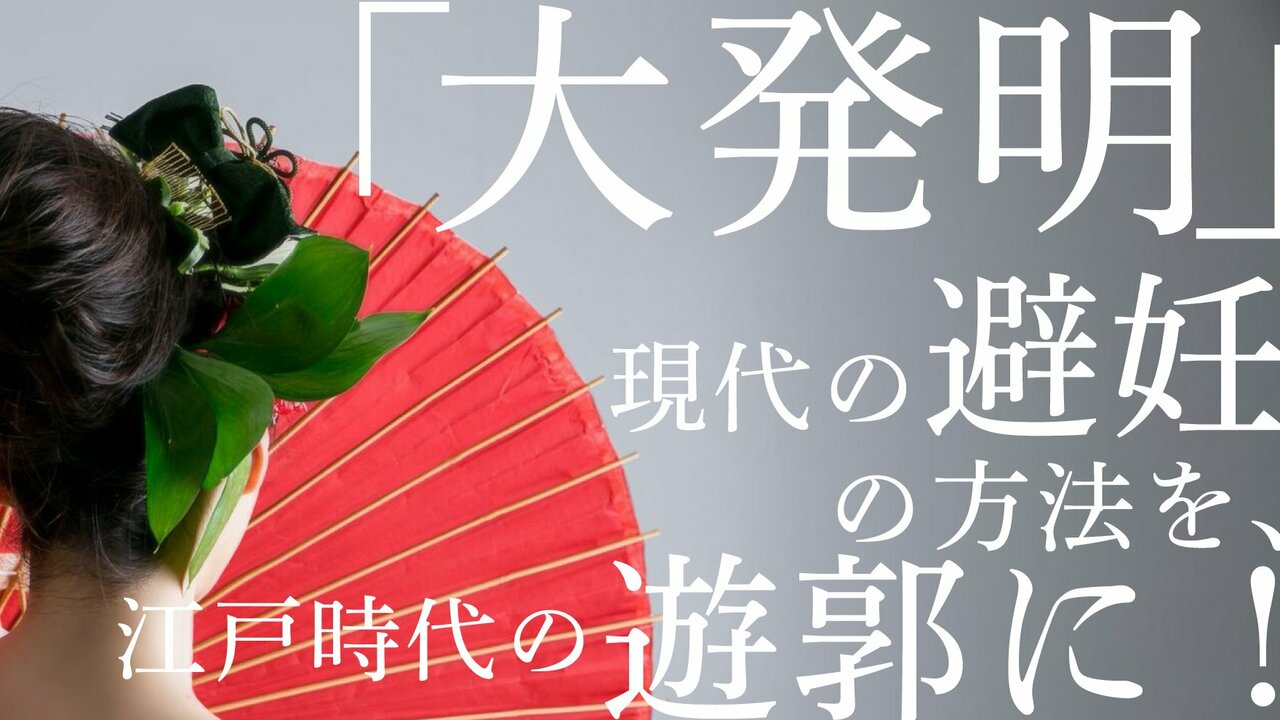第一話 ペニシリン
嘉永七年三月三日(千八百五十四年三月三十一日)に江戸幕府とアメリカ合衆国が締結した条約だった。そして……ペリーが来日して、不平等条約を締結してから、一年後だった。
大川の桜も散り、川岸坂のツツジの花が咲き乱れる、毎日だった。満潮近くになった緩やかな川の流れに太陽の光が輝き、爽やかな潮風が夏の訪れを告げる、青葉若葉が風に揺れる季節だった。黒いキャスター付きの旅行用大型トランクボックスを二台転がし、背中には黒のリュックサックを背負い、吉原大門前に立っていた。
三十代半ばに見える、その男の颯爽とした出で立ちは、白い医者服を羽織っていた。グレーのジャケットに赤系チェックのカジュアルシャツを外に出し、レモンイエローのチノパンに太い茶色の皮ベルトを締めて穿いていた。背筋を伸ばし、素足に黒系のサンダルを履いていた。「おっ! ここだな」と辰の刻朝五ツ(朝八時)に木戸門前に立った。
「中に入ってみるか」すると……禿げた頭に小さな丁髷を載せた六十代ほどの木戸門の番人が出てきた。
「お前さん。何者だい」
「薬屋です」
「医者ではないのか」
「はい。医者も兼ねています」
「なら初めからそう言えよ」
「申し訳ございません」
「こんな朝早く廓になんの用だい」
「わたくしは梅毒専門の医者兼薬屋ですので、お女郎さんの病気を治すために来たのですよ」
「梅毒とはなんだ……」
“そうか! テレビで観た『JIN―仁―』では瘡そう毒どくと言っていたな”
「瘡毒です」
「それなら分かるよ。で、何処から来たのだ」
「江戸川区です」
「ここは江戸だぞ」
“そうかぁ”
「葛西です」
「葛西村か」
“江戸川区は東京村だったな”
「そうです」
「なら、漁師の子か」
“違うけど、長くなって面倒だから、そうしておくか”
「そうです」
「それでなんで薬屋になったのだ」
「先にも言った通り、お女郎の瘡毒を治すためです」
「そんな不治の病を治す薬があるのか」
「わたくしが開発しました」
「そうかぁ……」
「通っていいですか」
「ちょっと待て」
「はい」
「とりあえず中に入って詳しい話を、お役人の田宮様に話してもらうか」
「そうですかぁ~ではお願いします」と二人で番小屋に入った。