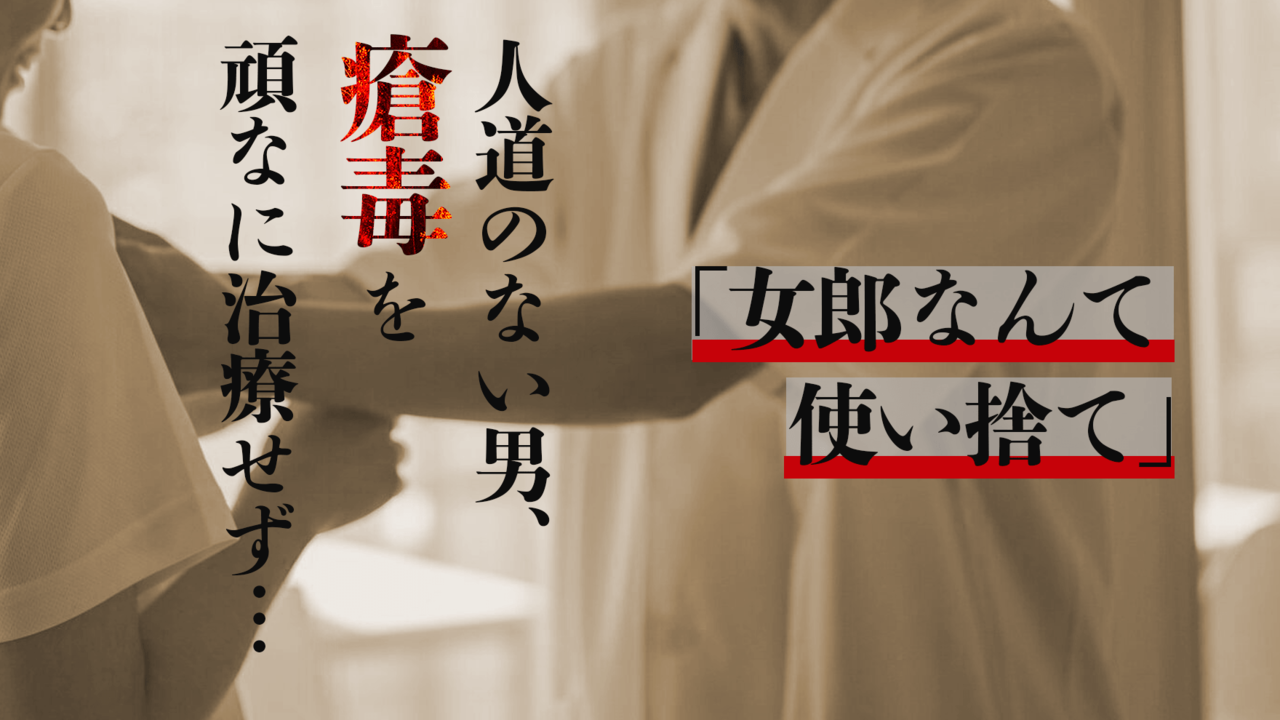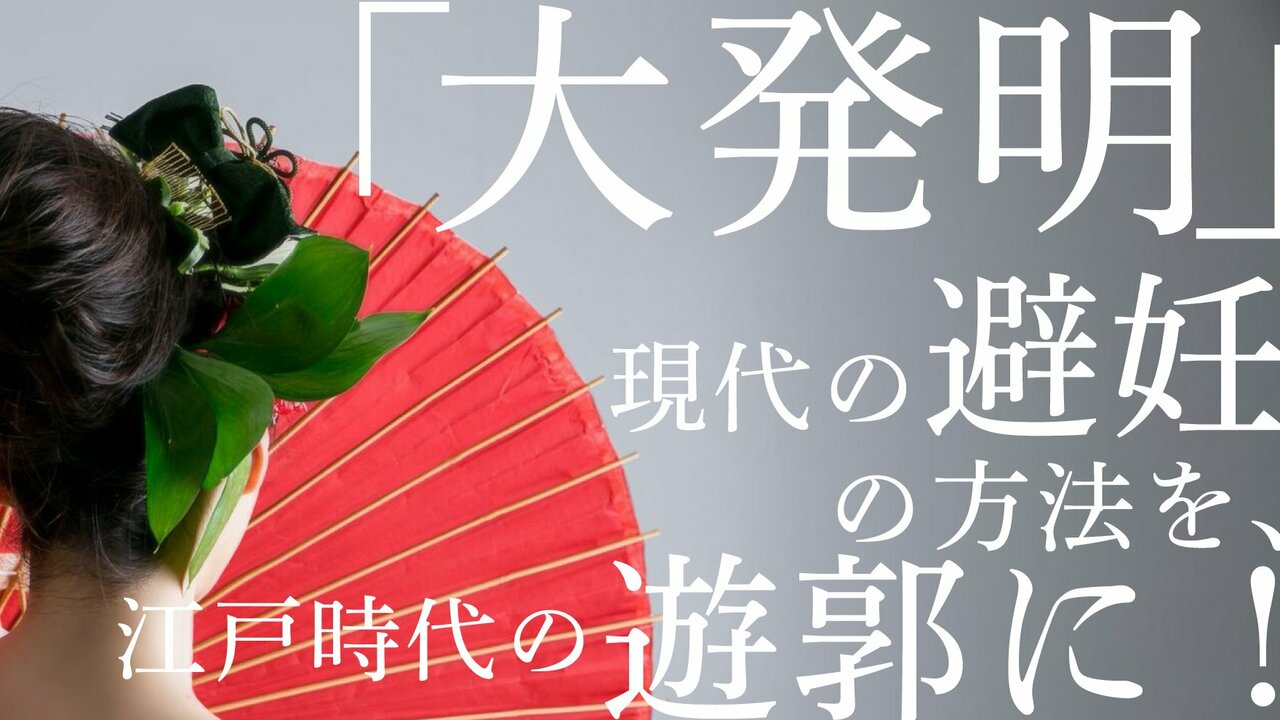「田宮喜平様。薬屋を連れてきました」
「名はなんと申す」と五十代に見える髪の薄い同心に聞かれた。
「富司洞泉と申します」
「屋号は」
「豆屋です」
「豆屋が薬を売るのか」
「私の代で薬屋に変わりました」
「いくつだ」
「三十七歳です」
「女房子供はいるのか」
「いいえ。まだ一人者です」
「使用人は何人いる」
「私一人です」
「それで出来るのか」
「はい」
「そうか。それに変わった服に見たことのない箱を持っているけど、どこで手に入れたのだ」
「この服はメリケンさんが着ていたのを見て、動きやすそうなので自分で作りました。それと、この箱は下に車を付けて運びやすく作ったのですよ」
「全部自分で、なのか」
「そうです」
「ずいぶん器用なんだな」
「これだけが取り柄です」
「中には何が入っている」
「瘡毒の薬関係です」
「開けてみろ」
「はい」と赤いトランクから開けた。
「これはなんだ」と指を差した。
「注射器です」
「どうやって使うんだ」
「この液を入れて瘡毒を持っている、お女郎さんの体に注入して治すのです」
「飲み薬ではないのか」
「はい」
「効き目はあるのか」
「軽い瘡毒なら一回打てば、二~三日で治ります」
「重いと……」
「一週間ですか。ただ寝たきりになるよぅなら無理ですね」
「まさか伴天連ではないだろうな」
「違います。全部自分で作りました」
「そうか。と、この箱はなんだ」
「これはマラサックです」
「マラ……とはなんだ」
「これです」と自分の股間を指した。
「それがなんの役に立つのだ」
「お女郎さんとお客が、お互い病気をうつさないようにです」
「どう使うんだ」
「マラに被せて、お女郎さんの陰部に挿入するのです」
……!?……
「そうすると、お女郎さんもお客も病気がうつらなくなるのですよ」
「そんな便利なものがあるのか」
「はい」
「どのくらいあるんだ」
「ペニシリンが一万本。マラサックが同じく一万枚です」
「そんなにあるのか」
「ご納得いただけましたか」
「まぁ……いいだろう」