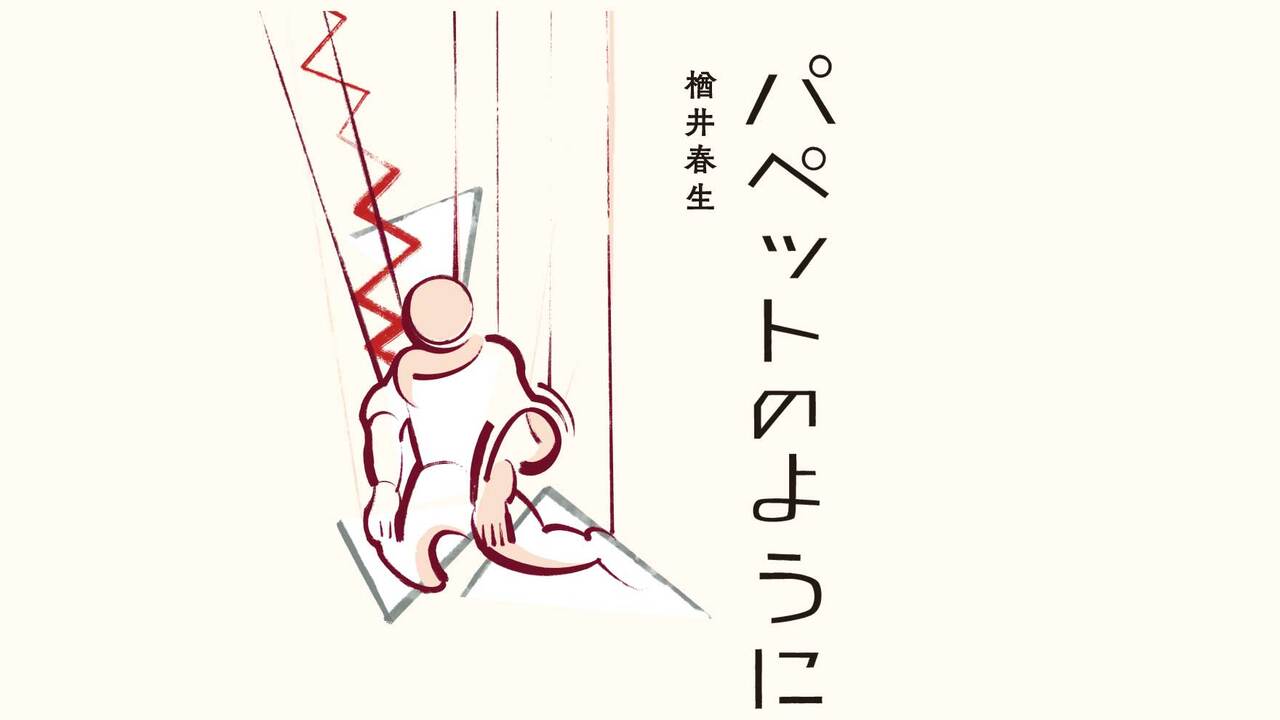一部 ボートショーは踊る
一
俊夫はハンカチで汗を拭きながら中に入って行った。奥の方で、鼻眼鏡をかけたどこか飄々とした雰囲気の老人が狭い受付のカウンターの向こうで腰を下ろして本を読んでいる。
「ビザ用の写真をお願いしたいんだが。すぐお願いできますかな。急いでいるんだが」
老人は鼻眼鏡の蔓に手を添えて俊夫の方を振り向いた。
「どうぞ、こちらへ」
俊夫は奥の部屋に招き入れられた。古びた脚立付きの写真機が一台あるだけのがらんとした部屋だ。俊夫を椅子に座らせ、老人は脚立の上に乗せた古びた写真機をいじり、ファインダーを覗き込んだ。何が気に入らないのか老人は脚立をいじったり、写真機を取り外してファインダーを調整し直したりし続ける。
「ちょっとお待ちを」
そういって老人は自分の頭を黒いフードの布の中に隠した。俊夫は足を組み直したり、ちょっと表情を取り繕ってみたりしながら待った。
「ちょっと、左の足の位置を変えて」
「どのように」
「ご心配なく。足は写しませんよ。でも、顔の表情とか、生きた人間の姿に撮るには写らない部分も絵的にはすべてが完璧でありませんとね」
なるほどそうか。もし芸術的に凝った考え方をする写真屋だったらそういう考えもあり得るだろう。そんなふうに俊夫は妙に感心してなおも我慢しようとするのだが、苛立ちは一層募って来る。
カシャ。フラッシュが焚かれ、一瞬俊夫は目眩を覚える。目をくしゃくしゃすると、ようやく焦点が合った。黒いフードから顔を覗けた老人の鼻眼鏡が歪んでいる。
「見えまするな、あなたさまの心が。本当の姿が。その純粋な心を何時までも持ち続けなされ」
老人は眼鏡の蔓に手を添えていう。
「何が見えたんだって」
俊夫は皮肉っぽく聞き返した。
「純粋さが、何か、とっても透明な深いものが。あなたの目の中に宿っておりまする。このファインダー越しだと普通では見えないものまで、人の心の中までがはっきりと見えてきます。どんなに偽っていても」
何をいいやがると、俊夫はむかついて心の中で毒づいた。お世辞にしては妙だし、からかいにしては稚拙過ぎる。我慢も限界で、怒りが爆発しそうだった。あんたに化けの皮を剥がされ本性を見破られるほど単純な俺ではないぞ。
少年に純真さを囃すとしたらそれは褒め言葉だ。だが中年男に向かって同じことを語るとなると、ひねた中年男だったら(この俺様もそうだと認めざるを得ないが)十人中十人が馬鹿にされたと思って怒り出すだろう。ひねていなくても喜ぶ奴はいないさ。それが分かっていない鈍感さが許せない。
それとも、この老人はもう呆けていて、俊夫を子供と見間違っているのかも知れない。どうせ時代遅れの、霞を食って生きている写真屋さんだ。