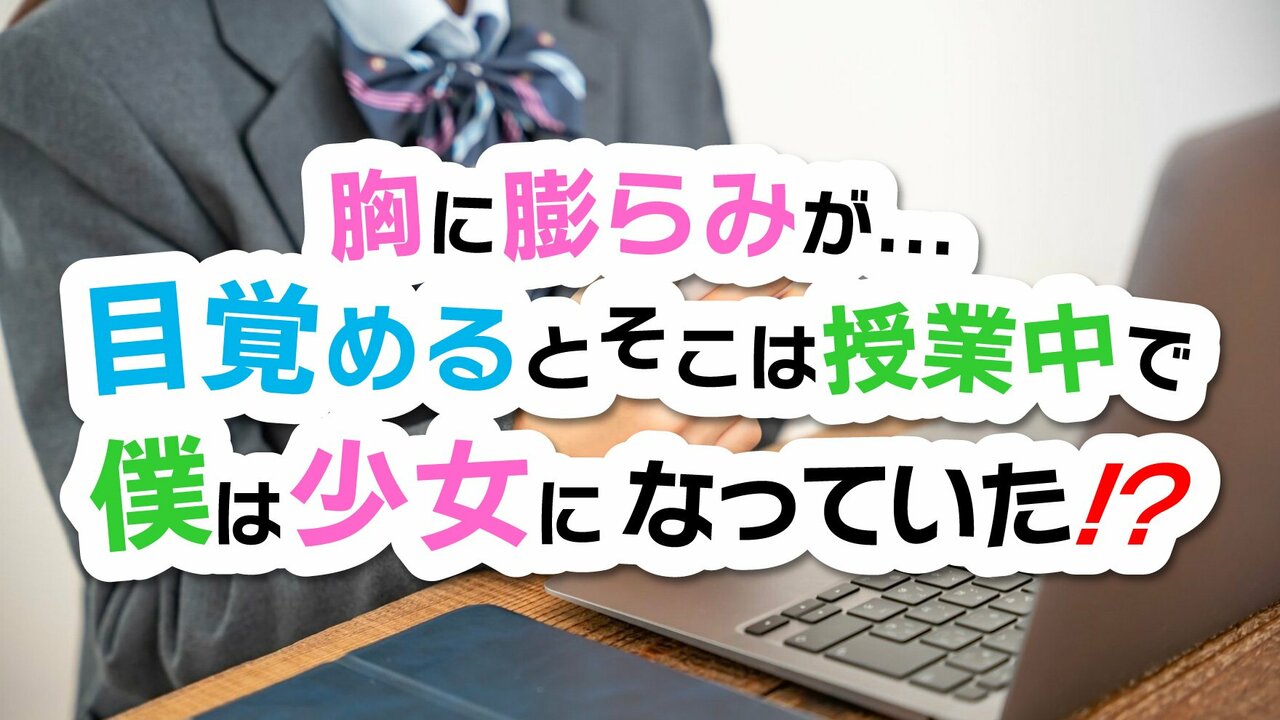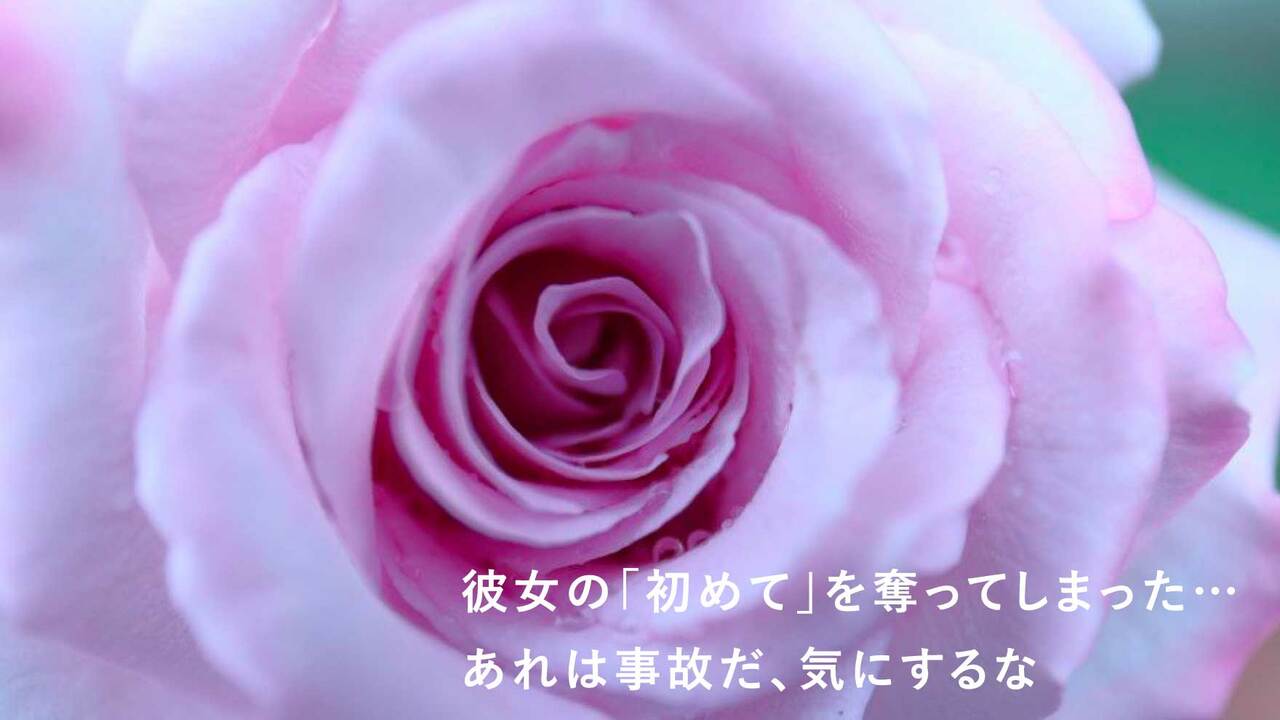序章 冷たく壊れた姫君の夢
気づけば千年にもわたる、果てのない永遠の恋。数多の星の、一つひとつが燦然と輝く夜の天空の下で、想う彼の人と二人きりのひととき。見渡す限りに水面が張る、透き通るように清らかな湖は、まるで写し鏡のように空模様を反射させ、世界は星の輝きで煌めいている。
──彼とともに過ごせる時間はもう、現実ではないことを悟っているけれど。だからこの、星の残光が糸を引いて消えゆく瞬間が“夢”であることは承知している。
幾度か言葉を交わし、最後に彼は告げた。
「──」
けれど。境界線を過ぎれば、落ちた雨粒によって生まれた波紋が広がり消えゆくように、記憶は奪われてゆくもの。それは数え切れないほど味わっているのに、胸が痛い。
「……ん」
……──からっぽになった教室の、開けた窓から流れるそよ風が、眠りから覚めた少女の長い黒髪をはらりと揺らす。雪のように白い肌の頬を、柔い毛先がくすぐった。微睡から覚めながら、宝石のような双眸で傍らを窺う。机が滑稽味もなく四方に並び、黒板には落書きの欠片もなく、風を取り込んだカーテンが風船のように膨む。沈みかけた夕陽と、黒いセーラー服を身にまとった少女の影が、床にコントラストを描いていた。針の刻みを諦めている、壁の時計。世界は、進み続けているというのに。
再び机に身体を委ねて、少女は物憂げにまぶたを閉じた。また、夢を見るために。
夢は好き。だって、願いが叶うから。特にこの七月七日は、彼と巡り逢えるから好き。忘れかけた胸の鼓動も高鳴ってくれる。氷のように冷めた肌も、火照りを思い出す。けれど〝悪夢〟もあるから、……やっぱりこの日は嫌い。
消えゆく意識の中、少女は願った。
「また、逢えますように」
目尻から頬に零れ落ちた一筋の涙の意味を、眠りについた少女本人でさえ、もはや知らない。