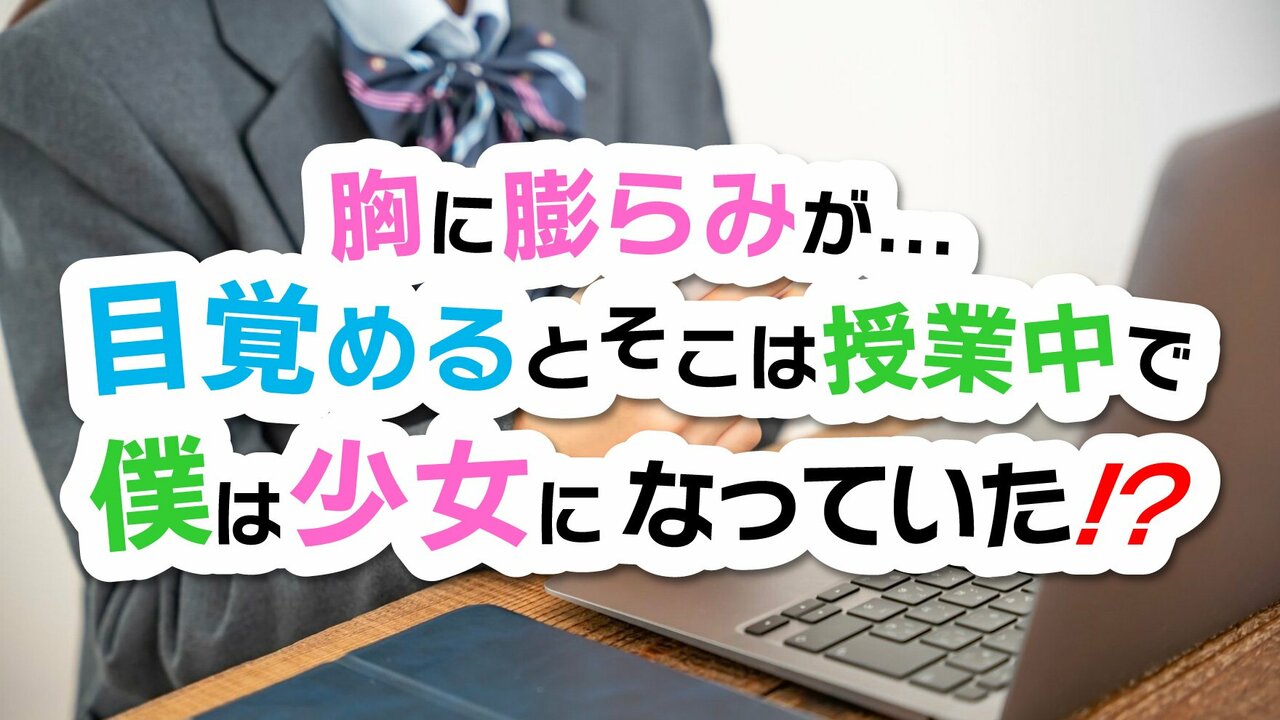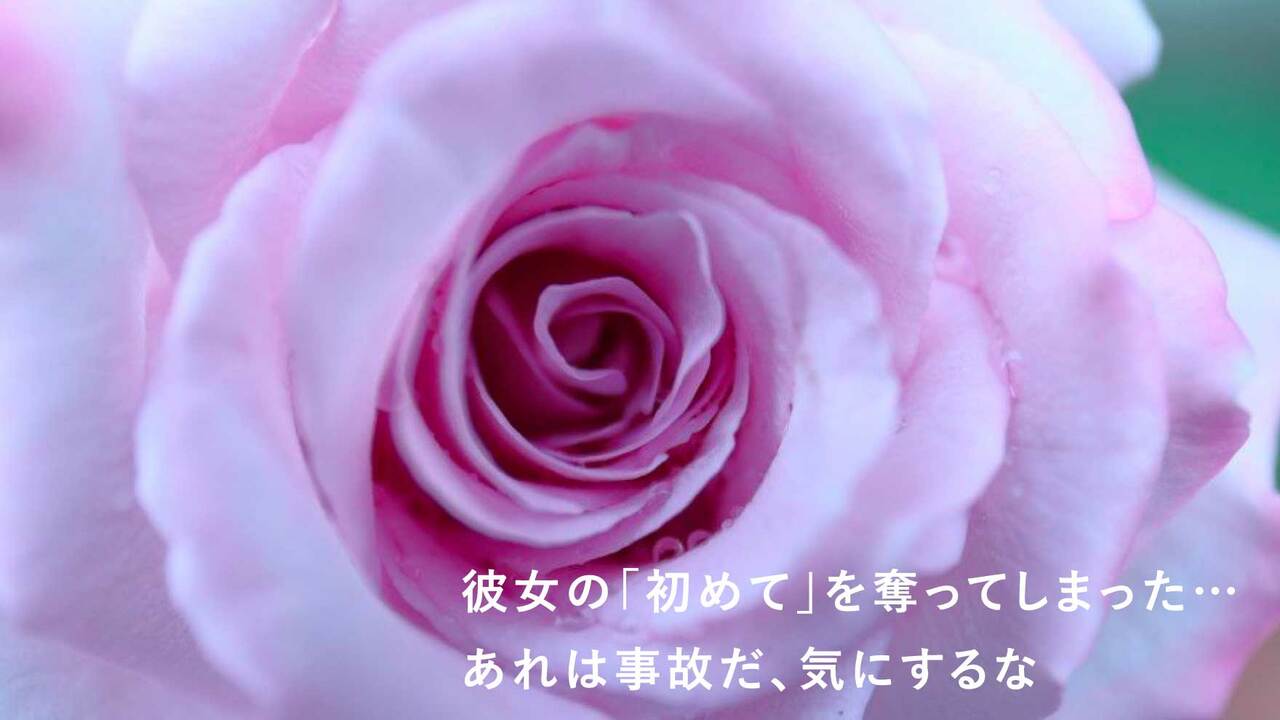1章 まやかしの織姫と彦星
「はぁ、疲れた。学校、早く終わらないかな」
クラスメイトと適度に会話しながら腹八分目に昼食をすませた二宮玲人は、特に目的もなく校舎を出て、ぶらぶらと校庭を散歩していた。数少ない友達は用事で教室から消えてしまったから。イヤホンを耳に差し、机に伏したまま午後の授業を迎えるのも構わないが、賑やかな教室には少なからずの居づらさもある。それゆえに散歩で昼休みを消化することが、図書室通いに並ぶ彼の日課になっていた。
「まったく、暑い中よくやるよ」
グラウンドでは制服姿の男子らがグラブを手にはめ、声を張り上げてキャッチボールをしている。坊主頭に太い眉、鉄骨のように逞しい体躯、遠くまで届く声……、様々な面で玲人とは対照的だ。そんな生徒らを横目に、整髪料で形づくった栗色の、同級生に比べて長めの髪を指でかき分けた玲人は先をゆく。
しばらく校庭を巡り、花壇の前でしゃがんだ。鮮やかな花が咲いている。マリーゴールドにミニヒマワリ、サルビア。花に興味はないが、ともあれ内臓を撫でられるような不快感はない。教室で過ごすときよりは。生まれながらに恵まれた中性的な顔立ちが自然に和らぐ。
「五限目は英語か。教室に戻ってから復習しようかな」
英語は担当の教師が先回の授業を振り返りせずに、次の内容に入りたがる傾向にある。賑やかな中での復習は気が進まないが、これから図書室に向かうのも時間の無駄になるし、まあ仕方ない。英語に触れる時間は好きだし。
(気づけば六月上旬。早いな、ついこの間までは春だったのに)
天を見上げた玲人。白い雲が青空に、呑気な旅人のように浮いていた。前まで桜の花びらが舞っていたのに、紺の長袖ブレザーに袖を通していたはずなのに、いつしか変化している。代わり映えしない日々を送るせいか、自分だけがこの世界に取り残されているような錯覚だ。
七限目の授業を終えても、難関大学の進学に特化したコースの生徒である玲人に待つのは、来年の受験を見据えた一時間の補習。そのあとに一日の学校生活がようやく終わる。しかし帰宅したところで昨日のくり返しのような、やはり退屈な時間が控えているのだが。
「きっかけがあれば。何か少しのきっかけがあったら、変わるのかな」
あやふやな望みを胸によぎらせ、空から視線を戻す。身体が汗ばんだ頃、自販機で紅茶を買っていこうと、玲人はおもむろに膝を伸ばした。
「さてと、戻るか」
綺麗な歩幅で歩みを進め、校舎の角を曲がろうとした─……。
倉科奏空と二宮玲人、─────二人は思いもよらぬ形で”再会”する。