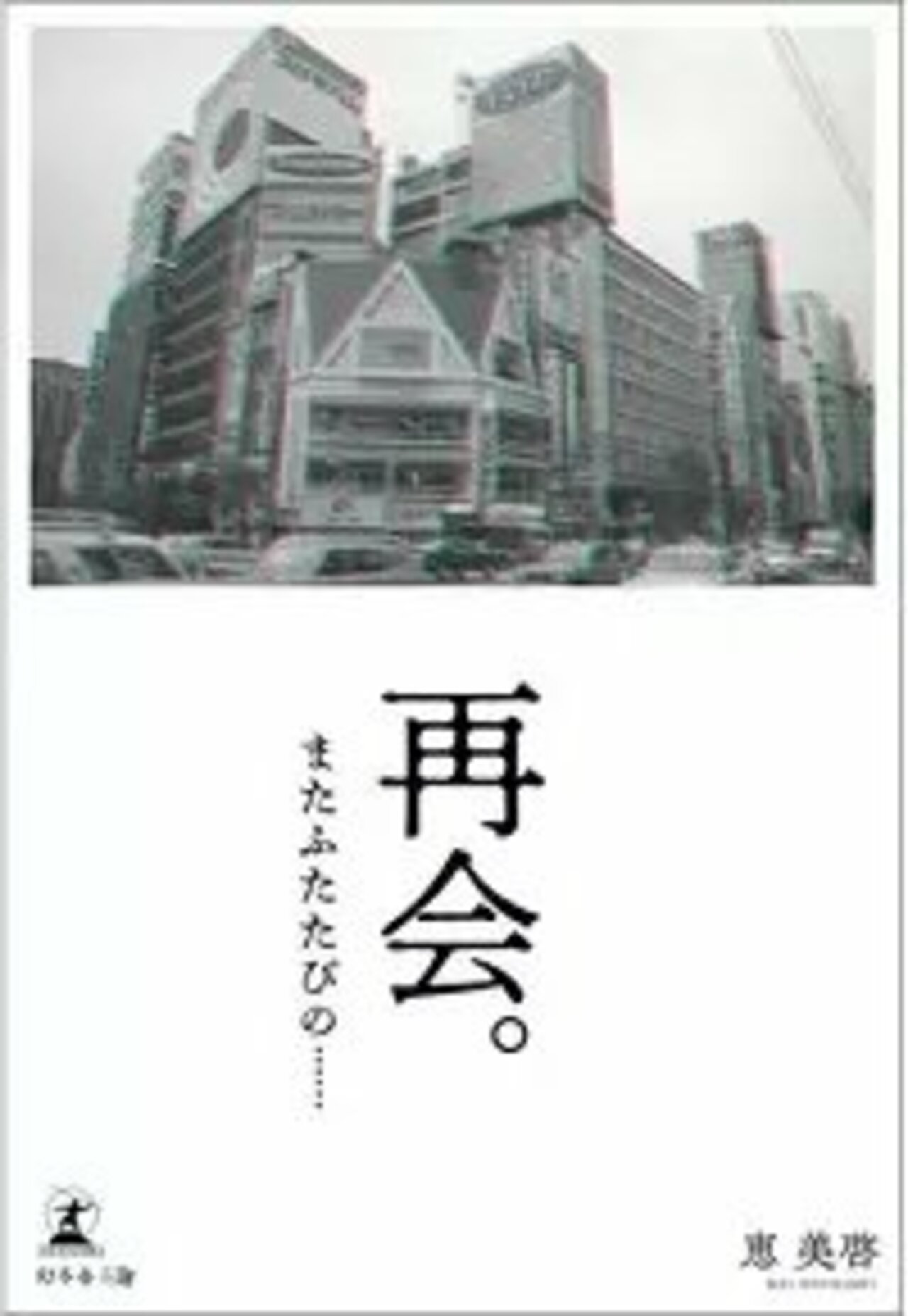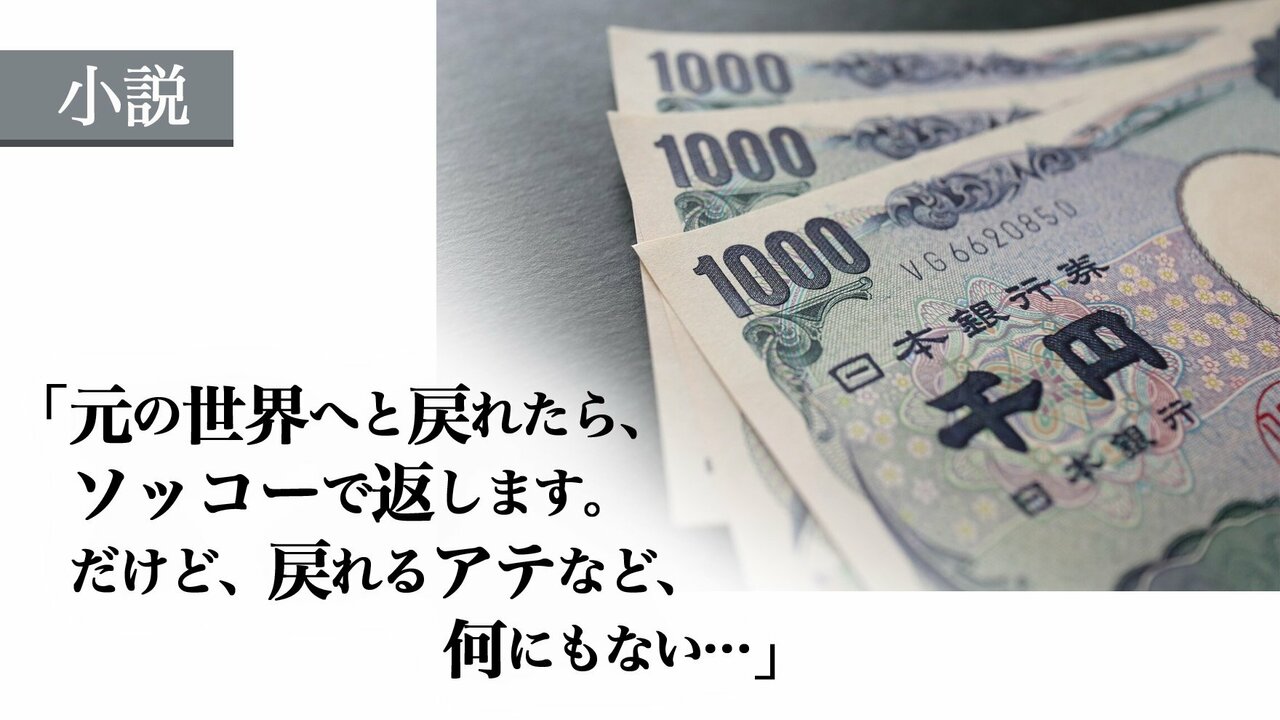プロローグ
今夜、そんなには遅くならないだろう。きょうの土曜出勤は、米国出張から戻ってくる三田専務の報告を直接聴くだけのため。だから、ネクタイを締めず、スーツも着ていない。だいたいのことはメールですでにわかっているのだ。
「でもさ、慰労というか、顔を見てね、おつかれさん、と三田さんに直接、言ってあげたいわけよ」と生駒は言う。
設立当初からの仲間でもある。学年は同じだが数か月、生駒の生まれが遅い。たいていは「三田さん」とサン付け。ときおり、敬語を使う。「技術面はヤツがいなきゃ、どうにもならない」らしい。
もう一人の設立メンバーは経理や総務全般を担当する梅木という既婚女性。常務取締役。三人はアメリカで知り合った。会社としてはこの役員三人だけだが、社外に何人もの協力者がいて、「いわゆるネットワーク型のベンチャーなんだよ」との説明は、たしか、つきあうまえに聞かされた。いまも、ピンとはきていない智洋だが、社長の生駒が多くの同志のような友人らによって支えられていることは、理解していた。
成田に十時ごろ到着だから、オフィスで昼飯でもしながらの報告会、せいぜい二時間程度として、四時か五時には帰ると昨夜、言っていた。「だから、問題ない」とも。
智洋は、このあとの昼食をマダムに誘われていた。
「わたしは、二時か三時には帰ってるから」
「どこだったっけ?」
「三軒茶屋だって」
「また、おしゃれな店へ連れて行ってくれるんだろうなあ」
「でしょうね」
「相変わらず、親切な女性だ」
「そうね……、こっちの親切は取るに足らないっていうか、当然のことをしただけなのにね」
「まあしかし、こういう縁は大切にしておくに限る」
智洋にも異論はない。きょうの約束が直前にオファーされたものであれば、あるいは「申し訳ないけれど……」と断ったかもしれない。平日ではなく、週末のこと、夫が在宅している。それほど失礼でもないだろう。が、マダムは、かなり以前に、この話を持ち出してきた。なんでも知り合いのレストランのグランドオープンで、激励に行くから、つきあえ、と。
一月の下旬のことだったか、そのときは、生駒に異議もなく、気軽に承諾した。そもそも、生駒のきょうの出勤は二日前の決定だ。米国での用向きが長引き、専務の帰国が一日延びた、その結果である。