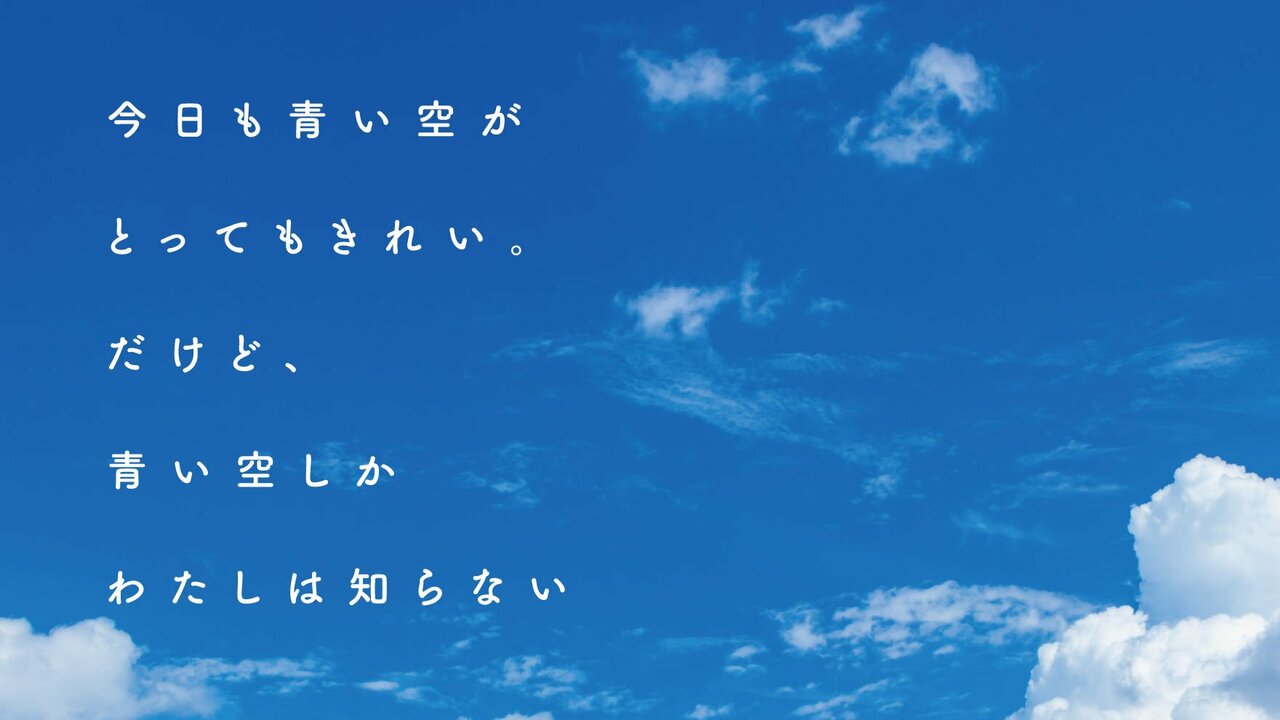花の精ラーラと木の精リックの物語
ラーラはひとりの少年と出会いました。その少年は、押し花がだいすきで、ふくろにたくさん花をつみとると、家にもちかえっては、本のあいだにはさんでいました。花の精であるラーラは、ほんとうは花をつみとってほしくはありませんでした。しかし、少年のつくる押し花はとっても美しいのです。つみとった花からていねいに土をおとし、水分がはやく抜けるように、くきの部分にやさしく切りこみを入れたり、どうすれば花が枯れずにすむのかも、いっしょうけんめい研究したりしていました。
「花をつみとって、永遠にしようなんて、ほんと人間て、勝手な生き物だわ」
そう思いながらも、少年の花に対する情熱に、ラーラはいつのまにか惹かれていったのでした。ラーラは、少年の部屋からふわりととびたちました。
そのころリックも、あるひとりの少女に出会いました。少女は、病気でずっと病院のベッドで横になり、小さな窓から見える景色をながめているだけの生活を続けていました。そばには、リックの好きなかわいいピンク色の花がかざってありました。
「今日も青い空がきれい。とってもきれい。だけど、青い空しかわたしは知らない」
少女のひとことにリックは、少女がねむっているあいだに、ふっと窓の外の木に息を吹きかけました。すると窓のそばから、木の枝がするするとのびてきて、青い空しか見えなかった景色に、美しい新緑があらわれたのです。
「あら、いつのまにか木の枝がのびてきてるわ」
ねむりからさめた少女は、ふしぎそうに窓を見つめました。その木に、コマドリがやってきて巣をつくりました。なんてかわいらしい鳥なの!
コマドリは卵を産み、その卵からヒナがかえりました。少女は毎日がたのしくてしかたありませんでした。いつかとびたつであろうヒナたちの物語を、こんなにも近くで感じることができるんですもの。少女の胸は幸せでいっぱいでした。
ある雨上がりの朝でした。
「あっ、いま小鳥が空をとんだ!」
あの小さかったヒナたちが、雨が上がるのをまっていたかのように、つばさをはばたかせ、空をとんだのです。少女は、もうひとりのおかあさんになったような気持ちで、ヒナたちの巣立ちに賛美の声をあげました。そうして、だんだんと少女の病気も回復していき、その年の秋に、少女は退院したのでした。
リックはほっとしました。そんな人間たちとのふれあいを幸せに感じ、ラーラとリックは、ふたりで湖の芝生にすわりこみ、毎日のように語りあっていたのでした。
しかし、いよいよラーラの頭の花が咲こうというそんなとき。人間たちの争う声が聞こえてきたのです。森の木を切りすぎたために、雨がふり続き、予想もしなかった洪水がおこり、食べものも流されてしまい、町中で食糧のうばいあいがはじまったのです。いてもたってもいられなかったラーラは、水の精に雨をふらせることをやめるよう、たのみにいきました。水の精はこうこたえました。
「わたしに、雨をやませる力はありません。水の精の力でもどうにもならないことがあるのです。わたしたちの力は、自然をあやつることではありません。リックは、ある少女のために、力を使って木の葉を広げました。なぜそのようなことができたのか、わたしにもわかりません。もしかしたら、幸せを望んでいた少女の強い魂がリックに力を与えたのかもしれませんね。
今人々は、己のこころさえも信じることができなくなっています。わたしたち妖精は、ただ信じる人々のこころの中にしかいられないのです。自然は自然として生きているのであって、わたしたちもその中でともに人々と生きている。ただそれだけの存在なのです」