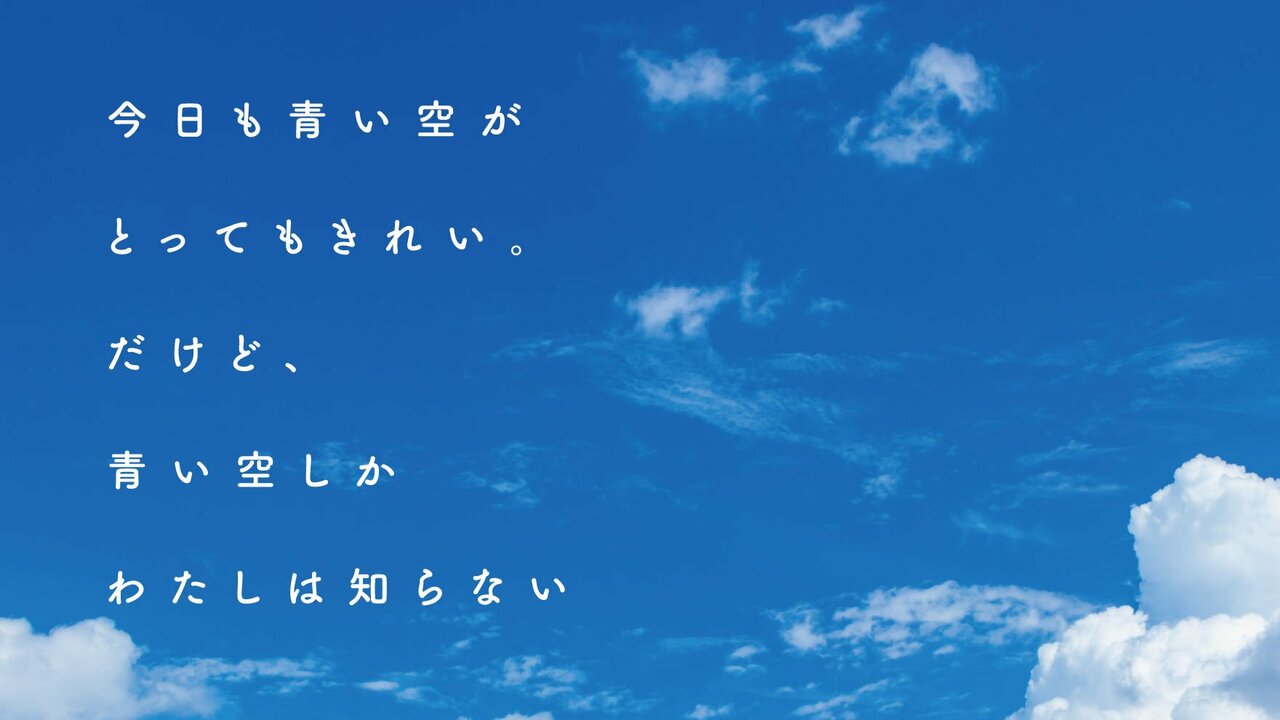ラーラには水の精のいった意味がよくわかりませんでした。花を大切にしてくれていた人たちが、苦しんでいる。自分に何ができるんだろう。ただそれだけをいっしょうけんめい考えました。いくら考えてもこたえは出ませんでした。
そんなとき、頭に小さな白い花が咲きました。花が咲いたとき、花の精はだいすきな人と結婚をするのです。いよいよやってきたのね。ラーラは大きく深呼吸をしました。だれかのためにと必死になっていたラーラは、自分のことをすっかり忘れてしまっていました。
ラーラはいつもそばにいてくれたリックを思い出しました。ラーラは、リックを探しにいきました。リックは、いつもの湖で白鳥たちとたわむれているところでした。ラーラの姿を見ると、リックは手をふりました。急いでおりてきたラーラの頭の上には、まちにまったかわいらしい白い花が咲いていたのです。
「咲いたんだね! 風がささやいた名前のように、ラーラの花は、とってもやさしい香りがするよ」
そのことばを聞いてますますラーラは、もうリックしかいないと思いました。リックも同じ気持ちでした。花が咲いたラーラと、木の精リックは、たくさんの妖精たちに囲まれて、結婚式をあげました。幸せいっぱいのふたりでしたが、妖精たちの数が少なくなっていることに、気づかないわけがありませんでした。
「ねえ、リック。今、町はみんな争ってばかり。わたしたち妖精の国も、なんだか元気がなくなって、暗くなってきたわね」
リックはだまっていました。
「もう、わたしたちがすてきにダンスをおどってみても、だれも見てくれないわ。虫たちもどこかにいってしまった」
リックはだまったままです。
「わたしにできることって、きっとあるよね」
「ないんじゃないかな」
リックがやっと口を開きました。
「何もできないんだよ。水の精がいってただろ。人間たちは今、何を信じたらいいのかわからなくなっているんだ。自分のことしか考えられなくなっているこの世界では、きっと何をしてもお互いうまくいくはずがないんだ。何か、希望のようなものがあればいいんだけど」
希望がない。リックは、自分のいったことばに、はっとしました。そうだ。希望だ。つぎにリックから出たことばはさっきとはまるでちがうこたえでした。
「ぼくたちは何もしない。だけど、やるんだよ」
「何もしないのに、やるってどういうこと?」
ふたりのはなしあいは、夜明けまで続きました。