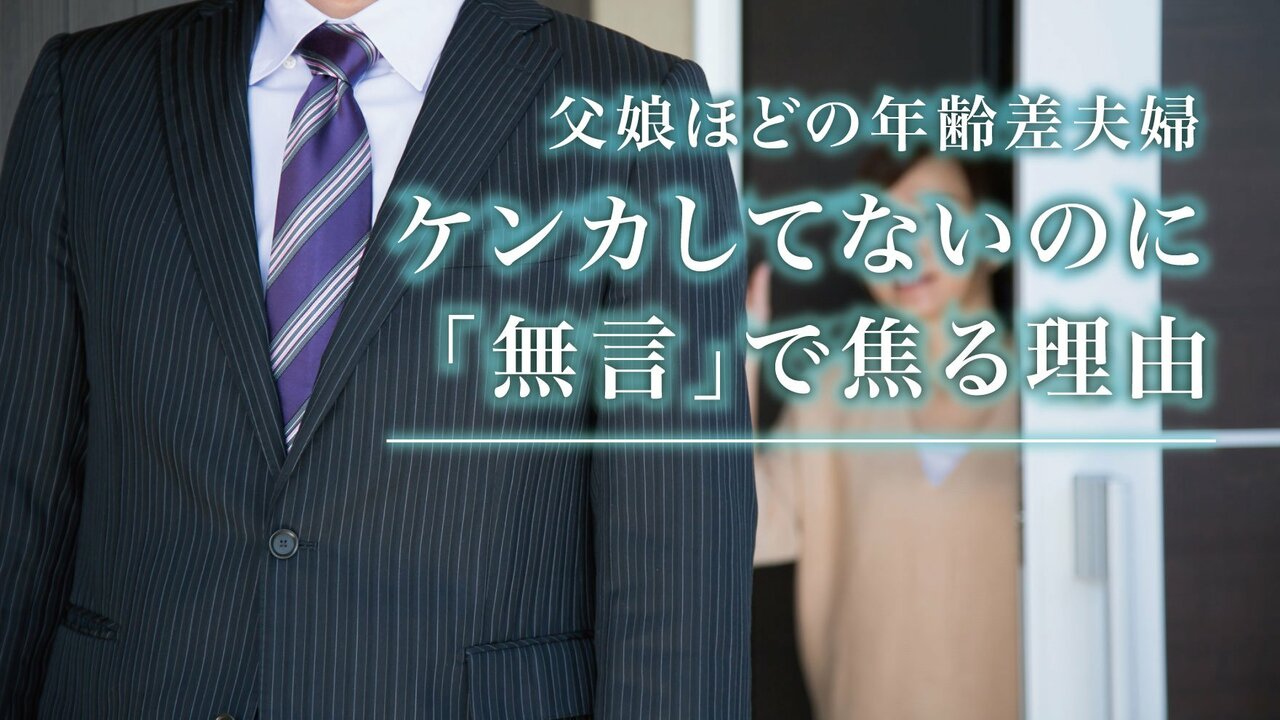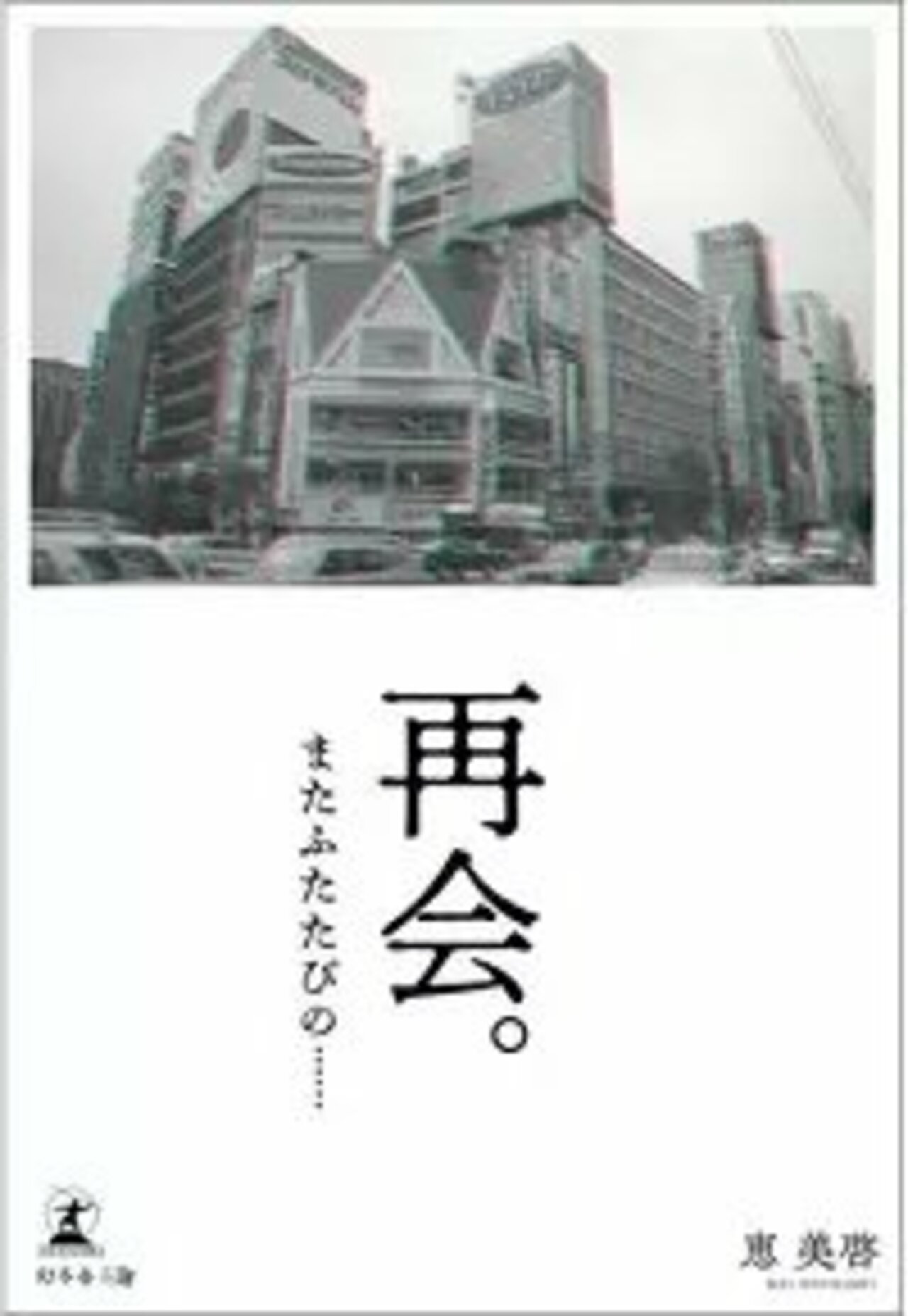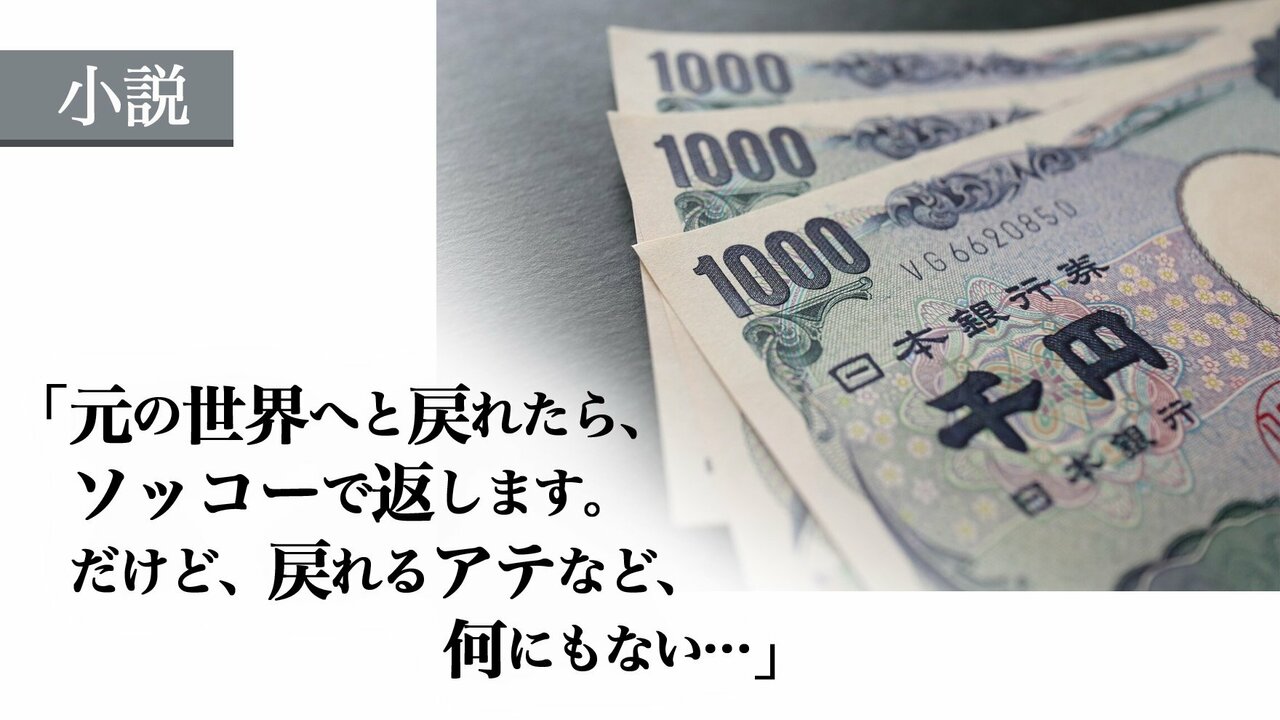プロローグ
「風の冷たさが意地悪くなくなったみたい」
高橋智洋は満面の笑みを浮かべ振り返った。さりげなさを意識した。つとめて明るく口にしたつもりだった。
玄関の三和土で前屈みになって靴を履こうとしていた高橋生駒が、その動作を止めたように見えた。面白い言い方だね、とか、春が近いんだね、でもいい、とにかく何か喋って……、智洋は祈った。
夫はもう何分も口を開かない。ケンカしたわけじゃないはずなのに……そりゃ、ちょっと、ちょっとだけ、嫌みなことを言ったかもしれない。けど……、いつもなら、笑い飛ばすじゃない? 相手にしないじゃん、こんな子どものわたしの言うことなんか。
生駒は、しかし、黙ったままである。
べつに、謝ってもらいたいわけじゃないのよ。バカみたいにヤキモチ焼いて、いまはもう反省しているの。なのに、あなたは、口をきかない、どうして?
靴を履き終えた生駒は、鞄を左手に持ち、玄関ドアを抑えている智洋の横を、すり抜けた。一瞬、何か言いたそうな顔に見えたが、結局、そのまま共用廊下へ出た。
行ってきます、は、ないの? いま、言いかけたんじゃないの? それじゃあ、わたしも、いつもの、行ってらっしゃい、が言えないわよ……智洋は、結婚以来の習慣の途絶を恐れた。
しかし、夫を見送る一言は口の中でグズグズと解けていき、エレベータに向かう生駒の背中に届くことはなかった。
こうして、習慣というものは崩れる……智洋は、悲しくなった。たかが一枚の、それも、古びた、ピンボケの、モノクロ写真によって、結婚以来のパターンに終止符が打たれた。ほとんど泣きそうだった。
生駒がエレベータの箱の中からこちらを見ている。
最後のチャンス。せめて、手を振ろうと思った。ほんのわずか、躊躇った。エレベータの扉が閉まった。間に合わなかった。智洋の右手は中途半端に空中で泳いだ。