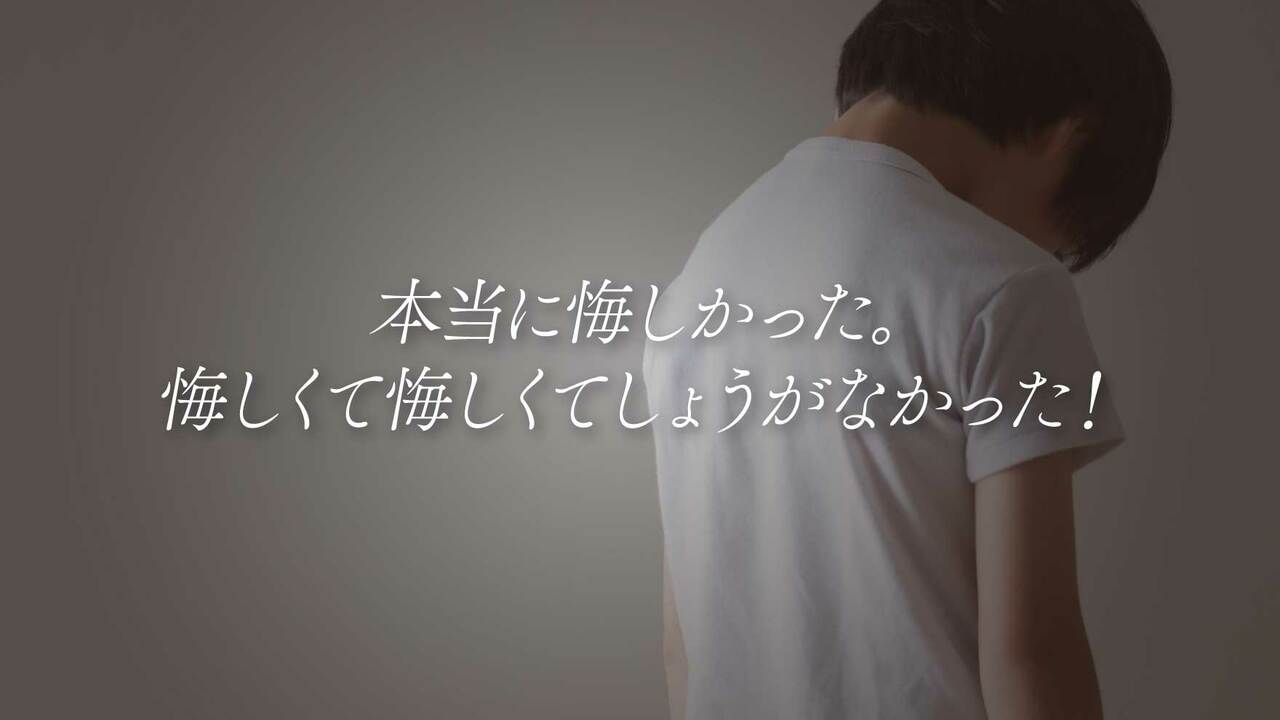【前回の記事を読む】嫌われ者の「僕」が学校に行くたった一つの理由とは…?
第一章 傷を負った者達
小学三年生を終えて四年に上がる頃、両親の仲は急激に悪くなる。まあ、どこの家にもある倦怠期というやつだ。結婚が十年も続けば相手のイヤな一面だけがすべてに見えてきて相手を汚い言葉で罵る。どこにでもある夫婦喧嘩だが、子供にしたら一大事件であり、その後の人格形成に大きく影響してくる。
我が家の場合は、父が一方的に母を罵り、母は我慢するのだ。母は掃除が苦手で物が部屋中に散らばっている。それくらいと思うかもしれないが、繊細で神経質な父にはそれが耐えられないのだ。仕事から帰ってきたら、開口一番「汚いな、掃除してるのか!」と母に大声で怒鳴る。父はネチネチと口撃したり、ときには新聞を投げつけたりと子供の僕の心は引き裂かれるどころか潜在意識に刷り込まれ決して忘れられない記憶となって残っている。
確かに父の言い分が正しいのだろうが、しかし、正しい思いも言い方ひとつで悪にも善にもなる。言葉に無頓着な父は母を怒鳴りつけた。なんとか間に入って助けたかったが勇気が出なかった。苦痛で表情が歪む母を見るだけで何も出来ない僕は情けない思いでいっぱいだった。
心底、高圧的な父に恐怖していた。当時の父は怖かった。怖いといっても子供が父の威厳にひれ伏してしまうような怖さではなく、ヒステリックな怖さである。父が怒るときはこちらが悪いことを前提に怒る。こちらの言い分を聞こうともしないで口撃と同時に脳の奥に響く拳骨を降らせる。あまりにも理不尽な暴力に何も意見が言えない。
例えば、誰だって深夜、尿意を感じれば、トイレに行くだろう。その夜も尿意を感じたので、周りに迷惑をかけないように、父に出会わないように静かにトイレに行く。ことを済ませて、トイレから出ると不幸にも、父とばったり鉢合わせる。そしてコミュニケーションのとれない父は口より先に暴力である。こちらの意見なんて聞きもしないでいきなり「いつまで起きているんだ!」と拳骨が降ってくる。
起きるも何も、生理現象なのだから、どんな動物でも生理現象がきたら当たり前の行為をするだろう。僕も動物なので当たり前のことをしただけなのにこれである。子供の僕でもわかる。
「この痛みに愛はない」
「理性などない」
感情に任せて父は子供を殴った。その事実は受け止めがたく許せない。理不尽な暴力に何も言えない僕は潜在意識の奥の奥、心の傷となって、傷の割れ目に殺意の芽が芽吹いていく。理不尽な暴力を栄養にして殺意が僕の中で育っていった。