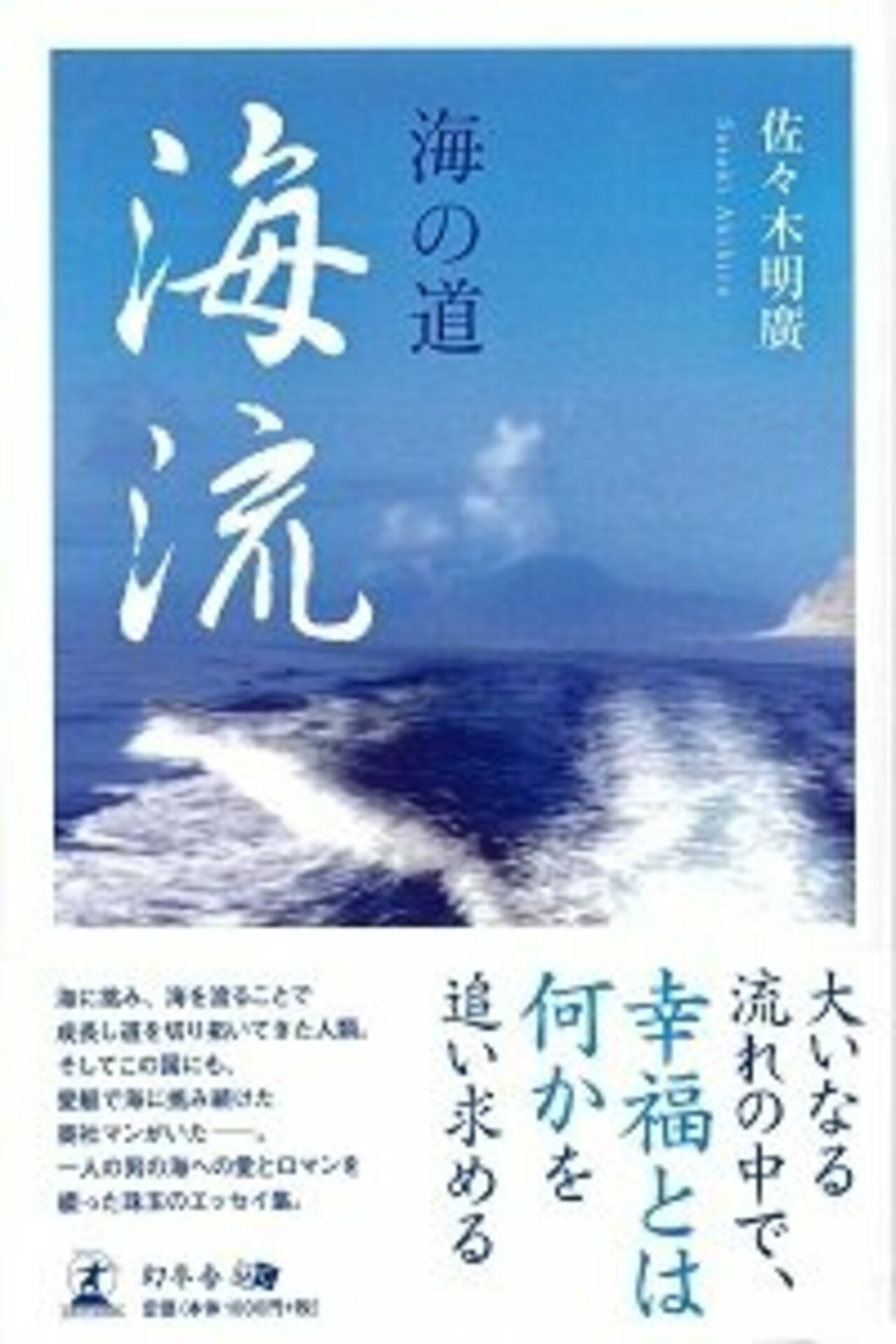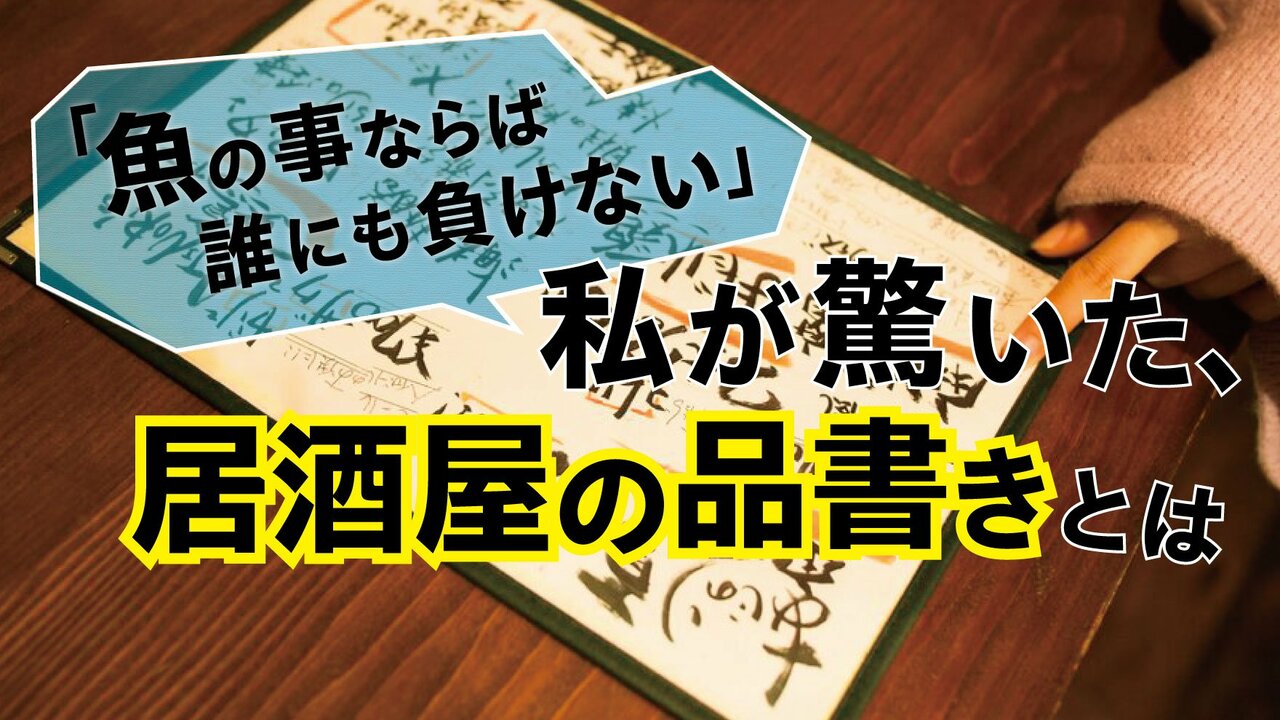第一章 北海道
二 「ウタリ」
ウタリとはアイヌ語で仲間と言う意味である。その名の居酒屋は札幌すすき野の西の入り口に近い所にあった。
一九六五年、私は大阪に本社のあった総合商社に入社後、アルペン競技で鍛えた足腰がうずき出し年末の帰省の際はまず私を育ててくれたニセコで滑ってから家に帰るのを常としていた。千歳空港から札幌に向かい、駅にスキー用具を預けてすぐに向かったのがこのウタリであった。
厳冬の北海道の夜は雪が降ると息が詰まるような静寂に包まれる。そして、しんしんと降る雪の中を歩くと寒さで靴がキュッツ・キュッツと鳴る。その靴音を久しぶりに聞きながらすすき野方面に向かうと、雪明りの中に地元の人しか知らないような古びた小屋が佇ずんでいて小屋の外壁から突き出た煙突から、降りしきる雪の中に焼き魚の煙が紫色に流れている。
吹き溜まりに閉ざされた扉を開けて店に入ると薄暗く、ほっとする温もりの中にいろりの火が赤く燃え酒肴をそそるような焼き魚の煙が立ち上っている。いろりを囲む客はただひたすら魚を突き、黙々と酒を飲んでいて誰一人として声を上げる人はいない。暗さに慣れた目を凝らすと壁には巨大なヒグマの毛皮が店の雰囲気に馴染み溶け込むように無造作にぶら下がっているのが見える。
私も空いた席に座り天井から吊り下げてある干物の中から好物の北海道の海に棲むキンキン(脂ぎった赤い高級魚)を注文して、壺から柄杓でくみ上げた酒を口に含んでいると程よく焼き上がったキンキンが大きなヘラに載って目の前にヌッと突き出されてきた。
久しぶりに脂の乗ったキンキンの味、そして銘柄はわからぬが熱燗の酒が冷えた体に滲みわたってくる頃、決まって頭に浮かぶのは私の帰郷を心待ちにしているであろう父母・兄弟の顔であり、また北海道に残っている旧友の顔の数々であった。
一つしかない窓に目をやると雪明りでぽっかりと空いたその外は依然として音もなく雪が降り続いているのが見える。この様子では明朝のニセコの山は新雪が深く積もり、久しぶりにリフト一番乗りをして未だシュプールの跡が付いていない無垢の大斜面を滑ることができるであろうと心の高まりを禁じ得なかった。全ては昔懐かしい静寂の北国の夜であり、学生時代に通ったウタリその物の姿であった。