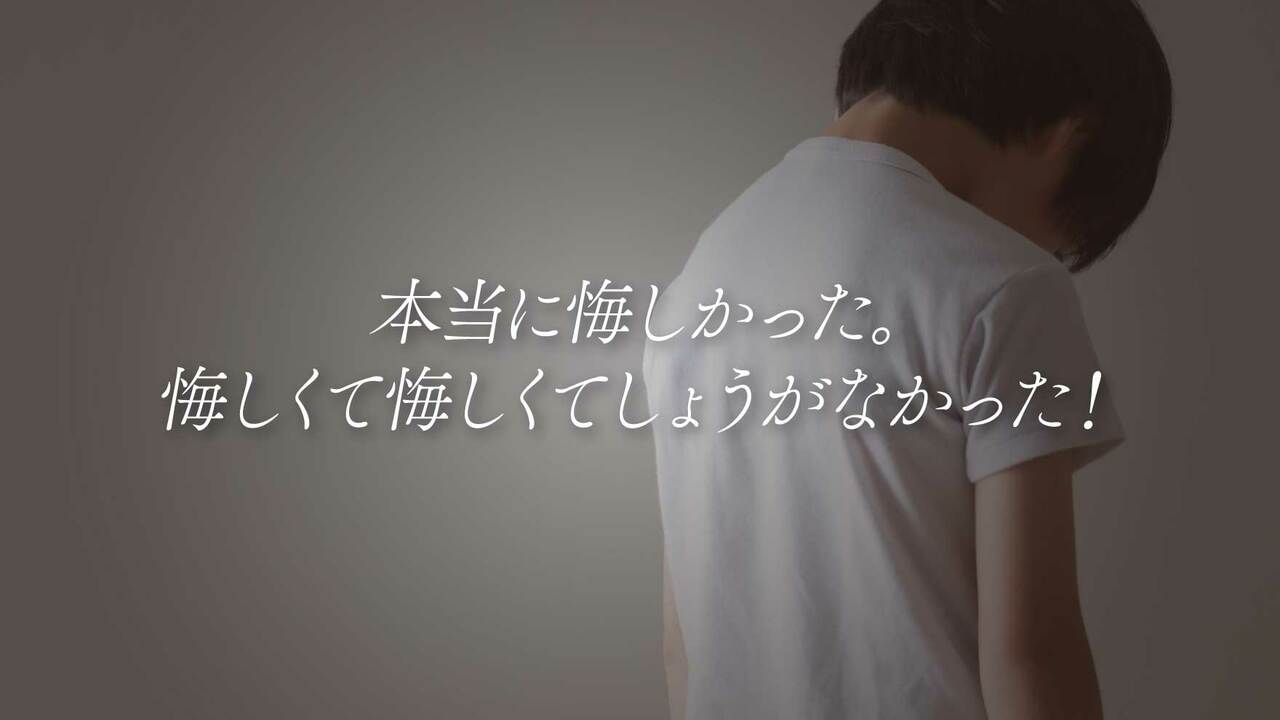それで、優等生との後日談になるが、大人になって同窓会に参加した僕は、そこであの優等生の子に会った。彼女もあの頃のことは覚えていたようで「二人で帰ったよね~」と話していたが、かねてから疑問だったので、彼女に聞いてみた。
「あの頃のAさんは、なんだか、親の期待に応えようと必死に頑張っていたように見えたよ?」
彼女はその通りと、パッと顔をきらめかせて答えた。なんでも、親の期待に応えようと小、中頑張ってきたが高校で周囲についていけなくなり、成績が落ちていったそうだ。だが彼女の顔は明るく誇らしげであった。きっと、成績が落ちたことで親の期待という呪縛から解放されたのだろう。どんな人にも悩みはあるものだと改めて思う再会だった。
当時、そんな優等生に憧れながらも授業などまともに受けない僕は、ノートの余白に落書きを書いて時間を潰していた。隣の女子が「なんで学校に来てるの?」と女子同士で会話をしてるのが聞こえたことがある。何故かといえば、理由は一つである。
周りから嫌われ勉強が出来ない僕が学校に行く理由はたった一つ。母を心配させたくないからだ。母を泣かせたくないからだ。ただ、それだけの理由で学校という戦場にランドセルという名の戦闘具を背負って毎日、家の扉を開ける。まるで神風特攻隊のように母に敬礼して学校に通っているようだった。
ただ、自慢になるが絵心はあるので落書きを書き続けていくにつれ、クオリティは高く芸術の域に達したのではと思うほど、当時の僕は落書きに命を吹き込んでいた。おかげで周りから落書きを褒められ、図工の授業だけは真面目に受けていた。
しかし、そんな僕でも、日々のストレスが溜まり、その日は本当に学校に行きたくなかった。布団に包まっても登校の時間は刻一刻と迫ってくる。焦れば焦るほど時間は早く過ぎていくもので、布団の隙間から時計をチェックする度に胃液が逆流しそうになる。そこで僕は苦肉の策を考えた。
「そうだ! 風邪を引けばいいんだ!」
…まあ、お察しの通り馬鹿である。だが、馬鹿を馬鹿にしてはいけない。時計の針はカチ…カチ…とあと数分で登校時間をさす。僕は間違った努力ならお手の物。今までにない集中力と念力で、布団に包まりながら『熱でろ~熱でろ~』と体中に走る血管に命令を出して体温を上昇させるように必死に念じた。
人間、本気の思いは神に通じるもので次第に体温が上昇して見事に平熱から微熱に昇格した。体中から勝利の汗が噴き出て爽やかな朝を迎えることが出来た。人は本気になればなんでも思いを叶えることが出来るものなのかもしれないと学んだ出来事だった。