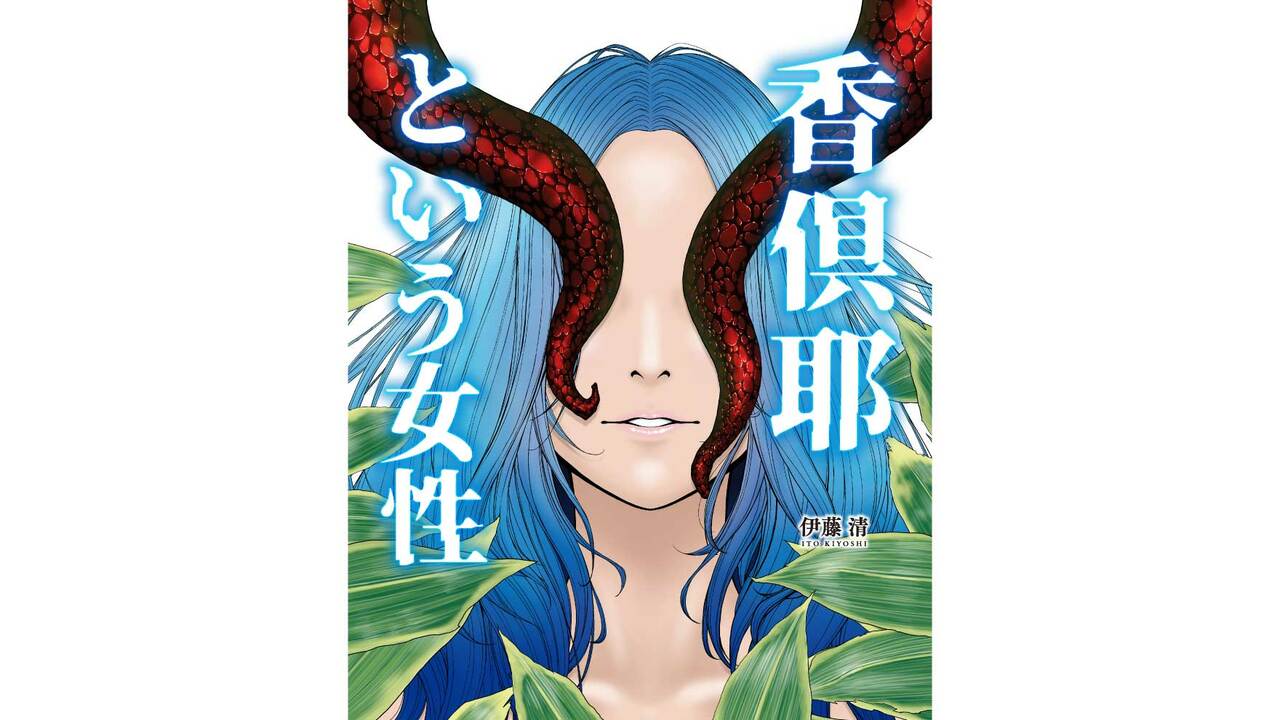第一章 夏の夜の出来事
啓一が入社した時期は日本経済の黄金期だった。
景気の好況感と国民の満足度が一致しており、一億総中流という言葉がはやったほどだ。それは世界史的にも例のない特異な時代である。
その後日本は、失われた二〇年と呼ばれる経済の低迷期が続く。景気は一時的に持ち直した時期もあるが、国民が豊かさを実感することはなかった。そしてこの間、国民の経済格差は急速に進行し、今では中流という言葉は死語に近い。
啓一の給料は入社時で手取り三〇万円を超えていた。東京都の公務員が大卒で一五万円くらいだったことを考えれば、破格の収入である。
啓一は、五三歳になると部長職でいったん退社し、系列会社の執行役員となる。そこで三年後に常務取締役となり、翌年に本社役員として同じ肩書のまま戻った。それから二年後に専務取締役となる。
啓一の会社は、役員報酬が他の大企業に比べて高い方ではないが、退職時の年俸は七〇〇〇万円を超えた。啓一はこのように、難関国立大学を出て一流企業に入社すると順調に出世して、最後は系列の二つの会社で役員を務めたのである。二人が生まれた家庭は、どちらも裕福だった。
そんな恵まれた者同士の結婚は、両家をはじめ親戚や友人たちにも祝福され、順風満帆にスタートした。だが、二人の希望は結婚生活だけにあったわけではない。あくまでも、子どもを儲もうけて幸せな家庭を築くことにあった。
最初に不妊を疑い始めたのは節子である。結婚して五年になるのに子どもができない。夫婦生活は普通にある。
にもかかわらず子どもができないのには、何か理由があるかもしれないと節子は考えた。いったん不妊を疑うと不安がどんどん募っていく。そこで一度、検査を受けてみようということになって、節子は近くの産婦人科医を訪ねた。
検査を受けてみると、節子に問題はないことが分かった。ならば啓一に問題があるかもしれないと考えて、節子は啓一にも検査を受けるように勧めた。結果は啓一にも特に問題は見つからなかった。
医師は人工授精を勧めたが、二人はそれを断った。今は二人とも後悔しているが、当時は、啓一も節子も人工授精に否定的な感情を持っていた。特に啓一は、二人とも問題がないのならそのうちできるだろうと考えた。
それに、社内では幹部候補生として育成され始めている。そのため、年々、多忙になっていく啓一は、一度検査を受けて問題がないと分かった以上、それで自分の義務を果たしたように感じていた。啓一は順調に出世するにつれて、いつしか子どものことは忘れていた。
妻の節子はずっと気にはなっていたが、夫が出世するにつれて夫婦生活も疎遠になり、子どものことは諦あきらめざるを得ないと考えるようになった。それが退職してみると、二人の気持ちにぽっかりと大きな穴が空あいていたことに気が付く。