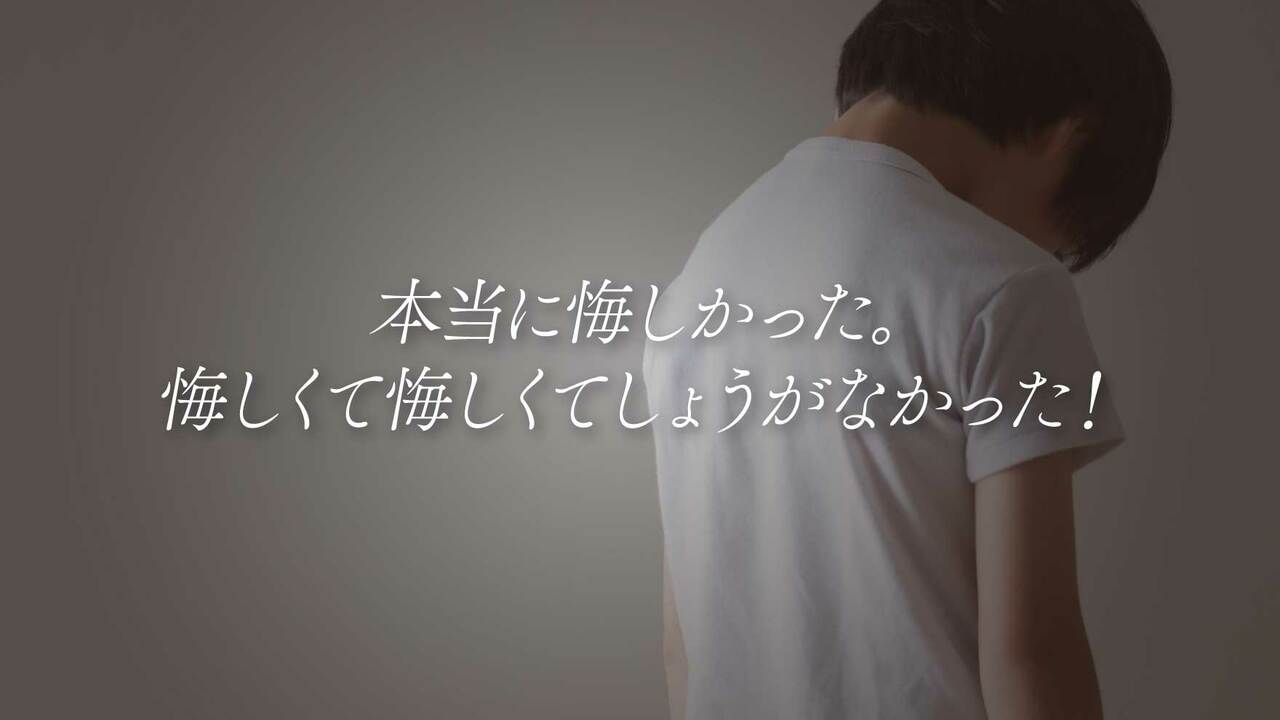第二章 父への殺意
僕を苦しめた一番の要因は家庭にあった。イジメはその派生に過ぎないと思っている。我が家は二階建ての一軒家、狭い庭には大きな杉の木が生えている。
父はめったなことがない限り二階には上がってこない。父に用があって階段を上がってくるとすぐわかる。ゆっくりと重量感のある音。まるで不機嫌な怪物が階段を這い上ってくるように、ミシ……ミシ……と木造の階段が不気味に軋む。
階段を上る音が近づくにつれ、兄弟皆の顔に緊張が走る。母は心なしかふてくされているように見える。まあ、そうだろう。これから、父の小言が始まるからだ。それ以外に父が二階に上がってくる理由がない。いっそのこと一階と二階の間にバリケードを作りたいと本気で考え何度もイメージすることを繰り返した。早く、一階に戻ってくれと胸の中で祈りながら嵐が過ぎるのをまつしかない。
それでも、父は普段は二階に上がってこないので我々兄弟はゲーム三昧。母はこちら側で僕らにゲームを買ってくれたりした。母は僕等がゲームをして仲良く遊んでいる姿を見るのが、余程嬉しかったのだろう。
初めてファミコンが我が家に来たときの衝撃たるやすさまじく、画面の中でコントローラーに合わせてマリオが走り、ジャンプし、泳ぎ、ファイヤーボールを投げた驚きは忘れない。ゲームにハマるのも無理もないことだ。しかし、遊びとはいえ、いや、遊びだからか?
人は好きなことには内に秘めた驚異的な集中力を発揮する。
あれだけ勉強が嫌いな僕がRPGをクリアするために三日間徹夜した。ゲームのためなら夜更かしなんて当たり前。勉強そっちのけでとにかく遊んだ。自分でも将来ゲーム依存から抜け出せず、そのままゲームオタクになってしまうのではと恐怖を覚えた程だ。そんな、実現しそうな未来に戦慄しながらも目の前の刺激にはあらがえない。このように、現実を直視できず、現実から目を逸らしゲームの世界の中だけで冒険していた。
学校から逃げたい。家庭は息苦しい。外も内もダメならどこに逃げればいい!
どこに自分の居場所を作ればいいのか。
人から見たら駄目人間かもしれないが僕にとってはゲームが唯一の居場所、安心出来る場所だった。しかし、何故、その集中力を勉強に生かせないのか? 自分でも呆れるほどだった。