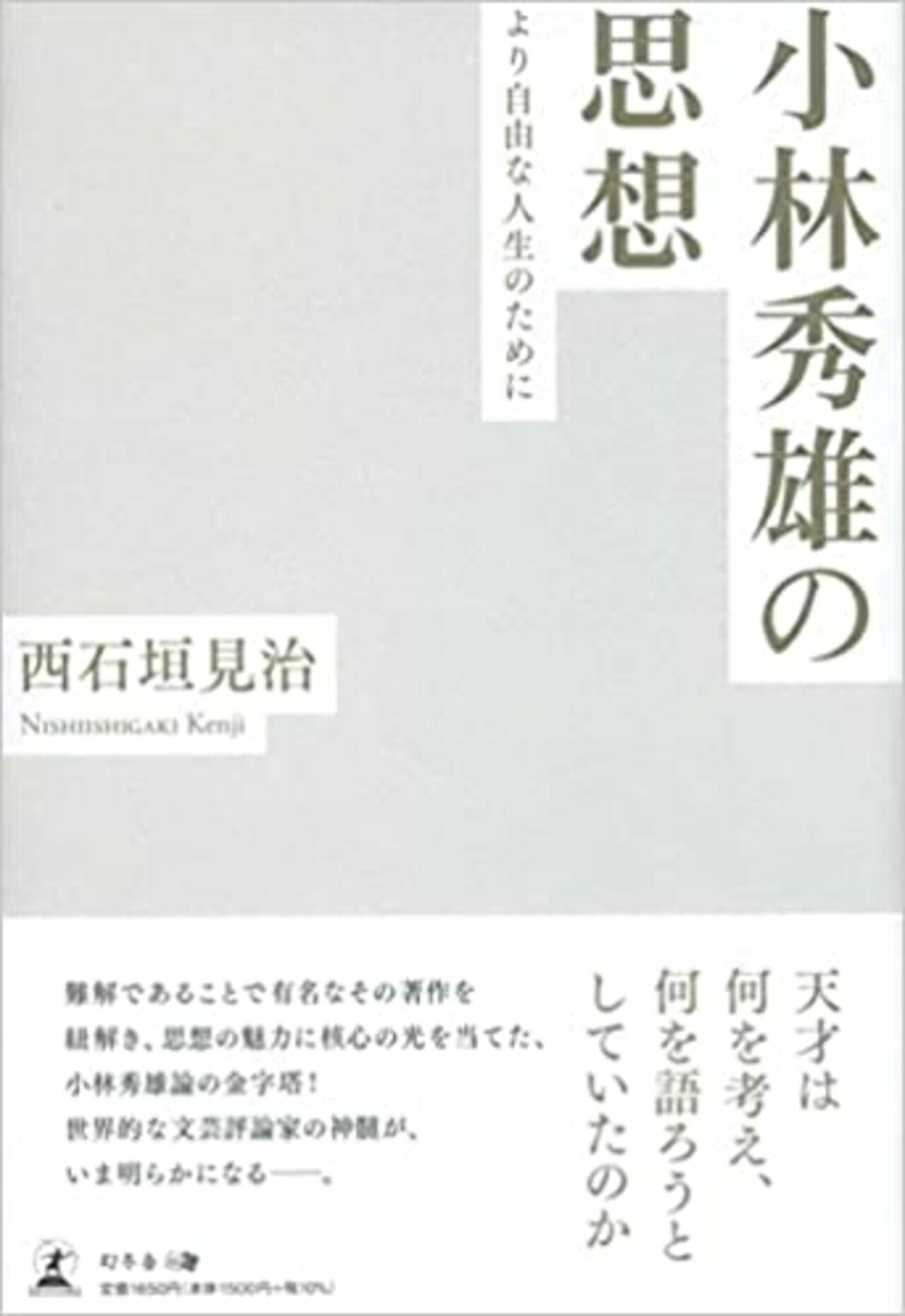“真知”への芽生えとしての「明晰なる無知」とデカルト哲学
それゆえ、「明晰なる無知」はもはや、単に明晰なだけの、不毛の、石胎の無知とはいえないのであろう。それはむしろ、“真知”へと向かう知が、芽生え、成長する胚子であり、無意識の土壌層ですでに始まりつつある芽ぐみなのである。
実際、それは、懐疑の精神を己の養いとする、それ自身が一種の目覚めた全体的認識ないし意識なのである。その自覚された自体的認識において直知されるヴィジョンそのものが、精神や自由の無限の光を湛えた、実存の限りない広がり、奥行きをはらむのである。
そのため、その照明性は、既知性への反省作用が背景に退いて、その積極的な意識性が前面に評価されると、“内観”や“観照”、“知的直観”という名前で呼ばれてきたのである。
─そこにあるのは、思惟の最前線において常に尖端的に存在してきた、知の極限の双面的在り方であって、科学や芸術、哲学、宗教すべての普遍世界に通底するのである。
そのゆえに、小林は、例えば、デカルトを論じ、その『方法叙説』から引用するなかで、やはり「明晰なる無知」の自覚に言及する。そしてそれが、デカルトが絶対に手放なさなかった“不思議な利益”でもあったという。
それというのも、それは、いわば返す刀さながらに、─同じ自覚の意識の深みから、かつ同一の根源的な光を以て─知の既成の秩序や権威に対し、批判の自由ないし自由の新しい能力をもたらすからである。
「『私が、私の審判者と望むものは、常識を学問に結びつける人達だけである。』と。彼は、廿歳で、学問は一通り身に付けて了った。ヨーロッパ最上の教師を擁する最上の学校で、学べるだけの事は、悉く学んだ、(中略)学問に励んでみたが、無駄だった、何の利益もなかった、『たった一つの利益は、学問すればする程、いよいよ自分の無智を発見した事であった』。
彼は、このたった一つの不思議な利益を、絶対に手放さない。(中略)彼は、當時の学問を疑い、至る所にその欠陥を見て迷ったのではない。根を失って悉く死んでいると判断できる自分の自由を信じたのである。(中略)学問は、抱え込んだ知識という財産の重荷で死んでいる。」(『常識について』小林秀雄全集第九巻「私の人生観」新潮社)