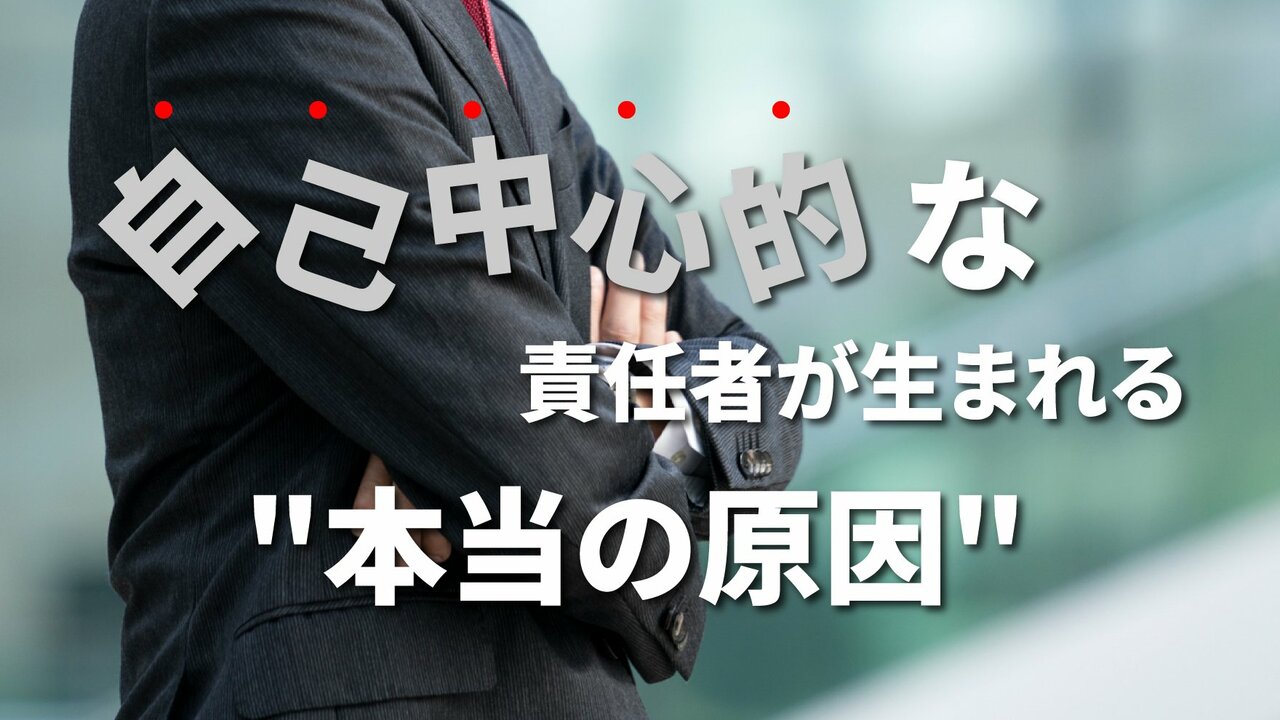【前回の記事を読む】長年の肉体労働で上がらない肩…体を回復させた現代医療に感慨
創業そして解散
ところで、老化と自分なりに判断したのに訳がある。以前、太股に痒かゆみのある十円大の痣ができて、何度かお世話になった、歩いて百数十歩の皮膚科に飛び込んだ。それが患者を安心させるだろう大きな声で、決まり文句の「どうしました」で診察を受けた。患部を素手で、指先で摩って「体質が変わったね」と塗り薬をくれた。
体質が変わるってどういうことだろう、とすぐには納得できずに、例によってそのあと二日三日考えた。政党の体質が変わったならなんとなく分かるが、一個の肉体が突然、変化する。それがたしかなのは怪我か病気しかない。病名も知らされず、先生はなんの説明のないまま塗り薬しか出してくれなかった。
ひねり出した結論は老化だった。たしかに耆老らしきはとうに超えている。遺老は何歳を言うのだろう。老翁は眼に心地よいが、老獪はいかがなものか。老がなんなのかと、とうとう頭が老害になった。とにかく老化によって、皮膚に取り付く黴への抵抗力が減っていると、耄碌の始まりを予感した。
患者に、患部にじかに手を触ふれて安心を呉れるのは整形外科の先生も同じだった。おしなべて聴診器で診察する先生よりも、理学療法士・作業療法士などの患者と濃厚接触する人のほうが、親密さのうえ、なにがしか敬う心持ちにさえなる。それでCOVID-19だが、クラスターの予防には限界があって、人情を持ち出せば避けられない理屈。少なくとも昭和はそうだった。
ところが今こうして、書きつつあるこの時、新型コロナウイルスの蔓延が人と人の距離を離そうと働いている。遮断しようとしているのは、だから反社会性の強い病になるのだろう。でなければ新しい社会、国際交流のあり方への促しだろう。国と国を切り離す現実には全く別の思いがあるのだが。
それで、ともかく手術の気配は一切なく、民間委託の市民病院で整形外科の先生が処方した薬は新薬らしかった。どうやら服用の量に上限があって、二ヶ月五十六日分をまずは日々控えめに出してくれた。なにか体内に徐々に蓄積する用法のようで、痛みが増したからとにわかに量を増やしても、効き目がすぐに現れないと言い含められた。むしろ劇薬らしくさえ聞こえる。
服用して一週間もすると痛みは明らかに和らいだが、目標にはさらに時間を要した。養生のような時間が快方に向かうのとは違っても、薬の効き目には時間だった。途中、徐々に量を増やして、三ヶ月あとにはすっかり、見かけは健康になった。見かけとは病状を評するなら、骨格の変形が元に戻る異常が、奇異がないかぎり、完治したとはいえないからだ。痛みのみが薬で和らいだだけで、骨が、骨格が戻ったわけではないのだから。完治は望むべきはなかった。