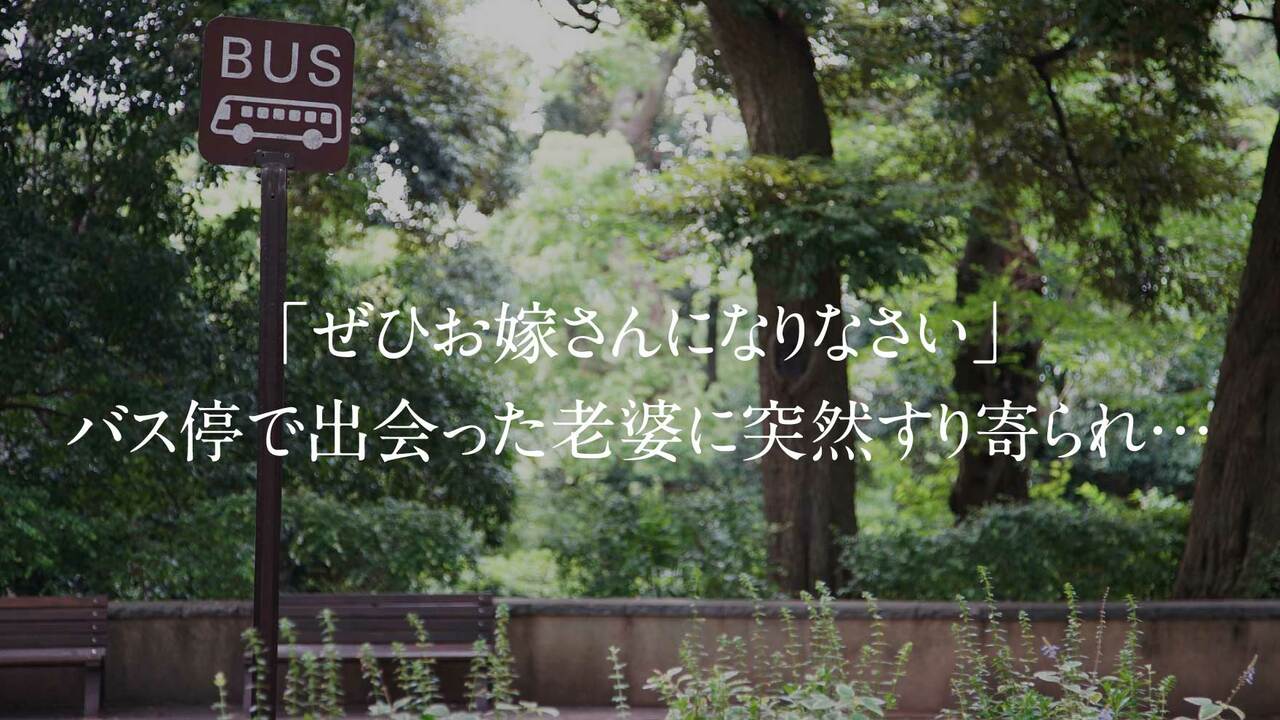黄瀬戸の平茶碗
たぶん二十六歳だったと思う。
春のある日、一人で鎌倉巡りをしたことがあった。北鎌倉の駅を降りて円覚寺に向かった。
ドウダンの柔らかい若葉が、自ら生きることを楽しんでいるように見えた。木造の古い建物の色調と生まれたばかりの若葉の色調の対比に目を見張ったり、ぼんやりと空を眺めたりしながら時間を過した。それから明月院に向かった。
鎌倉は小径も美しい街だと思った。紫陽花の季節にはまだ早かったけど、どんな花々が咲き誇るのだろうとか、不意にリルケの悲しい凋落をうたった「ばら色のあじさい」の詩が浮かび、妙に切なくなったことを記憶している。
鎌倉駅に向かったのは、午後の四時近くになっていたと思う。駅の周辺をブラブラしていると、一軒の骨董店が目に留まった。高価な焼き物が置いてあるのは、しっとりとした引き戸の店構えでわかった。老舗が持つある種の威厳を感じさせてくれる骨董店に、ジーパンとTシャツ姿の身元不明な女の子が、のこのこ入っていけるような店でないことはわかっていた。
でもここが私の性格の何とも言えない所で、入ってしまうのだ。好奇心が勝ってしまうのだから。ガラガラと引き戸を開けると、店の中には人の良さそうな四十代ぐらいの店主がいらして、笑顔で迎えてくださった。
「焼き物を見せて頂けますか」
「いいですよ。ご旅行ですか」
たぶんそんな会話だったと記憶しているのだが、私はしめたと思った。そしてなんと、
「たった今、小林先生が帰られたばかりなんですよ。この茶碗を褒めてくださったんです」
「え! 小林先生って、あの小林秀雄ですか?」
「そうです。散歩の途中に時々お見えになるんですよ」
私の心臓は、引き戸を開ける時よりも高鳴っていた。私が座っている畳に、たった今まで小林秀雄が腰掛けていたのかと思うと、恐れ多くて興奮した。その抹茶茶碗は、黄瀬戸の平茶碗で、とろりとした質感のある深い黄土色の形の良い茶碗だった。
あの頃生意気にも、私は小林秀雄を読んでいた。「評論の神様」と呼ばれた人の何がわかるというのか。何もわかってはいない。しかし、文章の間から波動のように伝わって来るものがあり、私を引き付けていた。
また小林秀雄自身が『読書について』の中で、いわば内部のごとき感覚に頼るほかないと語っているので、あながち間違っていないのかもしれない。特に「おっかさんと蛍」の話は大好きである。
この体験は、ある種の神秘体験のような気がしてならない。それから、ボードレールやランボーの詩を読むようになったのも、小林秀雄の影響だった。
私はゆうに、一時間はそのお店にいたと思う。凄いなぁと茶碗ばかり眺め、お茶を三杯もご馳走になったのだから、まったく図々しい人間である。小林秀雄が飲んだ同じお茶を頂いていると思うと、格別な味がした。
店主が熱心に教えてくださった話は、すっかり忘れてしまったが、あの茶碗だけは映像のように浮かんでくることがある。形は、京都で見た珠光青磁のようでもあり、釉調は李調ものの名品(喜左衛門)にとても似ていた。我が青春に出会った思い出の抹茶茶碗である。