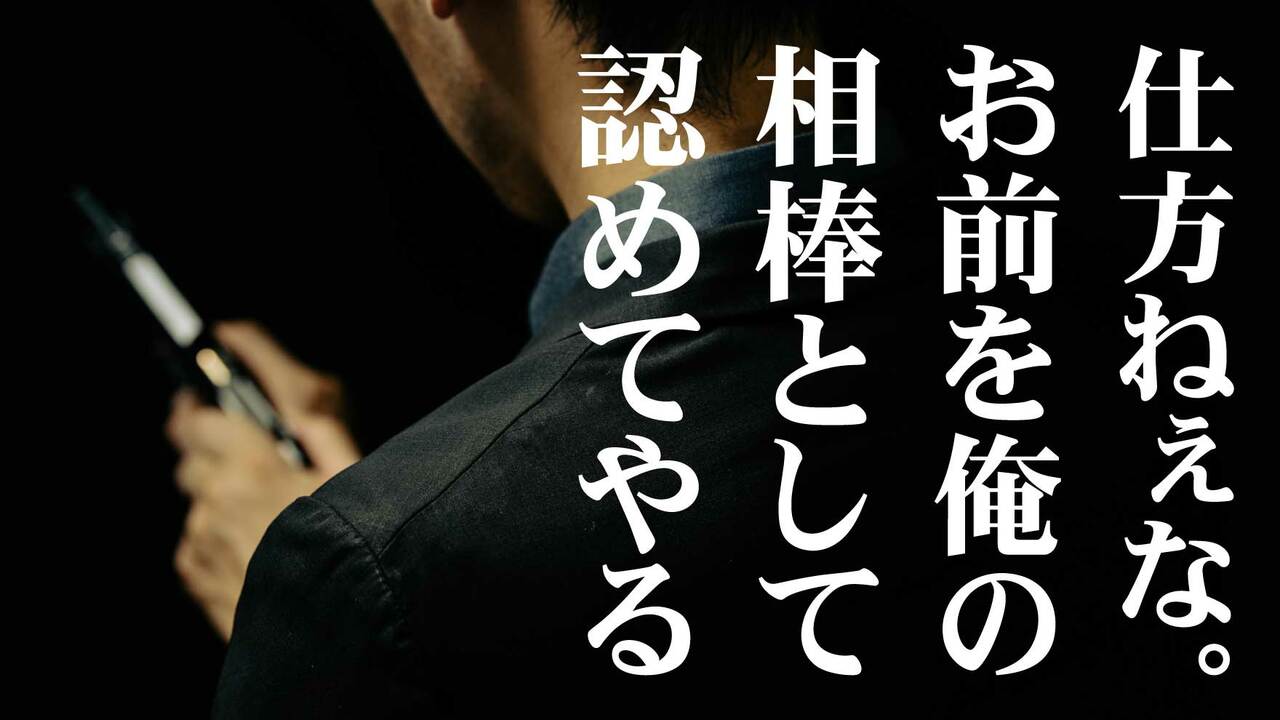突然恭子は森の闇の方へと振り返った。同時に頬を、闇から放たれた黒い固まりが掠めた。それは背後の官舎の外壁にぶつかり地面に落ちた。落下物の先端で、針が光る。
闇と対峙し、恭子はその漆黒の闇を睨み付けた。
「……ほう、よく気づいたな……」
その声は、地の底から響いて来るようだった。
声は、何処から放たれているのか。音の反響を利用し、声の主は音を発したようだった。
「我が国のサイレンサーは優秀。俺も気配を消す事には自信があったのだがな……」
恭子は、闇から視線を外さない。そこに、人の気配が感じられるからだ。
気配を絶つ事に長けた恭子はまた、気配を読む事にも長けていた。
自らの気配を絶つと、周りの存在に同化出来る。
木々も。
昆虫も。
生きるモノ全ての気配を感じ取り、空中を浮遊する羽虫の動きまで捕らえる事が、恭子には出来ていた。
草むらに潜む人間など、目で見るよりも大きな存在として捉える事が可能だ。
恭子の手には、いつの間にかナイフが握られていた。
刃先が、月光を反射し、鈍く光る。
暗闇から、草を踏み鳴らし、影が現れた。
「今のは麻酔弾だ。安心しろ。お前を殺す事が目的ではない」
月明かりの下に、その影は姿を現した。
恭子より小柄。酷くがに股で、暗視ゴーグルに覆面、迷彩服の男は、ガマガエルの印象を与えた。
「モノは相談だが、お前、我が国の諜報員として働く気は無いか。厚遇するぞ」
流暢な日本語を喋り、外見で区別は付かないが、国外の諜報員の者か。
「……いきなり発砲しておいて、よく言う……」
「俺は相手を説得するとかが、苦手でなぁ……」
ヒッヒッヒッと笑う。