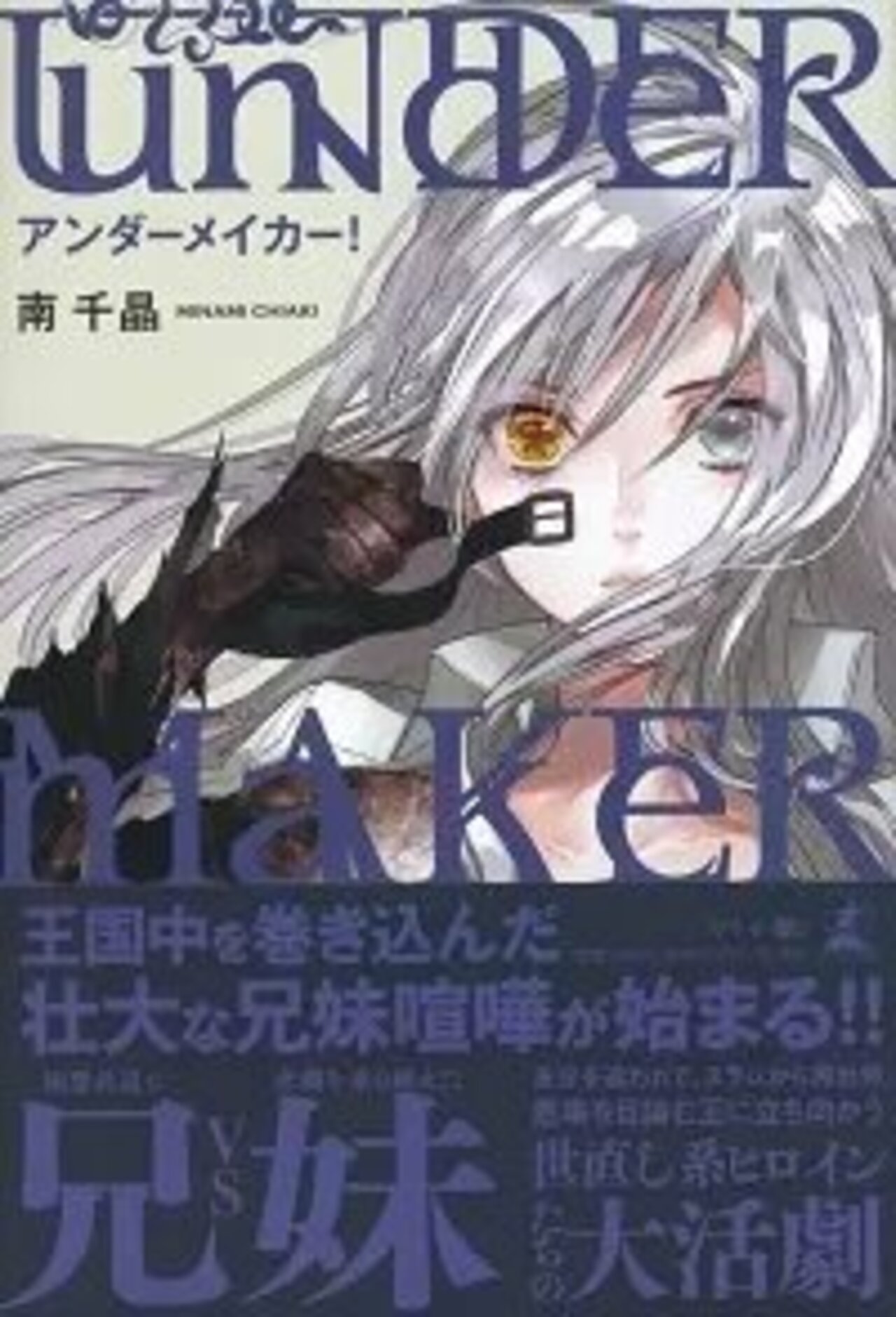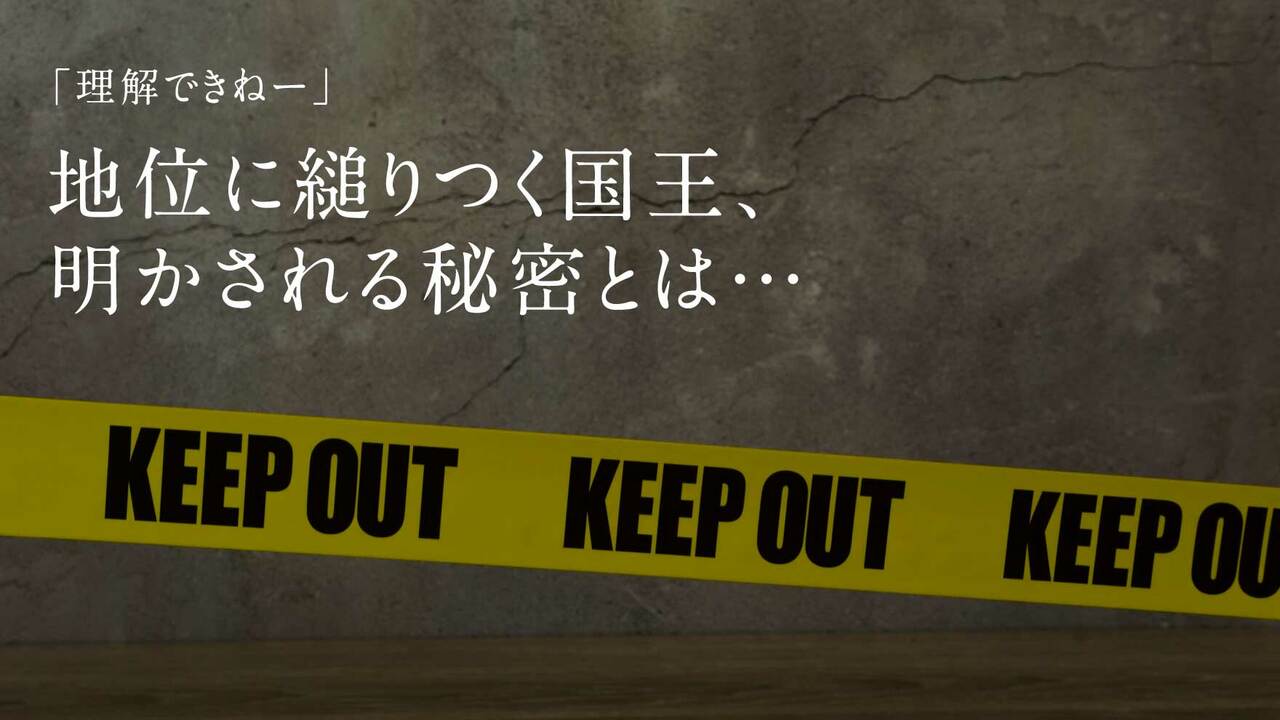「なんで貴族の俺様が倉庫整理なんざしなきゃいけねーんだよ! 腹も減ったし何か食わせろ!」
スープを全部飲み終えた頃に、事務所のドアが開いてやかましい声が届く。
「うるせーな。もっと静かに入ってこれねーのかよ浩輔」
歳にして彼女とそう変わらないだろう青年だ。浩輔と呼ばれた彼は、身体の至る所に埃がまとわりついており、それを払う仕草をしながらも口だけは達者だった。
「呼び捨てにすんな、この男女! 俺は貴族世界の人間だぞ! もっと敬え!」
「元、だろ。第一、てめーを拾ってここに置いてやってるだけでも感謝しろっつーんだ。それとも、俺様のやり方が気に喰わねーならスラム世界の中でも極悪な場所に捨ててやってもいいんだぜ」
「ふ、ふん。俺がこんなスラム世界に落ちたのは俺のせいじゃねーし?」
「じーさんが死んだのが悪いって言うのか?」
そこで、浩輔の眼の色が変わった。つかつかと彼女の座る机に一直線に向かい、両腕で殴るかのように机を大きな音で叩いた。
「机を殴んじゃねーよ。机が減るだろーが」
「じっちゃんの事を悪く言うんじゃねぇ。じっちゃんだけは俺の味方だったんだ」
「……へぇ? どんな風にだよ?」
「親族は皆、己の欲望とじっちゃんの遺産にしか興味がなかった。けど、その遺産の全てを俺に譲るっつーじっちゃんの遺言を知った瞬間、あいつらは遺書は無効だと言い出して屋敷から俺を無一文で捨てた」
「ま、貴族世界の人間なんてそんなもんだろ」
「けどじっちゃんは! それを見通して、俺宛に書いた手紙を残してくれてた!」
「それが厄介事の始まりだっつーんだ。なんで死んだじじいの残り物を俺様に押しつけるんだよ」
「俺だって好き好んでこんなとこに来たワケじゃねぇっつーの! 俺は貴族なんだからな!」
暫し睨み合いが続くも、所長である彼女は挑発的な笑みを浮かべている。
「お前は、二言目には“俺は貴族、俺様は貴族”、だな」
「本当の事だ!」
「じゃぁ今のてめーはなんだよ?」
ぐ、と思わず声を殺すしかなかったのだろう。浩輔は悔しそうな表情をしてから、反論に出た。
「俺はぜってー貴族世界に戻るんだ! 俺を捨てた親族連中を制裁する為にな!」
「はいはい、口だけでは何とでも言えるさ。実力が伴ってないんじゃ、ただの負け犬の遠吠えだぜ」
「俺はじっちゃんを信じてここに来たんだ! でなきゃ、誰がこんな訳の分からねーとこに来るかよ!」
「相変わらず、最期の手紙を肌身離さず持ち歩いてんのか?」
「……悪いかよ。俺が信じられるのは、この手紙だけなんだからよ」
そこで、所長である彼女は初めて溜息をついた。
「はぁ、名刺なんか渡すんじゃなかったぜ……」
そう、じいさんが浩輔宛に書いた最期の手紙には、“困った事があったらここを訪ねなさい”という一文と、ここ葬儀屋の名刺が入っていたのである。つまり、名刺が入っているという事は、彼女は浩輔の祖父に会った事があるという事でもある。しかし浩輔はそこまで頭が回らないようだが。