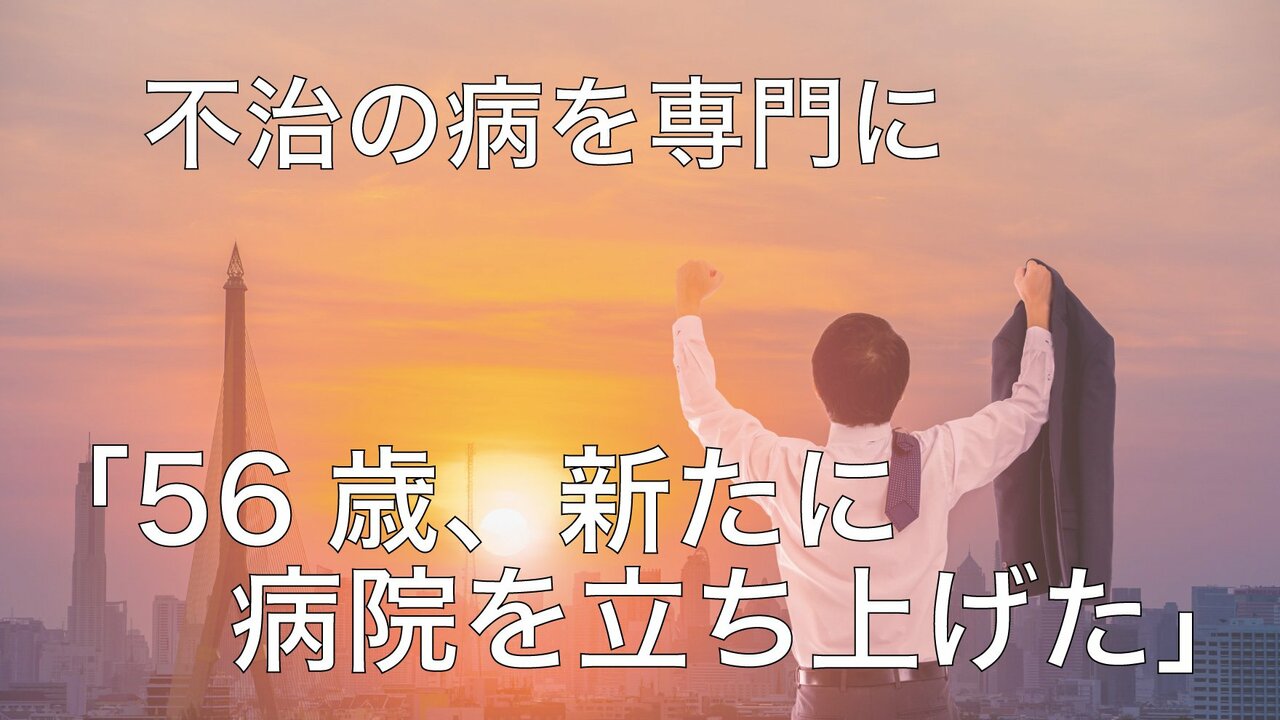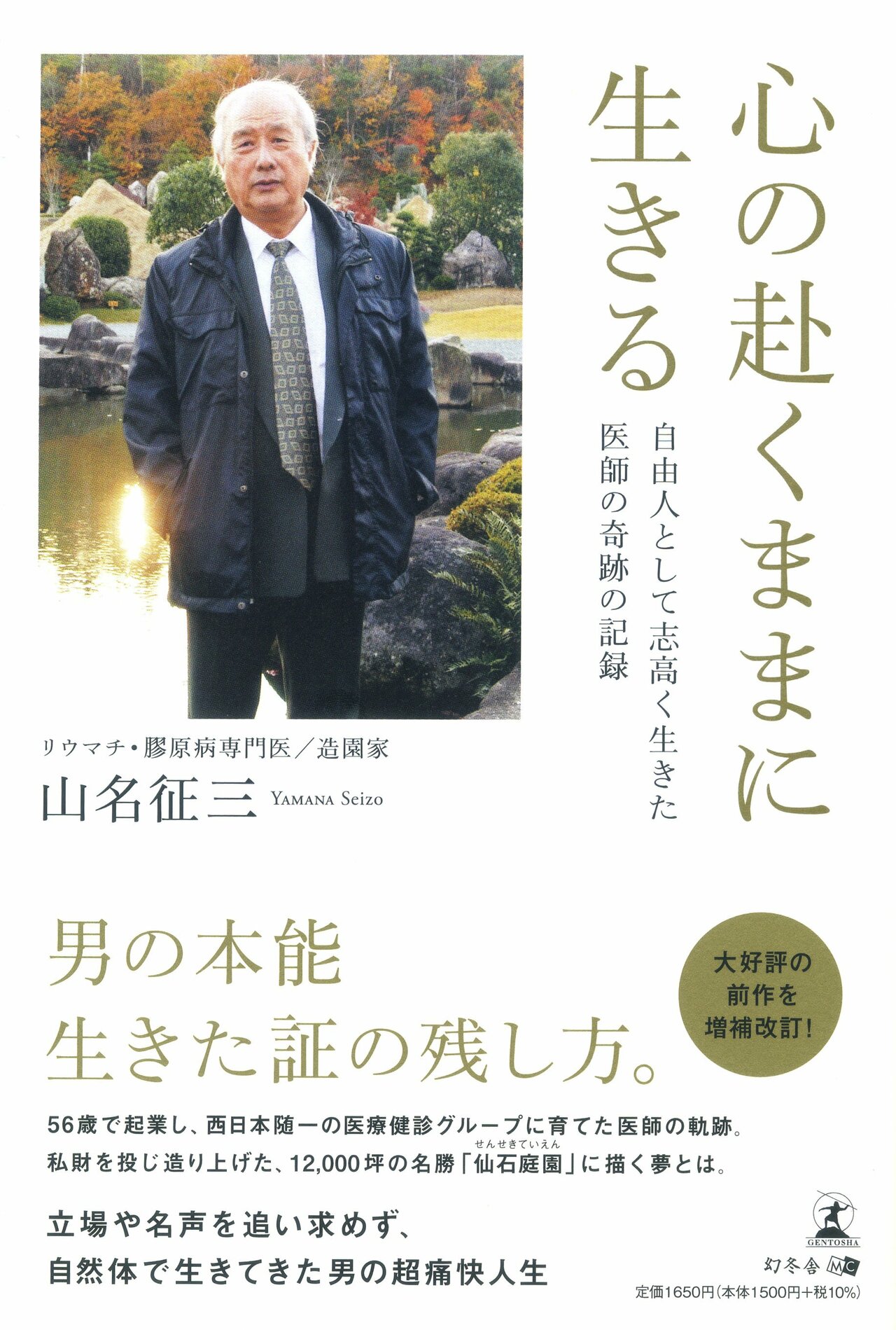大藤教授が学部長選挙に出る
大学では大藤教授は病院長の次の学部長ポジションを狙っていた。先生は権勢欲の極めて強い方で、大学においても、学会においても常に立場を追い続けていた。
学部長選挙の相手は基礎系の佐藤二郎教授であった。この人は野人と言えば聞こえはいいが、いろいろな噂の付きまとう人であった。しかし、選挙となるとめっぽう強い。当時の学部長の選挙は教授だけでなく、基礎系の職員も一票を持っていた。佐藤先生は彼らとマージャンをしたり、飲んだりすることで彼らの心を掴んでおり、職員間に太いパイプを持っていた。
大藤先生は選挙参謀に太田善介助教授を当てた。佐藤二郎教授から見れば太田君には次がある、即ち、教授選がある、そこを脅せば動けなくなることを良く知っていた。案の定、太田先生は動けず動かずであった。
大藤先生はいつもの細い目を真ん丸にして、眼はおびえていた。太田君が動いてくれない。大藤先生にとって落選など思いも及ばない事であった。飛び級で一中、六高と来た人で、私共の理解を超えた何かがあったのかもしれない。
ある時、私が大藤先生に呼ばれた。「山名君、今日から君が選挙参謀でやってくれ」とのことであった。私は教室内において卒業年次が上から5番目の序列である。教授選で5番とびならいざ知らず、太田先生には大変失礼な依頼であった。しかし、私は「はい、わかりました」と答え、翌日より教授室回りを始めた。
当時の教授連も20~30年前より腰は低くなっていたがいまだ気位は高く、私のような若造が選挙ごとで教授室を訪ね歩くこと自体、こころよしとしない雰囲気があった。
私はこの選挙に勝っていただくことが大藤先生に対する最後のご奉公とばかり連日5~6人の教授連にお会いして、大藤教授の支持をお願いした。選挙をすると人がわかるというが、会って一言二言で敵か味方かすぐ分かった。敵だとわかった時には、私の感触では大藤教授が70〜80%の確率で勝つと感じていますという言葉を残して部屋をあとにした。
結果は、大藤教授の勝利に終わった。私のように失うもののない者は強い。その頃すでに大学を去る気持ちを固めていた者にとって怖いものは何もなかった。
選挙の後、大学を去る気持ちは決定的となり、いつ大藤教授にそのことを切りだすかであった。昭和54年(1979年)の暮れ、辞意を伝え大藤教授は無言で受理してくれた。先生は私の固い辞意をすでに知っていたのである。
辞表を提出したとき、私は細胞性免疫班のトップであった。私の下で働くようになった若いDrs.には申し訳ない気持ちはあった。早く私の気持ちを周囲に伝えておけば彼らも別の道を取っていたかもしれない。しかし、その時の私の気持ちは矢野啓介、西谷浩次という若手を指導できる後輩が育っており、私が教室を離れても何の問題もないと確信していた。
大学を円満に去る道筋がつき、子供の頃からの夢の実現へ一歩踏み出せたとの想いから私の心は躍っていた。