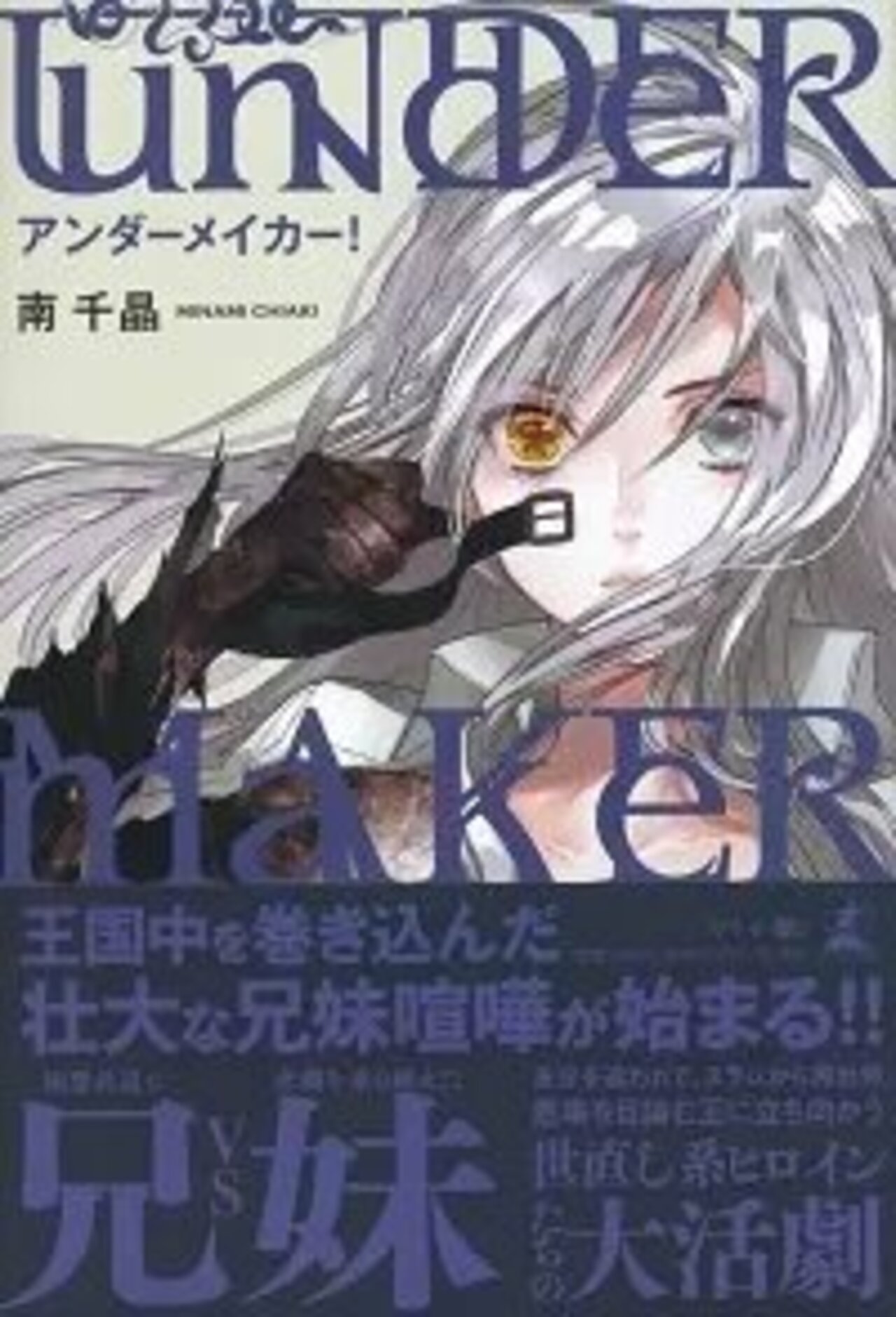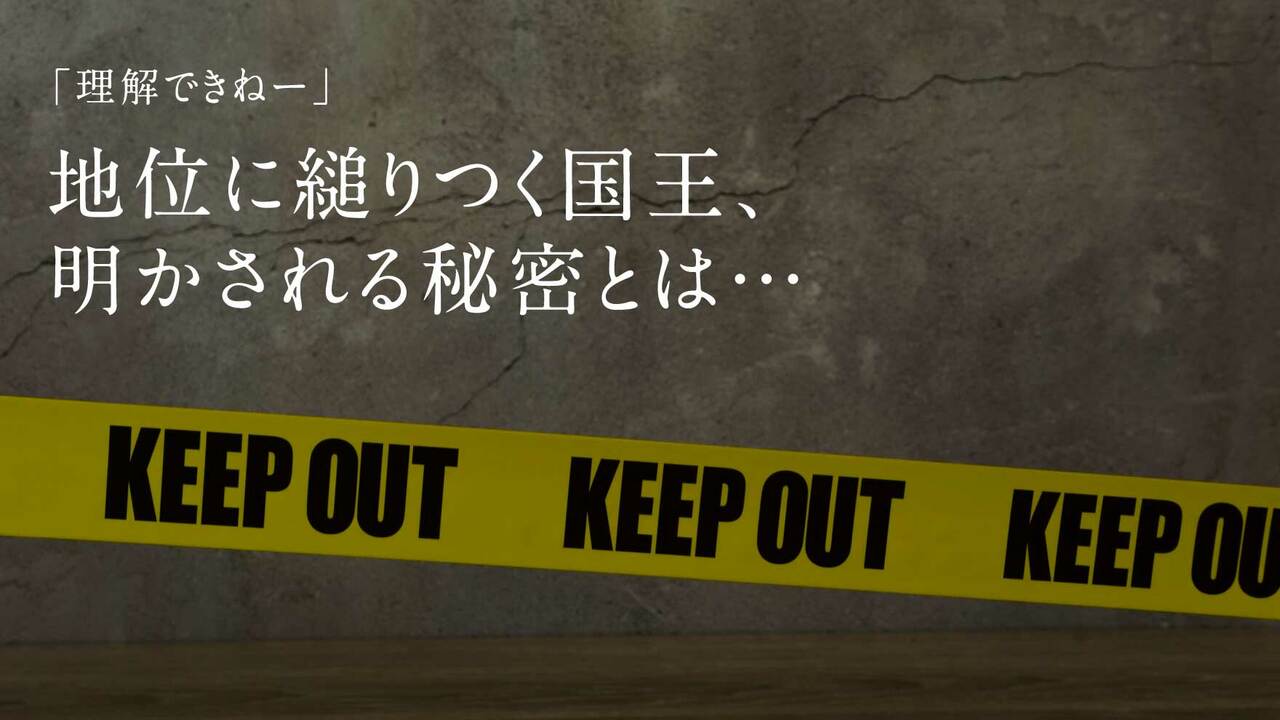葬儀屋の居候
あれは満月の晩の事だった。この目に映るのは業火に燃え盛る王宮の炎と、逃げ惑う使用人達の姿。この炎は一体どこから、出火原因は何なのか。まだ当時十歳だった私に分かる筈もなかった。
「反乱だ!」
「反乱分子がとうとう立ち上がってしまった!」
―反乱?
正直、意味が分からなかったのを覚えている。今朝までは普通に過ごしていた穏やかな日々の温もりはもうそこにはなく、あるのは殺戮と狂乱だけだった。
「ッ、お嬢様、こちらにおいででしたか! 早くお逃げください!!」
見慣れた執事が駆け寄ってくる。
「……父さんと母さんは?」
「殺されたという報告は上がってきておりません。まだご存命かと」
そして女郎の格好をした美しい女性の叫び声が聞こえてくる。
「栗栖! こっちはもうアカンわ! とてもやないけどお嬢に見せられるモンやない!」
次々と聞こえてくる断末魔の叫び。だが、その声は薄いガラスを隔てた向こう側から聞こえてくるようで現実味がなかった。中身のない物語を読まされている気分に似ていた。とにかく、その時の私は空っぽだった。その姿を見るまでは。
「……お兄ちゃん。何、してるの?」
業火の向こう側にいる兄と目が合った。その片手には父親の愛用していた刀が握られており、刃の部分は真っ赤に染まっていて、生々しい血がその先端から落ちゆくのを見た。そして、まだ高校生だった男は笑う。次はお前の番だ、とでも言うかのように。
"何者にも平等な国などいらない、これからこの国は変わる。俺を殺さない限り"
燃え盛る炎の向こうで、そう、聞こえた。
「お嬢様、御無礼を承知で失礼致します……!!」
栗栖に抱きかかえられて兄の姿が見えなくなっていく。
「ねぇ、なんで……?」
今朝、笑ってたじゃない。お前の方がおかずが多いって、取り合いっこしたじゃない。その様子にお母さんが怒ったじゃない。お父さんはそれを見てまた笑ってたじゃない。
「国王が御隠れになっている場所が分かりました。そこにお嬢様をお連れ致します」
栗栖の足は速かった。次々と燃え広がる炎よりも速かった。
「殺女、こちらで合っているのですか?」
ただでさえ迷宮のように入り組んだ王宮内を、獣耳の女郎が誘導する。
「間違いあらへん。うちの耳は100メートル先の僅かな音でさえ聞き取れるんや」
まだ火の手が及んでいない廊下を走り抜け、私は何を思っていただろうか。ただ抱きかかえられたまま―私の意志とは関係なしに物語が創られていく。
上空は暗い闇、そして燃え盛る赤い色と緑の庭。いつの間にか庭先に連れてこられていたが、それでもまだ走る。
「庭は燃え移るのが早いと思っていましたが、まだ被害は少ないようですね」
「もうちょっと走るで。庭先の別館や」
庭師による手入れの施された広大な庭を突っ切り、確かな目的地に向かっていく。
……そこに父さんがいるから何だっていうのだろう。これは、この光景は本当にお兄ちゃんの仕業なの? 何が目的なの? 私も殺される?
業火の中で笑っていたあの顔を思い出す。正気じゃない。きっと何かに取り憑かれているんだ。
―そう思いたかった。