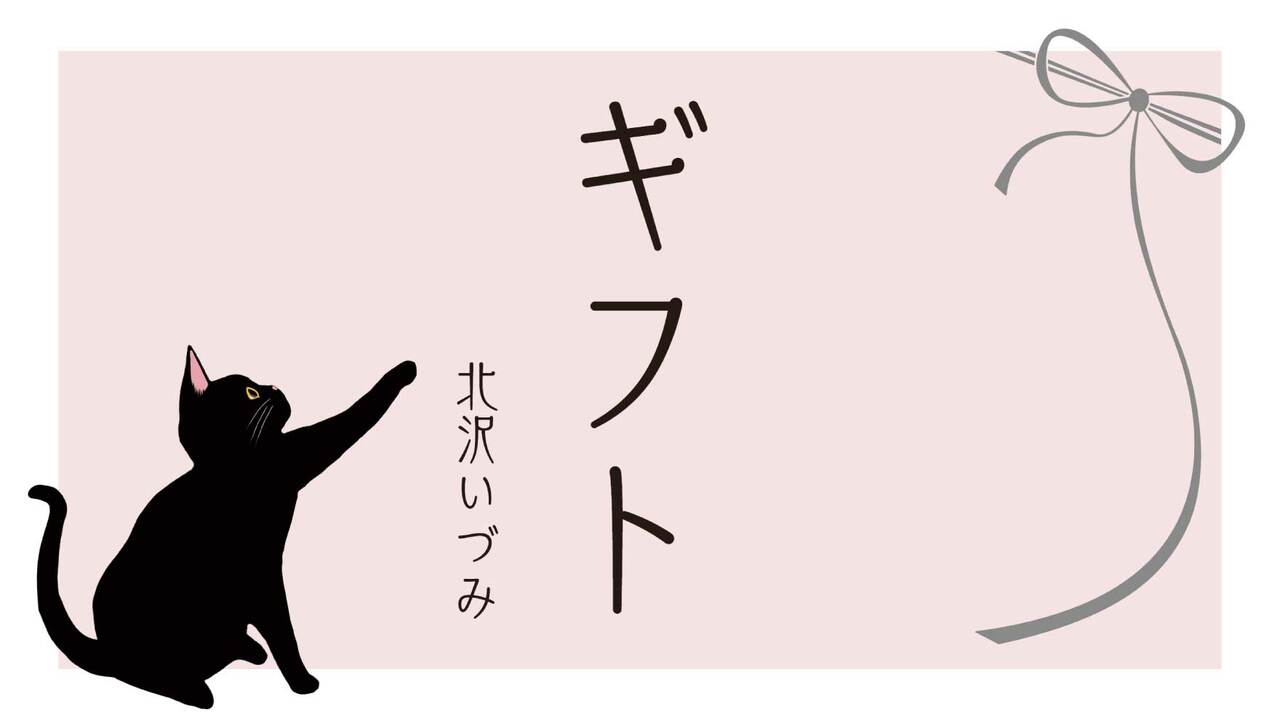【前回の記事を読む】「1分前に勇気を出していれば、彼の前には今ごろ私が…」
明日の私と私の明日
里香は、なぜ男の子の事を尋ねるのか、とは聞かなった。恐らく茶封筒を自分に届けに来た時点で、事の成り行きを知っているのだ、と佳奈は解釈した。
「さっき、あの男の子が道で白杖を胸の前で持ち上げて動かなくなったの」
里香はゆっくりと話し始めた。
「はくじょう?」
「そう、視覚障害者用の白い杖ね。白杖を空に突き上げるように持っているのは、困っています、助けてくださいっていう合図、サインなのよ」
佳奈は驚いた。そういう情報も知らなかったし、なぜこの女性は知っているんだろう。
「どうして片山さんはその事を……」
と言いかけて、何だか相手の事を詮索しているみたいでやめた。
「里香でいいのよ。実は私の一番下の妹も、目が見えないの」
そう言って微笑んで里香は窓の外を見た。その憂いを帯びた微笑みは物悲しく、本当は言いたくなかったのではないかと思うと、佳奈の心臓が大きくトクンと脈打って心拍数が乱れた。
「障害を持った方々の、色んな事がまだまだ知られていないの。世の中の人が、もう少しだけ関心を持ってくれるだけで、大きく変わるんだけどね。人が生きるという事と、生きてゆくという事の違いに」
細い声でそう言うと、里香は髪を耳に掛けて視線を落とした。佳奈の呼吸が、また乱れた。目の見えない妹さんを、ずっと傍でサポートしてきたんだと、その言葉で十分伝わる。人が生きる難しさ、生きてゆくという現実の大変さ。不自由なく過ごしてきた佳奈には、俯瞰した事のない大きなテーマだった。
同時に、この女性の判断と行動の早さの理由も理解できた。
「さっきの彼、神山君って言うんだけど、いつもはバス通学みたい。でも雨の日はバスって凄く遅延するでしょ? だから雨の日は電車を使うそうなの」
里香はそう言って、佳奈を見た。
「そ、そうなんですか」
自分が彼に好意を持った事を悟られそうで、佳奈は素っ気なく言うと、メールが届いたふりをして携帯を見た。里香が、更に佳奈を驚かせる。
「実はね、神山君と妹が同じ盲学校なの」
「え!?」
佳奈が目を丸くする。
「世間は狭いってホントね。これもご縁かしら」
と、里香が嬉しそうに言った。