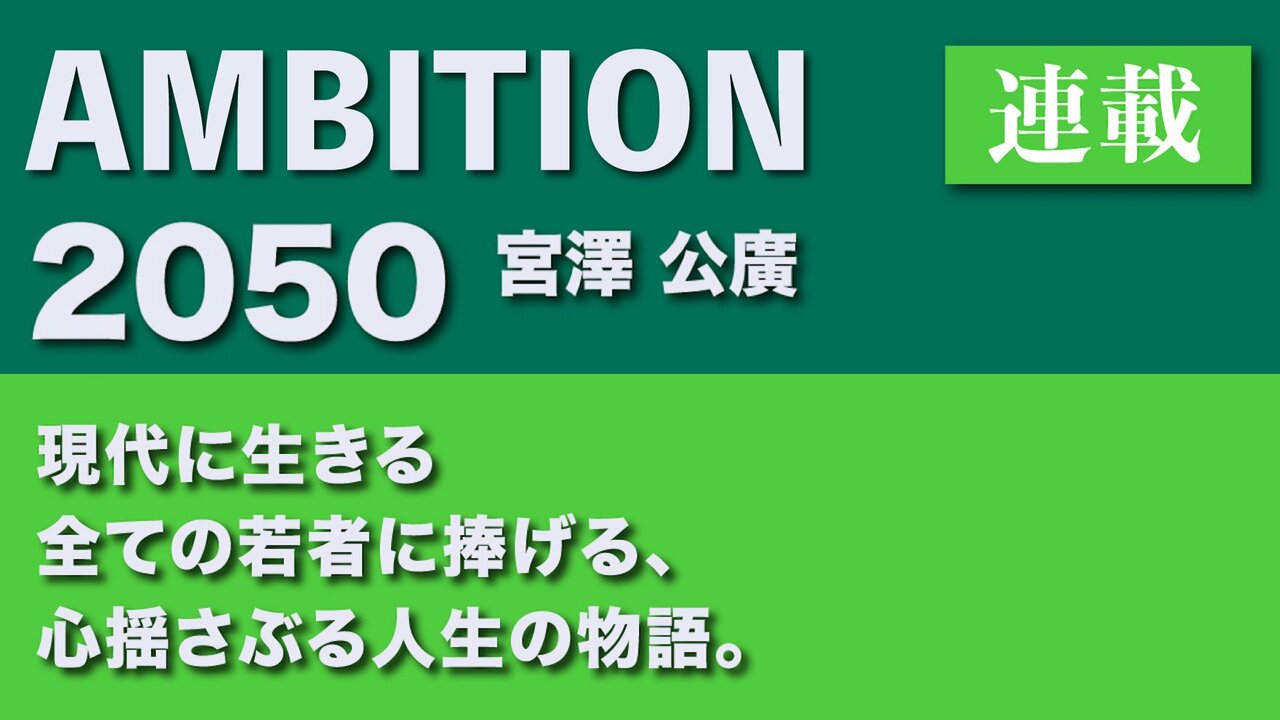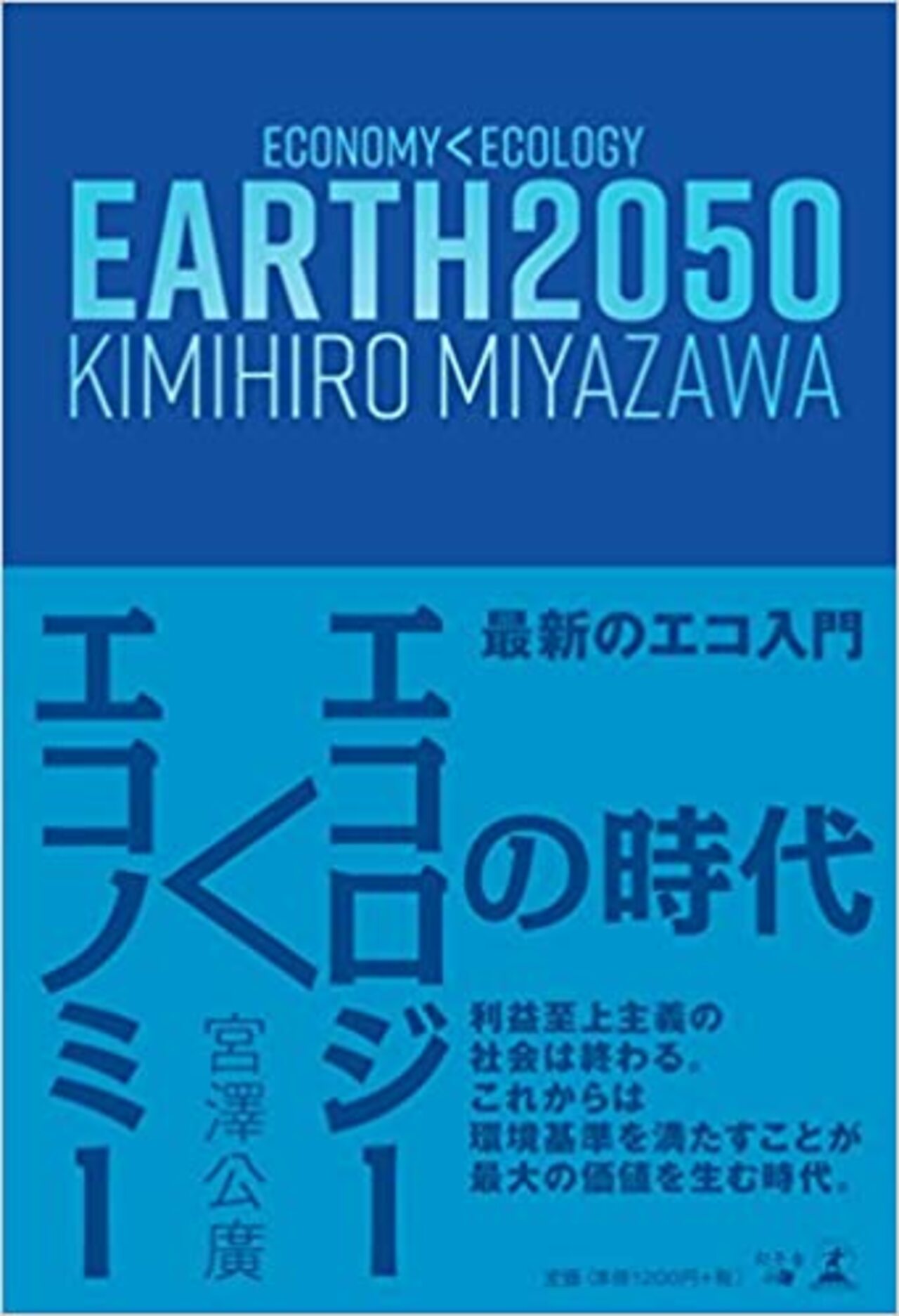第二章 奔走
【3】
目の前に出された緑茶はすっかり冷めている。宮神は茶碗を片手に持ち、緊張で乾いた喉を潤した。事務室に通された宮神は、応接室で銀髪の男性と向き合っていた。
男性は福豆食品の社長で、福島と名乗った。表情は憔悴しきっており、言葉にも力がない。ここ数日で、一気に消耗したのだろう。
福島の話では、キンキマート経由でクレームがあってから、不眠不休で原因を調査しているものの、未だに解決に至らないという。もしかすると一過性のものかと思い、万全の態勢で納豆を製造しても、やはり粘りのないものになってしまうそうだ。
「できる限り手は打ちました。もう手詰まりです」
「キンキマートだけではなく、ほかのスーパーからも返品がきていますか?」
「もちろんです。すべての取引先に連絡をして、自主回収しました。お客様があってこそやからね」
他社はまだこの一件を嗅ぎつけていないようなので、事の顚末を記事にすれば、スクープにはなる。しかし、それでいいのだろうか。記者としては失格かもしれないが、誠実に商売をしている地元企業をサポートすることこそ、人の道理ではないのか。宮神は葛藤した。
「五日後までにちゃんとした納豆をお得意さんに納品できなければ、うちはおしまいや」
福島はがっくりと肩を落とした。やつれた顔を見ているうちに、どうにか助けになりたいという気持ちに傾いていった。
「私の知り合いに、GOES(国際環境衛生協議会)の会長がいます。何かいいアイデアがないか、相談してみましょう」
「本当ですか」
「ええ。電話を借りますよ」
宮神は鞄からメモ帳を取り出し、GOESに連絡した。幸いにも社長の広澤はすぐにつかまった。事情を話すと、社員を伴ってすぐに神戸へ出向くと言い、工場内をそのままにしておいてほしいと念を押された。
広澤とその片腕である北原が到着したのは、夕方になってからだった。福島とあいさつを交わした広澤は、差し出された糸を引かない納豆を開け、じっくりと観察した。
「間違いない。これはファージ現象ですな」
広澤がおごそかな口調でそう結論づけると、福島の顔がさらに青ざめた。