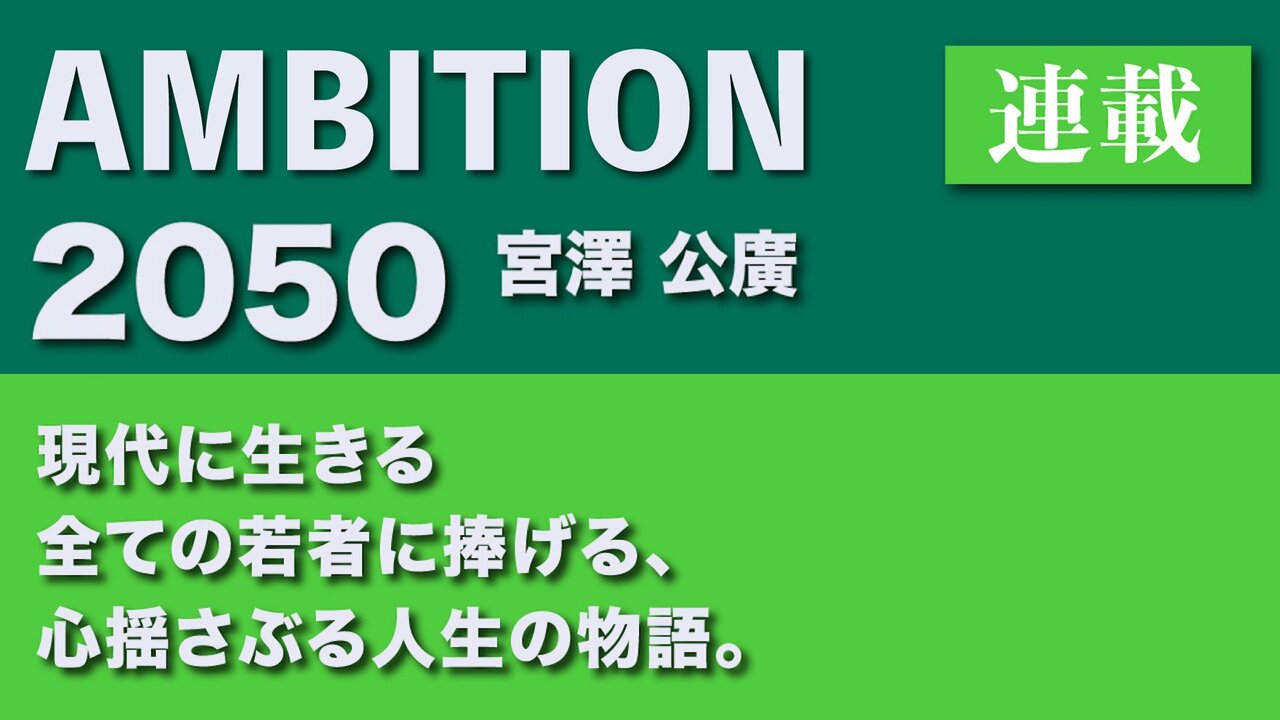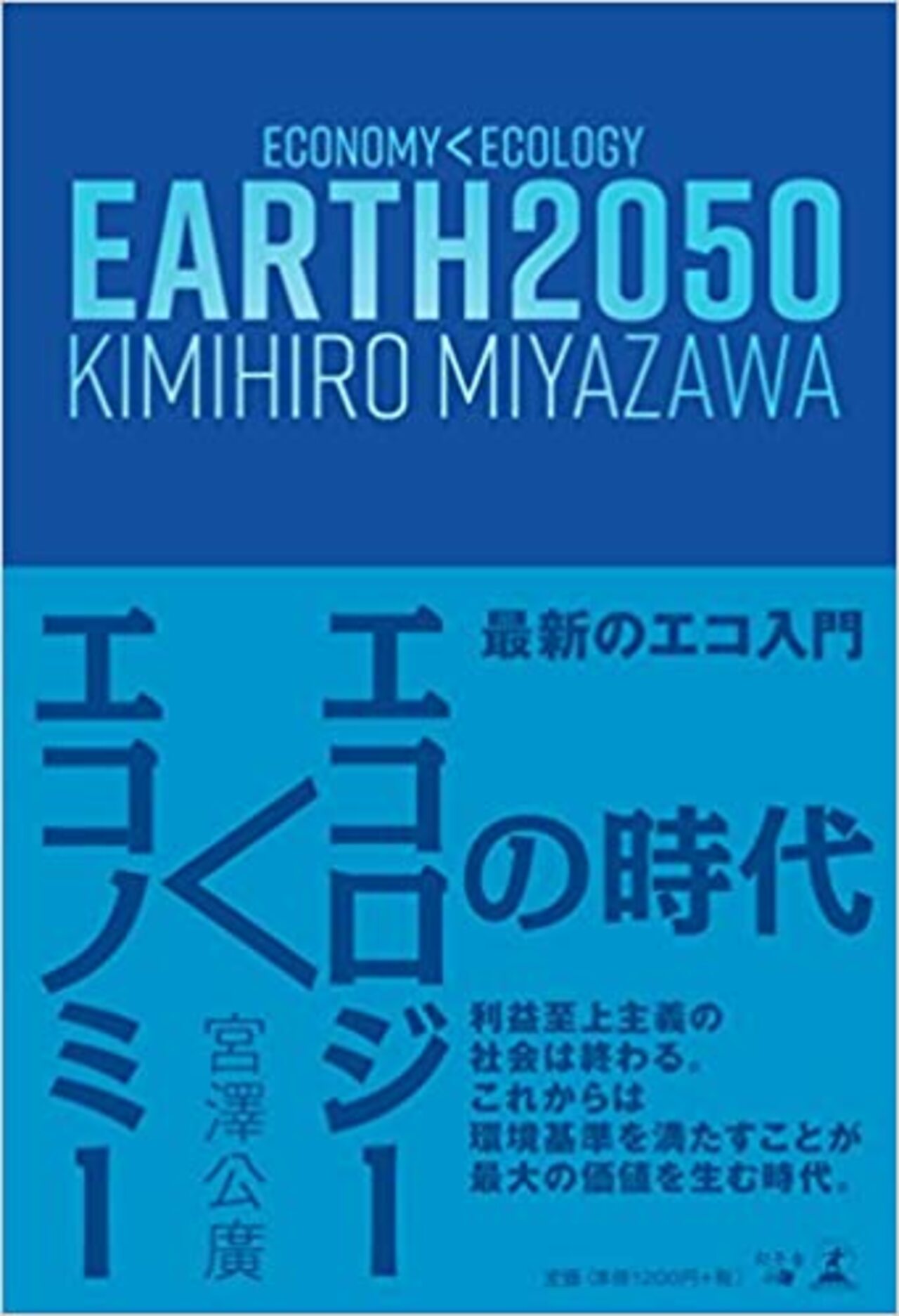第二章 奔走
【2】
近くを通りかかった店員に話を聞いてみると、どうやらアルバイトだったらしく、バックヤードまで店長を呼びに行ってくれた。五十代のでっぷりと太った店長は、やや面倒そうな顔つきを見せながら宮神の前に現れた。
「お忙しいところ、申し訳ございません。私、ユニオン通信社で記者をしている宮神と申します」
名刺を差し出すと、店長は目を白黒させた。
「何、記者さん? もう情報が伝わっているの?」
「消費者の方から情報をご提供いただきました。たまたまスーパーに寄ったら福豆さんの納豆がひとつもないので、少々気になりましてね」
「いやあ、さすがだなあ」
店長はハンカチで汗ばむ額を押えながら、意を決したように話し始めた。
「じつはね、福豆さんの納豆を買ったお客様から、大量のクレームが入りましてね。みなさん、口をそろえて『納豆に粘り気がない』って言うんです。それで私どもも、店内に陳列している納豆を調べてみたのですが、見た目こそ変わったところはないものの、箸でかき混ぜても粘りが出ない。これで何かあったら大変だと思って、系列店全体で福豆さんの商品をすべて返品しました。トラック四台分にもなりましたから、それはすごい量でしたね」
「福豆さんの方たちは、何かおっしゃっていましたか」
「早急に調査しますと言っていました」
「なるほど。お仕事中にありがとうございました」
「いえいえ。お役に立てればいいですけどね」
やはり何かある。宮神は確信した。
翌日、出社直後に福豆食品へ電話をかけたが、コール音が繰り返されるばかりで、誰も出る様子がない。神戸総局から福豆食品の本社までは、タクシーで三十分ほどの郊外だ。宮神は取るものもとりあえず、現地へ向かった。
到着した福豆食品は、工場が併設されているにもかかわらず、妙にひっそりとしている。正面玄関から入り、受付に行くものの、誰もいない。
「ごめんください」と言っても、返事がない。オフィスそのものが静まり返っている。
宮神は社屋を出て隣にある工場へ向かった。物音が聞こえてこないため不安になったが、かすかに何かのこすれる音がする。耳を澄ますと、その音は倉庫から聞こえてくるように感じた。
予感はズバリだった。ドアの隙間から中を覗くと、作業服を着た数人の社員が段ボールを山のように積み上げていた。どこもかしこも段ボールの山だ。おそらく、返品された納豆なのだろう。
そしてその周囲には、うなだれてへたり込む社員の姿が見られた。なかには今にも涙を流しそうな表情の人もいる。事態はよほど深刻なのか。取材をお願いしようと思ってやってきたのだが、この雰囲気だと声がかけにくい。
「どちら様ですか?」
不意に声をかけられて後ろを振り返ると、銀髪の男性が立っていた。目の下にははっきりと隈ができている。
「勝手に覗き見をして失礼しました。私は、ユニオン通信の記者で宮神と申します。じつは、読者から御社の納豆が糸を引かないという情報をご提供いただき、取材をお願いしようと参った次第です」
「通信社の記者さん……」
「そうです。アポイントも入れず申し訳ございません」
「記者さん、私たちを助けてください!」
「たすけ、え? 助けてとはどういう……」
目の前の男性に深々と頭を下げられた宮神は、ただただ困惑するしかなかった。