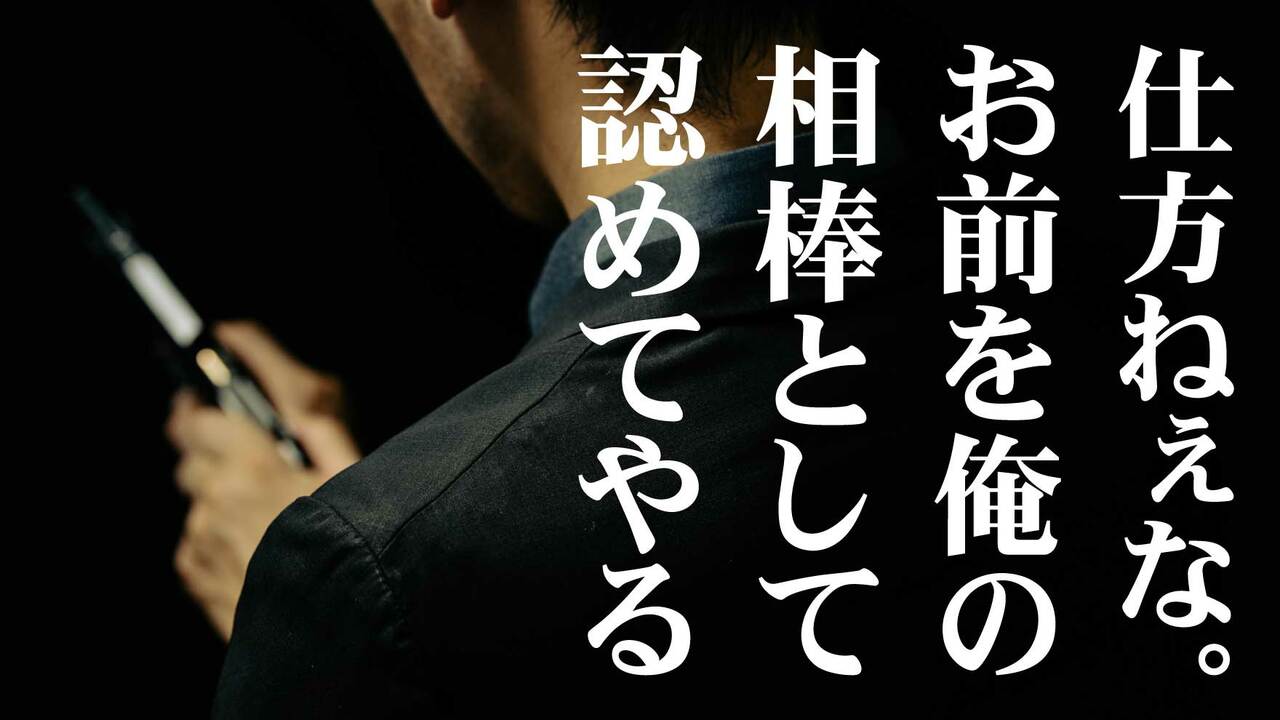暫く見つめ合っていた二人だったが、腕を掴む祖母の力がふっと抜けた。そして祖母は蹲り腰をかがめ、恭子の瞳を見つめた。
「恭子……、感情的になってはいかんぞ……。気持ちを抑えるんじゃ。ましてや、相手を殺そうなどとは絶対に考えちゃあ、いかん」
そして、何時もの優しい笑顔を浮かべた。
その笑顔を見て、恭子は張り詰めていた緊張から解かれ、無意識のうちに涙が頬を伝った。そして天を仰いで大泣きし始めた。
祖母はよしよし、と言いながら、恭子の頭を撫で続けていた。
何故祖母が自分に対して怒ったのか理解出来なかった。悪いのは、この砂場を奪おうとした男の子達だったのに。
理解出来ずに、幼い恭子は泣きじゃくった。
今病室で祖母を見つめる恭子は、その当時の出来事を思い出し、また別の疑問が湧いて来るのを感じた。
あのとき祖母は、相手が死ねばいいと私が思ったなんて、何故判ったんだろう……。そして、祖母が発した「それ」とは何だったのだろうか……。
当時は喧嘩をしてはいけない、という意味だと思っていた。しかし、それなら「喧嘩を」とか「そんな事を」と言うはずだ。「それ」などと言うだろうか……。
おばあちゃんが言いたかった、「それ」って……?
恭子は自分の手を見つめた。
手にはタクシーの運転手がはめるような白い手袋がしてある。
一年ぐらい前に、恭子は初潮を迎えた。
その際、祖母が与えた物だった。
他人の前では絶対に外さないこと。
ただそれだけを言って、恭子に手袋を付ける事を義務付けた。理由は今度説明すると言い残して。
それから間もなく、祖母は入院する事になった。
この手袋には、何の意味があるのだろう……。
突如、祖母の呼吸が荒くなった。
恭子は容体の変化を感じ、祖母に近寄った。
祖母は苦しげに身を捩り、突然酸素マスクを剥ぎ取った。
「おばあちゃん!?」
「い……痛い! ハア……ハア……。苦しい……」
祖母はベッドの上でもがき苦しんでいた。
「おばあちゃん!」
切羽詰まった大きな声に、祖母の瞼がゆっくりと開く。
胸を上下させながら恭子の方に顔を向け、視線を合わす。
「恭子……、かい……?」
荒い息をしながら、恐らく焦点の定まらない視界の中、久しぶりに祖母は声を発した。
「恭子……楽にしておくれ……」
恭子は祖母の寂しい言葉を聞いて、思わず手を握りしめた。
祖母にはまだ生きていて欲しい。
しかし、祖母の苦痛を取り除いてやりたくもあった。
医学的な方法が無い今となっては、取り得るその手段は、死――。祖母の身体から生命維持装置を外す事だった。
自分の希望と祖母の要求に葛藤する恭子の頬を、溢れた涙が伝う。