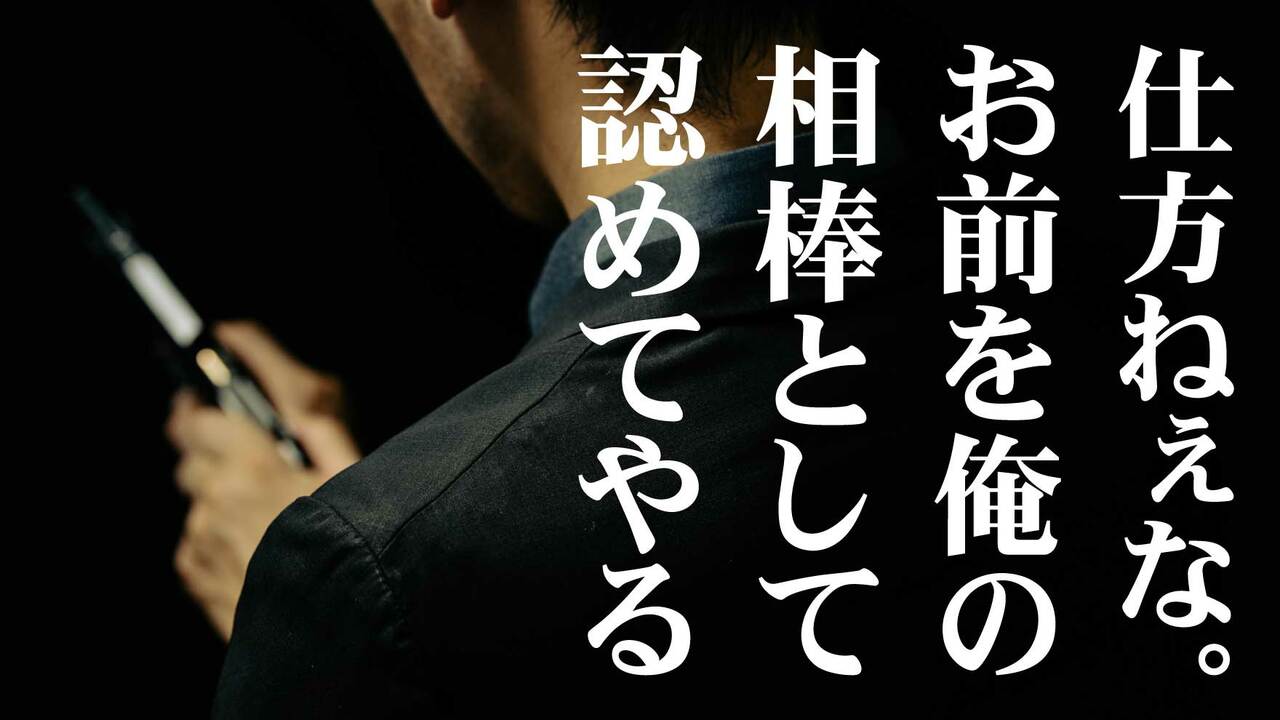第二章 恭子
少女は、生き物が大好きだった。
自然の中で育った彼女にとっては、ごく当然な事だったのかもしれない。毎日、自然を観察して遊んでいた。
動物。
昆虫。
植物。
そしてそれらが行う自然の営み。
彼女は幼いながら、生き物が「生きている」、という事が不思議だった。
昆虫は何故動くのか。
蟻や蛙は何がしたいのだろう。
彼女はそれを知りたくて、何度も捕まえようとした。しかし、バッタや蝶はそう簡単に素手で捕まえられるモノではなかった。
しかし彼女は諦めなかった。
自分の身体で、「生きている」という感覚を確かめたかった。
そして、ある日とうとうバッタを捕まえる事が出来た。
それはまるで、バッタが自ら自分の手に飛び込んできたような偶然だった。
彼女は、自分の掌の中で飛び跳ねるバッタの感触に興奮しながら家へと急いだ。
「おかあさーん」
母は夕食の準備中だった。
彼女は両手で包んだ掌を母親に見せながら、
「ほらっ」
と言った。
「なんなの? それ」
母親が振り返って訊ねる。
「バッタを捕まえれたんだよ? あたし」
母親はバッタが飛び出して来ると思い、一歩後ずさった。
彼女は気にする事なく、掌を開いた。
母親は思わず手で顔を庇う動作をしたが、彼女の掌に乗っているバッタはピクリとも動かず、横たわっていた。
少女はバッタを見つめた。
「あれ~? 死んじゃってる……」
少女は悲しそうな声を上げた。
「握りしめて、死んじゃったんじゃないの?」
母親はまな板の方に向き直り、そう言った。
「そんなことないもん! きょーこ、優しく運んできたもん!」
「それじゃあ、息が出来なくなったのかもね」
少女はバッタを見つめながら囁いた。
「……そんなこと、ないもん……」
少女はバッタを見つめながら台所を後にし、玄関で靴を履いて庭に出た。