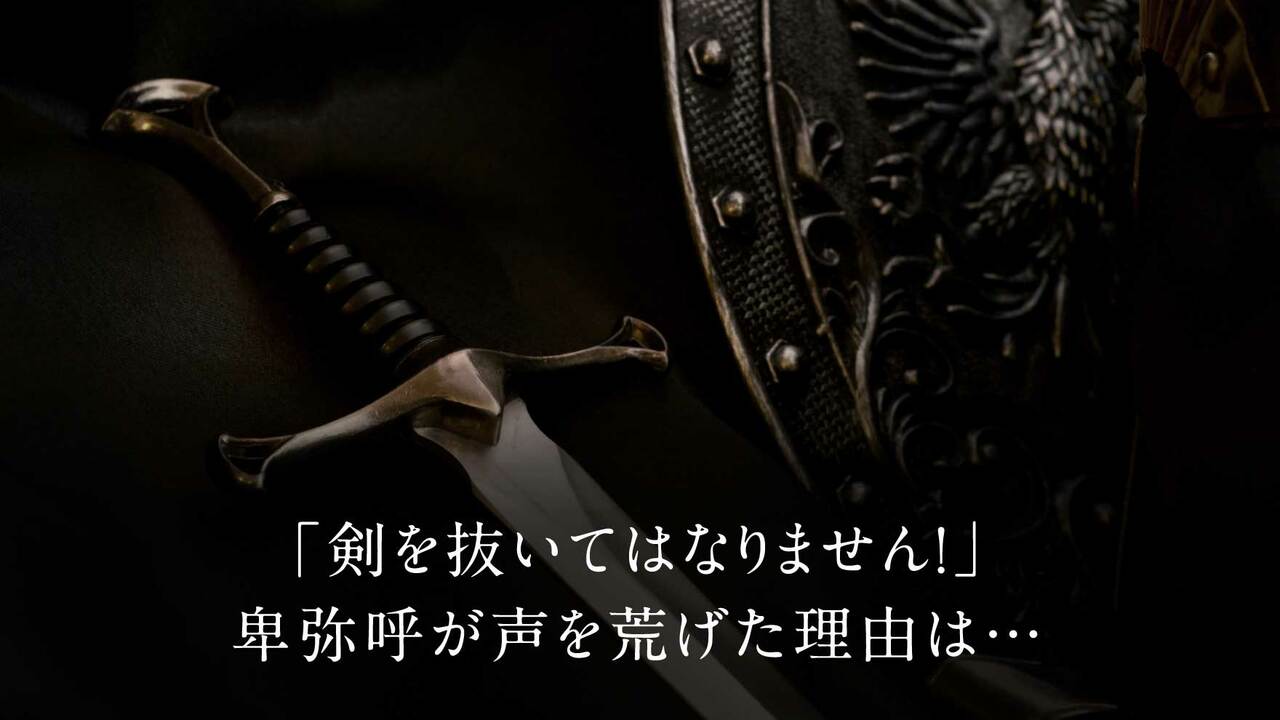【前回の記事を読む】体が勝手に動く…心に聞こえてくる声に導かれ、断崖の下に!?
第二章【反発】
覚悟を決めて中へ足を踏み入れると、暗くて先がよく見えない。やむを得ず勘を頼りに手探りでゆっくりと前に進んでいくと、徐々にではあるが周囲が見え出してきた。暗闇に目が慣れてきたんだなと思いきや、実は遠く上のほうから、微かな光が入っていたのだ。そこで後ろをついてきたはずの、レオの姿が見えないことに気づいた。
「レオ君、どこにいるのー」
呼んでみても返事がないし気配も感じられない、どこかにいってしまったようだが探している余裕はなさそうだ。レオは賢い猫である、きっと帰ったのだろうと、自分に暗示をかけ前に進むしかない。そんな明日美の心配を察して彼女が言う。
「レオのことは大丈夫です。心配ありません」
それを聞いてまずは一安心。ともあれ洞窟は広いといっても立って歩くのがやっとの空間で、入り口から続く岩にできた亀裂の延長といった感があり、それでも足元は白く舗装したかのようにほぼ平らになっていて、水が流れていたらしく薄明かりでも濡れて光って見えている。地震で水脈が変わってしまったのかもしれない。
進むに従って、視野の制約からくる反動なのか、明日美の方向感覚は研ぎ澄まされ、今いるところが祠の真下であり、そこは鍾乳洞だという認識を持ちつつあった。この先にどんな光景が待ち受けているのであろうか、県内に有名な鍾乳洞が数々あるとはいえ、明日美は地下というところも好きではなく、行った経験がない。それ故に鍾乳洞に関するイメージはよくないものばかりで、今の認識では次の通りである。
それは暗闇の中で誰にも知られることもなく、静かに水が流れ、それが一転して滝となり音を立てて流れ落ちていく、そこは冷たい地底湖であり、コウモリや奇妙な姿をした生物が巣くう光のない世界。一旦足を踏み入れると二度と戻れない迷路が続いている。そんな漠然とした先入観を持っていたのだ。しかもこのあたりまで来ると光はもう届かない、先はもう何も見えなくなってしまった。
「どうすればいいの、私はコウモリじゃないのよ、見えないところには進めないわ」
明日美が聞くと、
「見えないのなら見る必要はないわ、目を閉じなさい、そして心で感じなさい、私が案内します」
彼女がそう答える。
「やっぱコウモリと一緒じゃん」
さらなる命令口調に明日美は不貞腐れ気味に言うのであった。それでも言う通りに目を閉じてみると、驚くことに身の回りのほんの少しの空間ではあるにしろ、鮮明に見え出してきたのだ。ところがどうしても違和感があり、しっくりとこない。何かが違うと感じて、目の前の風景に見入ると、
「なーんだそういうことか」