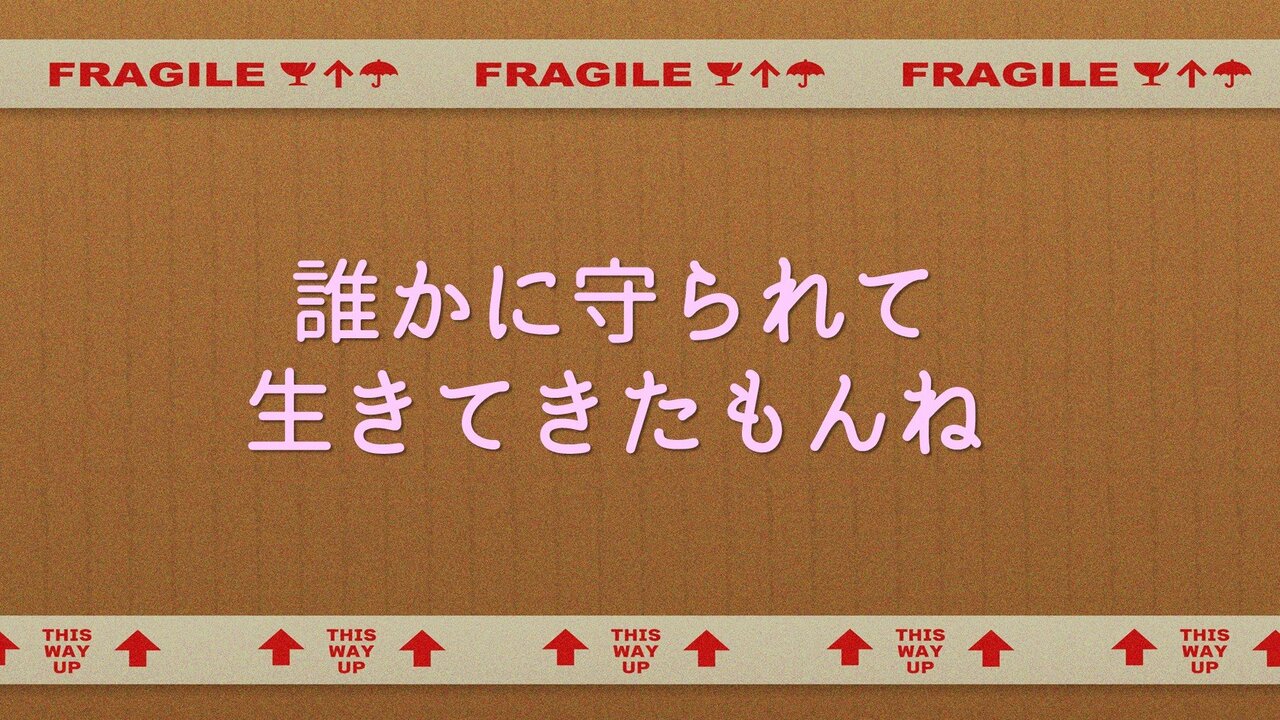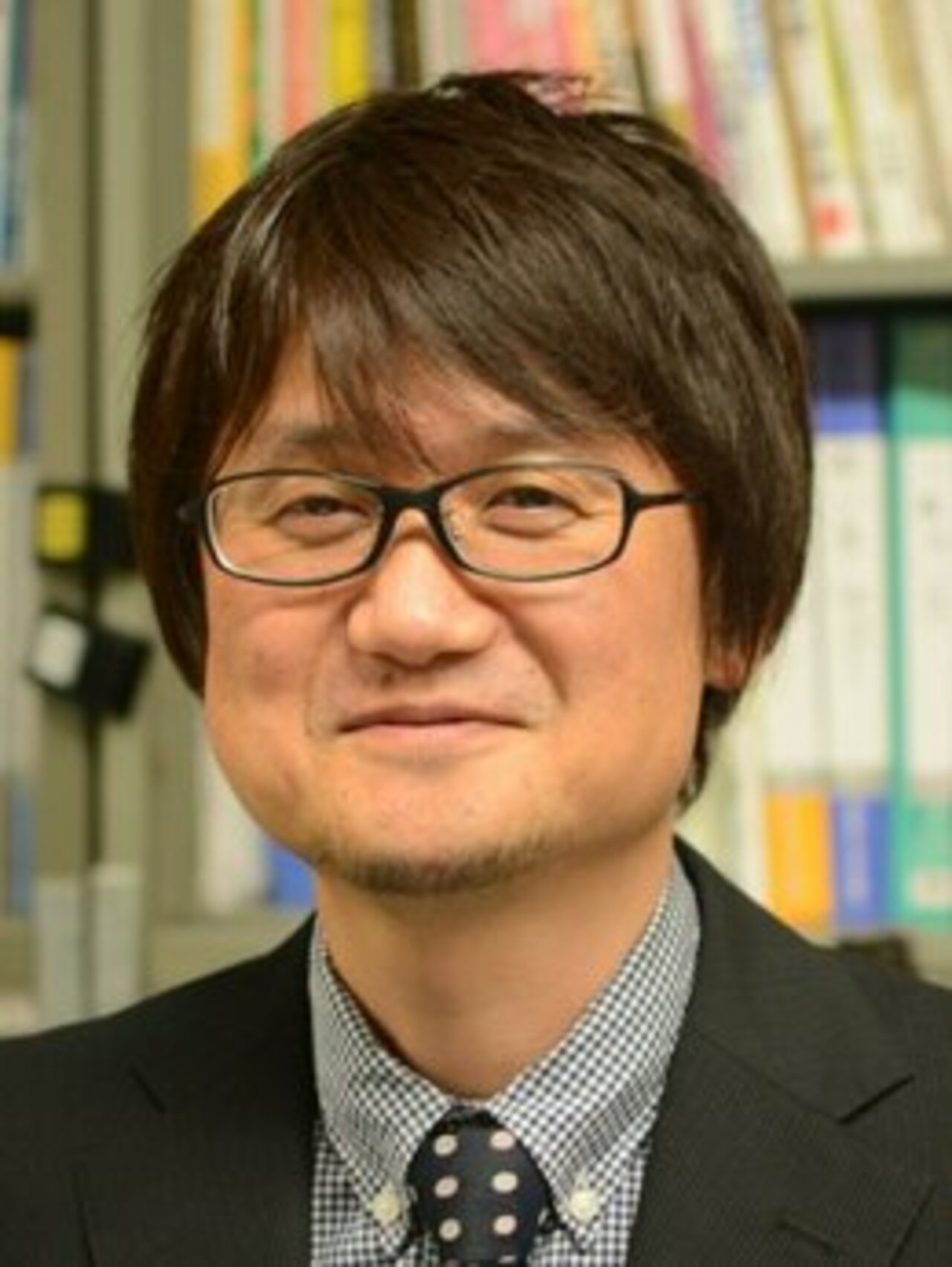第2章 解釈
3
「ケントくんは俺より2年も余計に学生してたから、組織の中で、責任のとり方って考えたことないよな。誰かに守られて生きてきたもんね。教授とか研究所の所長とか。ストレスってないだろ? 社内での人間関係のストレスもあるけど、社外の人間と関わる外勤も、相当ストレスあるんだぜ。中にはすご〜く嫌な客もいるわけだよ。“そうですね”って同調して会話合わせるけど、頭の中じゃ“こいつ何言ってんのかなぁ”って思うよね。顔には出さない訓練できてるから相手にはさとられないけどね。
そういう生活してストレス溜まるから同窓会やりたくなるんだろうね。きっと。腹の探り合いしなくていいからね。もともと相手の性格なり性質を知っているからね。まあ、同窓会もその時点で幸せな人間しか参加しないけどね。会社をクビになったとかだと参加しにくいよね。警察に捕まったとかなら、逆にギャグとして参加できるかもだけど」
ユウは同窓会に出席したことがなかった。幹事をまかされそうになったが、仕事が忙しいのでと断った。大学時代の仲間に会うのが嫌だった。
「だから真面目に生きた方がいいんだよ。ケントくん。長いものには巻かれろっていうだろ」
ケントが手のひらをこちらに向けて言葉を遮った。
「わかったよ、わかったよ。で、1ついいかな? ハラール認証が発行されたってことは間違いなくハラールな食品と言い切っていいんだよな?」
「もちろんですよ。我が社の基準では間違いなくハラールですよ。でもなんで今さらそんなこと聞くんだよ」
運ばれたコーヒーのスティック・シュガーをつまみ、上端を指でちぎった。その様子をケントがじっと見ているようだった。
「もうちょっと具体的な話をしてもいいかなぁ。ユウ。食品加工技術についてなんだけど。最近の進化はすごいよね」
「まあ、そうだよな。で?」
「数年前にはなかった食品添加物もあるわけじゃない。新しい香料とか」
「そりゃね、最終商品を作らないけど技術力の高い小さな食品関連会社ってたくさんあるからね。何が言いたいんだよ。ケントくん」
「だから、僕たちだって大学卒業して数年経つからね。その間に知らないけど新技術でものすごい食品添加物が生まれてる可能性はあるよね。食感改良剤とか。ニーズがあればそこに商品を提供するのが営利目的の企業だからね。“あれっ? 気づかなったけど、こんなところに豚脂、ラードの分解物が使われていた”とか、後になって気づくこともあるわけでしょ」
「ケントくん。わかったよ。言いたいことが。“だから君にもハラールかどうか判断できないでしょ”ってことだな」
「そうは言ってはないけど……」
「ケントくん。ご心配には及びません。前に話したように、我が社にはイスラーム教徒の専門家がいますので。彼女はチームを組んでいます。宗教の専門家、いわゆるイマームのような方、食品加工の専門家で大学の教授もメンバーです。それにビジネスの専門家、MBAホルダーの方。この三者が主力メンバーでハラールを判断しますので。全く問題ございません。御社は安心して我が社に発注くださいませ」