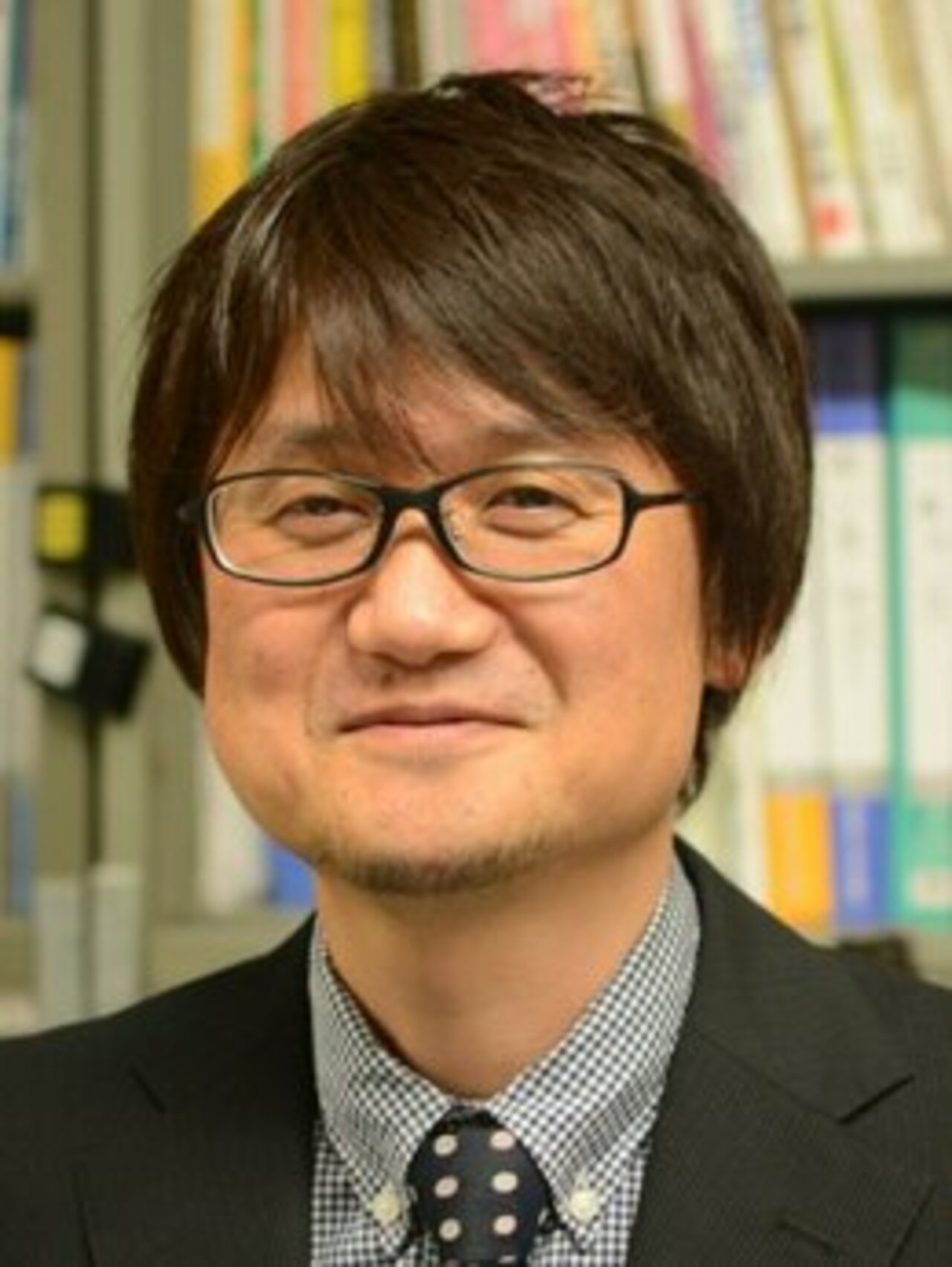第2章 解釈
3
ユウは会社で電話の対応に追われていた。ケントのハラール商品が売れるのに伴って、ユウの会社への問い合わせが増したのだ。電話での問い合わせに加えて、毎日何通ものメールが届いた。
ユウは大学時代を思い出していた。自分が頼りにされている、という充実感があった。真夏のような暑さが続く9月下旬、ケントから電話があった。話がしたいので出てこられないか、とのことだった。断ってもよかったが忙しさから逃れたいという思いもあり、会うことにした。
事務所での電話対応を同僚に頼み、指定された喫茶店に向かった。ケントはすでに店にきていた。窓側の席に座り、紅茶を飲んでいた。
「悪いな。呼び出しちゃって」といつものように清潔感のある声質と姿勢でケントが言った。この暑さなど全く感じさせない爽やかさがあった。それがかえってユウを苛立たせた。
「どうしたのケントくん。事務所じゃ話しにくいことなんだろう?」
「そんなことないけど。たまにはいいだろ。ユウのとこも忙しいんじゃないか? ハラールがちょっとしたブームになってるから」と言って笑顔を見せた。
「おかげさまで、ですよ。ケントくんの会社で大々的にハラール認証の宣伝してくれてるからね」
「問い合わせも多いんだろ?」
「そうだね。急増だね。あまたあるハラール認証団体の中から、かの有名企業が選んだのが我がイスラームビジネス研究所だからね。信頼性も跳ね上がったよ」
「難しい問い合わせもあるだろ?」と言ってケントがこちらを真っ直ぐに見た。
「難しいってどういうもの? ケントくんの言うところの?」
「判断に迷うような。ハラール基準を本当にクリアしてるのか、とか?」
「それは全く心配ないよ。我が社にはマレーシア人の専門家がいるからね。イスラーム教徒の彼女の判断が絶対だからね」
「彼女?」
「そう専門家の彼女」
「男性じゃなくて女性? その専門家は?」
「ケントくんも古いね。男性か女性かを気にするなんて。マレーシアとかインドネシア、タイとか活躍してる女性はたくさんいるんだよ。女性天皇を認めるかどうかで大騒ぎなのは世界基準からは、ズレてるよね」注文を取りに来た店員にユウは「コーヒーひとつ」と言った。
「日本が特別に男尊女卑なんだよ、未だに。キチンと責任を取るリーダーシップがあれば、男女関係なく尊敬されもするし、会社とか組織で上に立てるんだよ。ケントくんに責任を取る度胸ある? まあ、ないかな。それに比べたらおたくの女性上司。鈴木さんだったよね」と小指を立てた。
「あの人なら責任とってくれそうじゃない。何か問題が生じてもさ」ケントの顔はまんざらでもなさそうだ。もしかすると2人は付き合っているのかもしれない。幸せな人間はますます幸せを掴んでいく。一旦、不幸になればどこまでも不幸が続く。不幸のきっかけを作ってやりたいと思った。