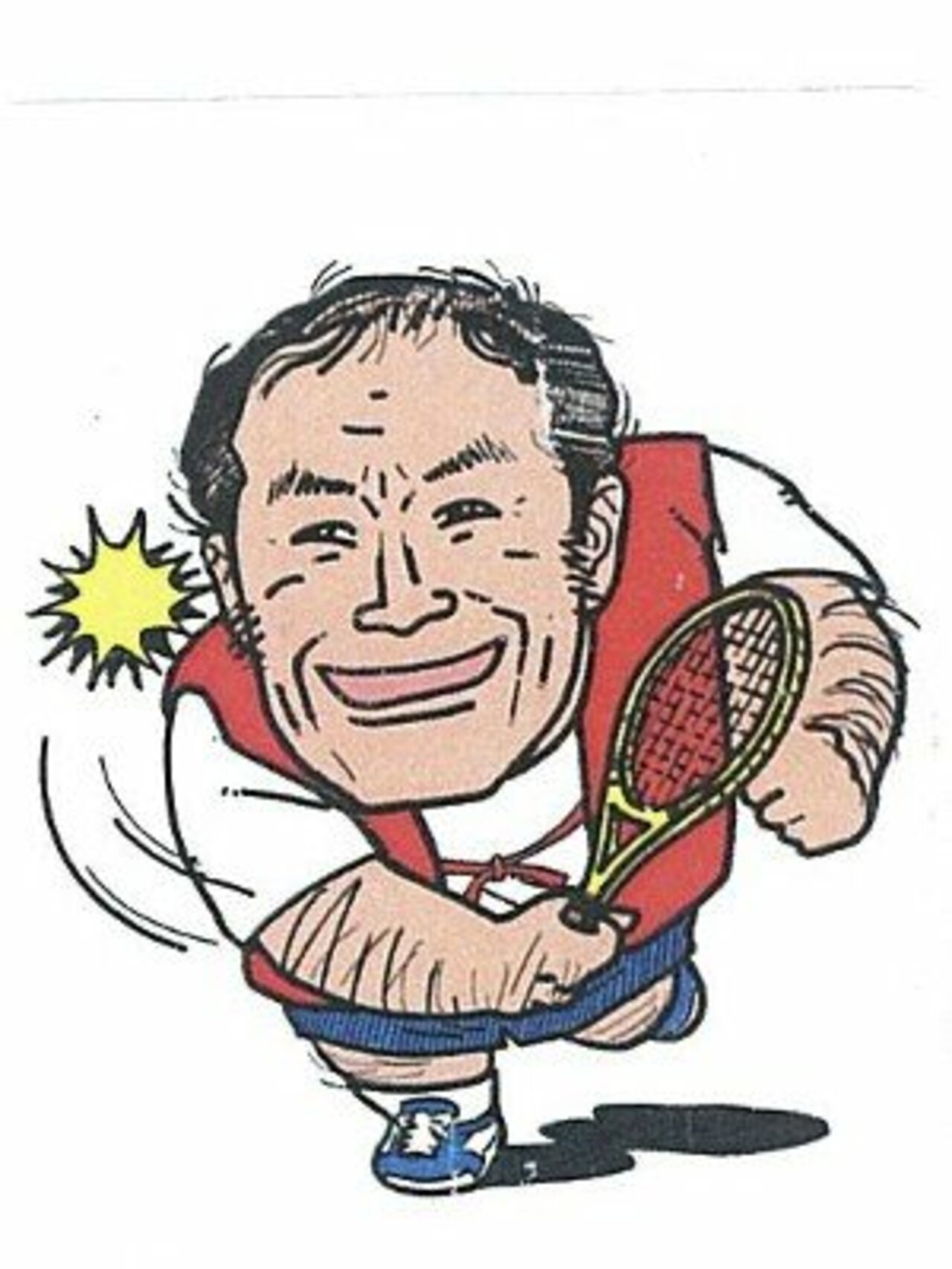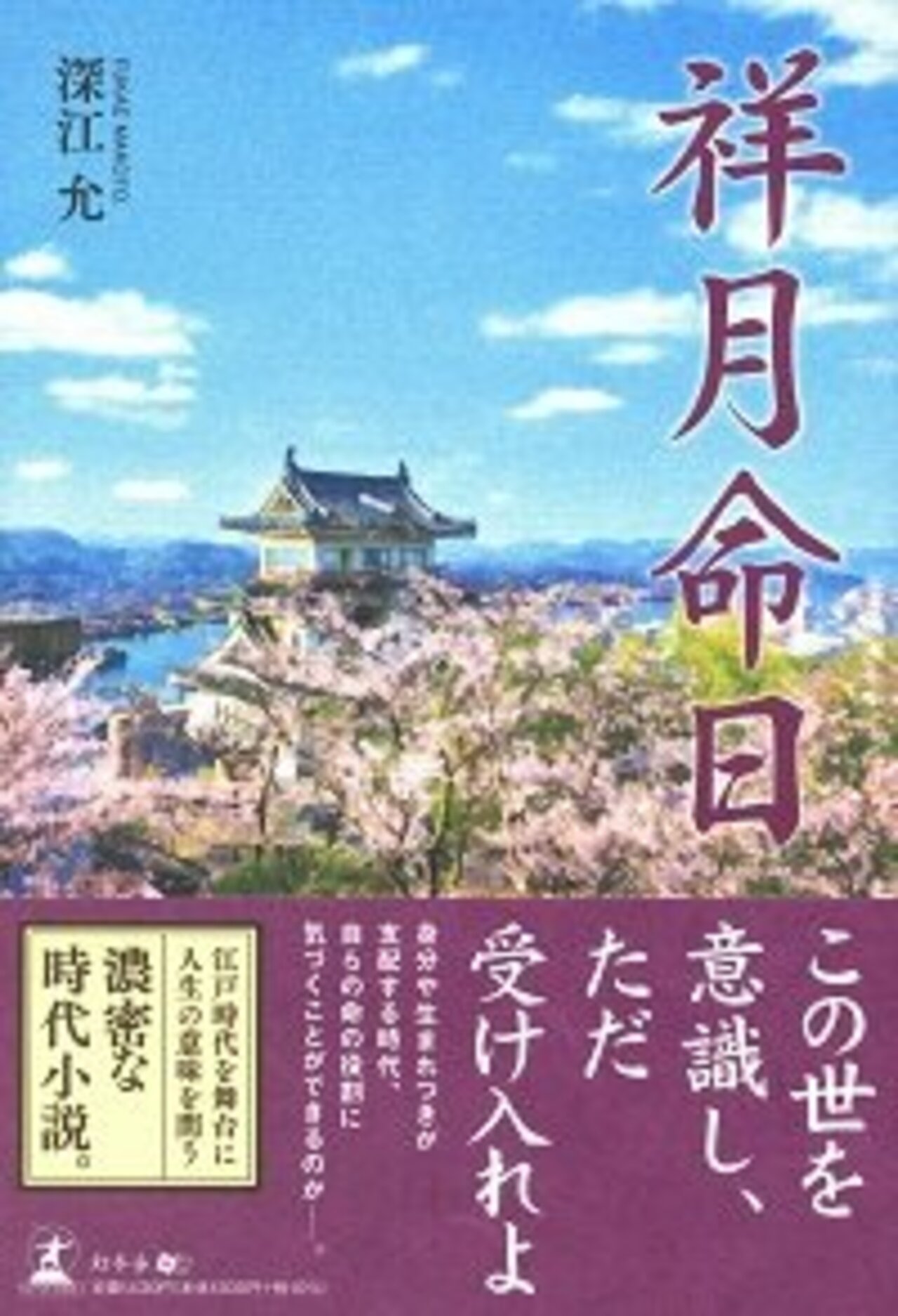和木重太郎、修行へ
重太郎は江戸に剣の修行に出ることを決めた。家は決して裕福ではない。それでも、重郎左衛門は自分と同じくらいの背の高さになった重太郎が、自分がたどってきた道とは違う道に進もうとするのを理解し、重太郎の願いをかなえようと、加持惣右衛門に江戸で内弟子にしてもらえる道場を探してもらったのだ。
重郎左衛門は勘定方の郷方廻りで身分は低かったが、小さい頃から近くの立花道場で修業し、藩内でも指折り数えられるほどの腕前だった。そのおかげで、知人も大勢いた。まだ若いが、藩きっての使い手である用人の加持惣右衛門もそのなかの一人である。
加持惣右衛門は、まだ新宮寺司という名で江戸に出ていたときに世話になった本所松倉町近くにある念流美濃島道場への紹介状を書いてくれた。
「重太郎。体には気をつけるのですよ」
母親の満は親離れして前に進む重太郎を心配しながらも、涙も見せずに江戸への出立を見送った。心の内は寂しい思いでいっぱいである。それをおくびにも出さない見送りだった。
重太郎は母親の気持ちが痛いほどわかりながらも、自分の道を進むと決心していたから、母親が涙を見せず送り出してくれたことに感謝した。
出立するに当たって、母親に宛てて文を書こうとは心に決めていた。それは父親からの言いつけでもあったからだが、黙って送り出してくれた母親にせめてものことと思ったのだ。
勘定方の郷方廻りだった父親の重郎左衛門は、物心ついた頃は、冬場はともかく、海浜地区の農事の見回りでほとんど家にいなかった。それでも、重太郎は自分が望まれて生まれてきたことを感じていた。
満は、いつも怪我はしないだろうか、体を壊したりしないだろうか、風邪をひかないだろうかと気遣い、心配している。だからと言って、それを表に出して重太郎を縛ろうとはしなかった。
いずれは巣立ち、親離れする。早くては親の愛情を知らず、粗野に育つかもしれない。遅ければ、独立心が育たない。江戸で剣の修業をしたいと言い出したときは、何かあったのかと思ったが、少し早いと思いながらも、独り立ちするのを邪魔するつもりはなかった。
ただ、心のなかにぽっかり穴が開いたような寂しさを感じたことは否めない。
江戸行きを望んだ重太郎は母親の想いに応えて、三月に一度くらいの割で母親に文を書いた。
重太郎が藩主義政の稽古相手をするようになったのは、重太郎が母親に文を出そうとして、たまたま藩の中屋敷を訪れたのがきっかけだった。
しばらくぶりで母親あてに文を書き、それを託そうと浦紗屋、阿佐美屋を回り、藩下屋敷も行ったが、託す人がいなくて藩中屋敷にまわった。門番は重太郎の顔を覚えていて、少し待つように言い、なかに連絡してくれた。それで、帰藩する藩士が剣道場にいるから、そちらに向かえと教えてくれた。
重太郎は中屋敷の剣道場に入るのは初めてだった。訪いを告げると、上がって待てと言われ、道場に入り隅に座った。
道場の中央では、義政が立ちあっていた。重太郎は参勤交代のときに遠目でだが顔だけは知っていた。相手をしているのは加持惣右衛門である。
「いまの呼吸でございます」
息継ぎをすると隙ができる。だから、息継ぎは相手に合わせてする。そのうえで、一呼吸の間に連続で技を繰り出すための稽古であろうと思われた。
重太郎は惣右衛門の言わんとするところがわかった。義政も相当な腕前と見たが、重太郎が目を見張ったのは、少しの無駄も力みもなく流れるように動いている惣右衛門の動きだった。
重太郎が念流美濃島道場の内弟子になれたのは、加持惣右衛門のおかげであるが、実際には面識がなかった。加持惣右衛門のほうは師範代の近江橘に重太郎のことを聞いていて、その実力を良く知っていた。